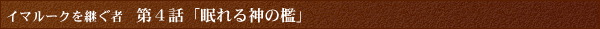 |
| |
◇
|
| |
庭に乾いた音が響いた。
その音に引き戻されるように、ミラールは顔を上げる。
日は傾き、あたりは赤く染まり始めていた。風が冷たい。
「そろそろ、帰ります」
仕切りなおすようにリタに微笑む自分がおかしかった。
リタが慌てて涙を拭う。
「ごめんなさいね。なんだか、おもてなしできなくて」
「十分です。
久しぶりに……いろんなことから離れることができました」
心の底からそう思い、思ったことを素直に口にしていた。
「……もう少し、いらして? フェリシャもこんなときにどこに行ってしまったのかしら」
リタがそう言うのに、ミラールは首を振った。
「いえ。仲間が待っていると思いますので。
彼女にはよろしくお伝えください」
「仲間」
「ええ」
ミラールはそう言って、立ち上がった。
「今は一人では、……ないので」
リタがこちらを見つめている。言葉の端々に現われる思いを、彼女は優しさで見つけてしまう。
ミラールは苦笑をした。
「僕は母を知りませんが、その……」
そう言ってミラールは、こちらをじっと見つめているリタの視線に気付く。
「あああ、すみません。僕の母というほどのお年では……」
「若く見えるという意味なら、光栄ですわ」
微笑んで、リタはミラールを見送った。
「また、機会があったらお寄りになって」
「いえ、多分……。
……はい、必ず」
言い直したその意味さえ、彼女には分かってしまうだろう。
もう、会いに来ることはない。
断ちがたい時間であり、断たねばならない時間でもあることをミラールは不思議に思っていた。
振り返らなかった。
屋敷を出て、宿までの道を歩いた。
灯りだす家の明かり。
日の傾きに追われるようにして家へ戻る子供の声が、耳に残る。
歌いたい。
そう思った。
この思いを、歌にしなくては溢れてしまう。
帰りたい。
(どこに)
家へ。家族のもとへ。
(家族?)
セアラも、
ランも、
(家族なんかじゃない)
張り裂けそうな気持ちになる。
暖かな家庭。
長い影がミラールの目の前を揺れ、そして、開かれた扉の中へ吸い込まれていった。その後に続く笑い声。
なんて、辛い風景。
拳を握り締めた。
ぽんっと背中を叩かれ、ミラールは我に返る。
そして、振り向くと、大きな瞳が目に入った。
「フェリシャ……」
「ありがとうって、言い忘れてたの」
にこりと笑う少女が有難かった。
不安と孤独と、そういうものから気がまぎれた。
「いいんだよ。
僕が勝手に帰ったんだから」
「これ」
フェリシャが手をぬっと突き出す。そこには一本の笛が握り締められていた。それをみて、はっとする。
「あれ、僕、忘れてきたのかな」
手に隠されながらも認められた彫刻は、自分の見覚えのあるものだった。だが、少し違和感を感じる。
木目が……。
「違うよ、これ。
探していた笛」
「探していた笛?」
「リタの」
ミラールは、はっとした。
フェリシャが部屋を出て行ったときに言っていた笛か。
『リタ、その笛はふけないっていうの。
音が出ないって』
「音が出ない、リタの笛?」
「そう。
でも変なの。出るの」
フェリシャはその笛を、小さな唇に当てる。
弱弱しいが、確かに音が鳴った。
「ね?」
首を傾けるフェリシャを、ミラールは瞬きもせずに見つめている。
「フェリシャ、その笛を見せてくれるかい?」
「いいよ」
ミラールは笛を受け取り、自分の笛を取り出して並べてみた。
色が似ている。
彫刻も……。
ミラールの手が震えだした。
「お兄ちゃん?」
表情が強張っているのだろう。フェリシャの呼びかけに影を感じる。
彫刻は同じではない。
けど、これは……。
二本の笛が一本になるように並べたとき、その彫刻の柄がつながる。
蔓と花の柄なのだが、リタの笛に咲き乱れる花が、ミラールの笛につながっていた。ミラールのほうに花は少ない。
『そうね……。蔓……と、花かしら? 小さな、花』
リタの声が頭で響いた。
「フェリシャ」
少女の肩にそっと手を置く。安心させるようにミラールは微笑んだ。
「暗くなってきたから、送るよ」
「うん」
小さな少女が差し出す手を握り締め、ミラールは彼女の鼻歌を聴きながら、先ほどまで歩いてきた道を戻る。
本当の家族が分かるかもしれない。
リタが……、母かもしれない。
それは希望のはずなのに。先ほどから胸を打つのは警鐘だった。
戻らない方がいいと思うのは、自分が希望に、慣れていないからだ。
そう言い聞かせて、足早に歩く。
フェリシャが居て、よかったと思った。喚き溢れるものが、小さな手の感触で抑えられている。
しかし、屋敷に近づくにつれ、足は重くなっていった。代わってミラールよりも先を歩いていたフェリシャが振り返る。
「お兄ちゃん?」
「ごめん。ちょっと疲れてきたかな」
心配そうに覗き込む少女にそう言いながら、ミラールは一歩一歩確かめるように歩く。
フェリシャと出会った場所で、ミラールは立ち止まった。
歌が、聞こえてきた。
空気を伝い渡っていく響きが、ミラールの身体を締め付けた。
こんなに心を揺るがす歌を初めて聴いた。
歌っている人物は直ぐに分かった。庭に出て茜色の空に歌を響かせているのは、リタだった。
黒い服と下ろした黒い髪が風に揺れていた。
(魂を送る歌だ)
立ち尽くすフェリシャの手を離し、ミラールは自分の顔を両手で覆った。
魂の安らぎを願い、残された人々を慰めるための歌が、哀しみを掻きたてる。
これは彼女の歌か。自分の歌か。
わからなくなる……。
「リタ!」
フェリシャが彼女を呼ぶことで、歌は止んだ。
ミラールは気付いた。自分が泣いていることに。
自分の中の思いはとめどなく溢れる涙を、拭うことさえ禁じた。
驚いたようにこちらを見たリタの表情は、すぐに安らかなものになる。
「フェリシャ。お母様が探しておられましたよ?
すぐに帰って差し上げて」
「でも……」
フェリシャはミラールとリタを交互に見て、幼いながらに何かを感じ取ったのだろう。わかったと小さく呟くと隣の家へ走って帰ってしまった。
リタはその小さな影を見送ったが、ミラールは見送る彼女を見つめていた。
扉が閉まる音がして、ようやくリタはミラールの方へ顔を向け、頭を下げる。
「つまらない歌をお聞かせしました」
消えてしまうような声に、ミラールは涙を拭おうともせず聞き返す。
「ミレリータさん……ですね。
歌姫……。ミレリータ=ユウ=シス、でしょう?」
リタは肯定も否定もしなかった。ただ、長い時間を置いてぽつりと呟いた。
「何年ぶりでしょう。こんな風に歌ったのは」
「あなたは僕の……母ですか?」
リタの言葉に重ねるように問うミラールの言葉に、彼女は小さく首を振った。
「子供は一人だけ授かりました。だけど……」
「僕の名はあなたの名前からもらったものです。
そして、僕の育ての親は、セアラ=ロック=フォルタニー、です」
リタは目を瞑った。痛みをこらえるように瞑り、そして、ミラールを見つめる。暗い瞳だった。
「懐かしい名前です。
セアラ。セアラ=ロック=フォルタニー……」
「では、やはり」
しかし、リタは再び首を振った。今度は強く。そして、ミラールから目をそらし、茜色の空を見上げる。
「私はセアラをよく知っています。
彼の元でしばらく暮らしていたこともあります。
そして、彼の元で私は一人の子供を産みました。
彼の子供でもないのに、あの人はその子の誕生を心待ちにしてくれた」
「……あなたがっ、僕の……っ!」
リタはもう一度首を振った。
「私も、貴方が私の子供かもしれないと思いました。
あの子を失ったことを、一瞬でも忘れるなんて。
あれから私は、あの子のためにだけに歌うと誓ったのに。
あの子の魂の安らぎを祈るためだけに……」
「僕は生きている!」
「違うの。違うのです。ミラールさん。
貴方のはずがない。
あの子は生まれて直ぐに……」
リタの手がゆっくりと上げられる。両掌を覗き込んでから、リタは胸に両手を押し当てた。
「この腕の中で、冷たくなっていったのだから」
肩が震えた。リタの睫毛が光るのを見た。零れ落ちそうな涙が、風に飛ばされて消えた。そんな細かなことを見つけられる自分と、肩が震えるほど動揺している自分の差を奇妙に感じていた。
その向こうで、リタは消えるような声で続ける。
「生まれたら『ミラール』という名を。
優しい子になって欲しい。
父親の名を教えることも出来ない愚かな母だけど、せめて名に願いを込めることぐらいは許してほしい。
そんな風に思っていました。
だけど、あの子は冷たくなってしまった……」
リタはそう言って悲しく微笑んだ。
「貴方が目の前に現われたとき。
生きていてくれたのだと思ったのよ。
『ミラール』と名乗ったとき、本当に嬉しかった。
自分の持っている笛と対に作ってもらった笛を貴方が持っていたとき、確かに自分の子供ではないかと思った。
けど。あなたの後姿を見ながら、私は思い出した。
私の子供は死んでしまった。
鼓動が消え、この腕の中で……冷たく、なっていった……」
リタはミラールへ視線を向けた。空ろな瞳に、ミラールは少なからず動揺する。吐き出すような声で、リタはミラールを問い詰める。
「貴方は、誰?
セアラに頼まれたの?」
「違います……」
「17年も経って、こんなところまで……。
あの人は何を?」
「……違う」
「穏やかな愛情。
子供を失う悲しさ。
それ以上に何が見たいと言うの。
現実と偽りの差もわからなくなった、愚かさ?」
「違う」
リタは一歩踏み出した。
「……あなたは、誰?!」
その言葉を受け、ふらついた身体を支えた。
誰と問われる度に、目の前の揺れが強くなっていく。
誰。
『死んだはずの子供』
セアラ。
僕は。
誰?
『ミラールはまだ知らなくていいんだよ』
『忘れるがいい』
『その時が、来るまで』
|
|
| |
|