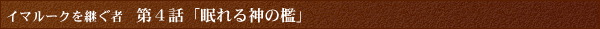 |
| |
|
|
| |
|
VII 眠れる神の檻
重苦しい雨。一粒一粒の痛みを布越しにも感じるほどだ。
ぴしゃりと足元で音がした。水溜りに一瞬足を取られる。胸に抱いていた布の包みを取り落としかけて、慌てて強く抱いた。
顔を、手を、足を打つ冷たさの中で、その包みの暖かさと重みだけが現実と希望だった。
『お願いします』
託されたのは重み。命、願い、母の思い。
遠い人だった。汚す必要もない、針の傷みも知る必要のない、美しい手から託された願い。
何の利益もない危険な賭けだったのに、その願いを受けたのはあの子守唄が美しかったからかもしれない。
『生きて……』
その切実な願いに心打たれたのも事実。その翳りを帯びた視線を前に、断りきれなかったのは何故だろう。
胸に抱いた命のその存在感に、『必ず』と言葉にして誓った。
だけどその思いとは裏腹に、徐々に足取りが重くなっていた。いつもなら風を含んで軽く揺れる布が、雨を吸って冷え込み、身体に重くまとわりつく。
雨の音とは明らかに違う、ざわつく背後を振り返った。
必ず届けると誓ったのだから。
前をしっかりと見据える。
もう少し。
もう少し。
自分の息の音が耳に響いている。激しい動悸。
重い。腕も、足も、肩も……。
ふと、白い光が目に入った。
見上げれば、頭上に覆いかぶさらんばかりの白い花の群生。闇夜に浮かび上がるほのかな光に見えた。
『目印は、白い花』
ばしゃんと耳元で水音がした。地面に叩きつけられる雨の音が近い。そして、自分が倒れていることに気付く。
重い。冷たい。痛い。
胸にある暖かな存在を、懸命に掻き抱いた。
届けます。
あなたの大切な子供。
あなたの美しい、子守唄と共に……。
「無茶な人だ」
赤い瞳が微笑んだ。
「君も、母親になるのでしょう?」
◇
ふと目覚めた。ぶるりと体が震え、冷え切ってしまった身体を実感する。床に落ちていた肩掛けを拾い上げて、頭から覆いかぶせた。
目を瞑ると思い出す。指先に絡みついた濡れた髪の冷たさを。今の自分以上に冷え切った細い肩の頼りなさを。
そして、守るように抱いた存在のまぶしさを。
彼女自身の身体に宿った、細い命の光を。
目を開けて現実を確認するように自分の肩を抱く。肩に食い込む指の痛さで、夢であったことを思い返す。
(なんとも懐かしい夢だ)
そう思いながら、ふと唇に笑みを刻む。
懐かしく、そして、暖かな気持ちになる。
彼女が命がけで運んだ二つの命。
セアラは頬杖をついて、卓上に飾られた赤い花を見つめた。
右手を上げて、目の前で軽く握り締めた。
一瞬だけ、この手にしたと思った。
ほんの、一瞬だけ。
(許されは、しなかったけれど)
落とした右手を見つめ、目を瞑った。
冷たい刃物の輝きと、押し殺された叫び声と、自分の瞳の赤。床に広がった赤い液体。その中に落ちた赤い石。緑色の瞳の間を流れていく赤。
その「赤」が瞑った目の前に広がっていた。
無駄だと呟いた自分を、見つめていた瞳の強さを思い出す。
愛しいと思った。
強い光。強い心。逃げ出そうとするその意志さえ、可能性に続くだろう。
名を呼ぶこと。
そして、出会うこと。
そこから掬い取る一欠けらの思いさえ、この世界への慈悲となる。
(それが、私の、ささやかな贖罪と願い)
セアラは髪をかきあげて、再び赤い花を見つめていた。
こんなときに感じる静けさは、深く暗い思いを覗き込んでいる気持ちになる。不快ではない。ただ、長く生きてきたことを思い出す。
何でもいい。他者の発する音や気配が欲しい。そう思いながら、耳を澄ます。小さな足音。遠くから届く微かな声。風に揺れこすれあう木々の音。そういうものを追いながら、気持ちを取り戻していく。
そんな風に回りに神経をめぐらせていたとき、全身にかかる重圧を感じとった。空気を震わせ、そして、体の芯へ伝わってくる力は、自身が力のある魔術師だからこそ分かる存在感。
迫る力の元を探って、セアラは思わず笑みを漏らした。
部屋の外へ控えているだろう侍従……つまりはゼアルークから向けられた監視役なのだけども……に、その力を持つ者を、こちらの部屋に招くように命じようかと思ったが、立ち上がった。
多分、『すっぽかされる』ような気がしたからだ。その存在に畏怖、または敬意や好意を与えられている自信はなかった。
扉を開け放ち、躊躇せず、足早に廊下を進むと、慌てた侍従の声が後ろから追ってくる。今日はずっと部屋にいると、約束されたではありませんか! まるで子供に言うかのような口調の監視者を振り返り、セアラは花開くような笑顔を向けた。
「君とは約束してないよ。ゼアルークとの約束は……」
思わずその笑顔に見とれる監視者に背を向けながら、笑いを含んだ声を残した。
「破るためにあるんだ」
セアラはその力の元へ吸い寄せられるように向かっていく。
求める先にいるのは、キャニルスという家が生み出した最高の結晶だ。闇《ゼク》を宿すからという理由だけで、その本当の価値の分からぬ人間が蔑み続けた、美しい闇《ゼク》の持ち主。
自分の足が向かっているのは、謁見の間に続く廊下だということを確信して、合点した。
とうとう、その『価値』を認める気になったのかと。
(少し、遅いけどね)
謁見の間へ向かう小さな人影を真正面から迎えることが出来た。
少女はセアラと5歩ほどの間を取り立ち止まった。紫色の瞳の強い光が射抜くようにこちらを見つめる。その視線に対して、セアラはあえて微笑んだ。柔らかな、小さな子供に対して向ける微笑を。
「やあ」
少女は軽く目を細めたが、膝を少し折って微かな礼を示した。
「初め……」
「初めてじゃないよ。
会ったね」
セアラはそう明るく声をかけて、表情一つ変えずに挨拶をやめた少女を見る。
「君はお祖母さまから離れようとせずに、目を赤く腫らしていた」
「私も、覚えています。貴方が祖母に送った白い、花を」
言葉を選ぶようにそう言って、少女はもう一度礼をした。よほどセアラとの間の空気を断ち切りたいらしい。そう感じて彼はますます興味深く感じた。
「……王に呼ばれておりますので」
少女は足早にセアラの横を通り抜けようとする。その気配の発する風の心地よさに目を細めながら、セアラは声をかけた。
「ねぇ、君。
どうして、帰ってきたの?」
少女が足を止めて振り返る気配を感じた。背中に感じる鋭い視線。セアラはもったいぶってゆっくりと振り返る。
「どういう意味、でしょう」
奇妙に区切られた言葉の間で、強い瞳の光が揺れた。
とても聡い子だと思った。意味を尋ねながらも、その言葉の含みを正確に捉えることが出来ていた。「吉」も「凶」も。
(本物の闇魔術師《ゼクタ》だ)
「側にいれば、また違う道を選べたんだよ。君の力と命があれば」
セアラはゆっくりと彼女の元へ歩き、その目の前で膝をつく。少女は彼女と視線の高さを同じにしたセアラから、一歩も逃げなかった。真っ直ぐに向けられた紫色の瞳へ、赤い瞳が微笑んだ。
「風《ウィア》との契約じゃ足りない。
変わってしまうよ? 彼」
紫の瞳が凍りついた。
「ミ……」
名前を声に出しかけた小さな唇を制止するように、セアラは指を当てた。少女は瞬時に状況を察し、口を堅く結ぶ。
「ゼアルークのあとでいいから、私の部屋に寄ってくれるかな? とびっきりのお茶と茶菓子を用意しておくから。
甘い焼き菓子は、好きだよね?」
紫の瞳がとても美しい。
彼女よりも。
ノーラジルよりも。
大切なものを守るための強さと、その強さが引き起こす血の色が見える。
「ねぇ、ジェラスメイン=ロード=キャニルス」
|
|
| |
|