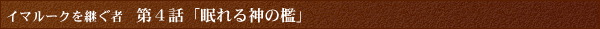 |
| |
|
|
| |
|
◇
彼女の目的地は、町から離れた小高い丘の向こうにあった。宿を出発してからエノリアの口数は徐々に少なくなっていっていた。
どこか思い込むように沈んでいく空気を、ランは余計な言葉をかけてかき回すことはしなかった。
穏やかで静かな町のわずかな喧騒さえ、避けるように建てられた一軒の家。日の光さえも拒むような暗闇を宿した建物を前に、ランは寂しさを覚えていた。人の気の残滓もない。
「私の住んでた家よ」
ランが問いかけるよりも先に、エノリアはそう言って、馬から降りた。エノリアの馬と自分の愛馬を並べ、労をねぎらうようにその鬣を交互に撫ぜるランの脇を通って、エノリアはよどみない足取りで家へ向かっていく。
おとなしいエノリアの馬・システィラがエノリアに向かって、小さくいなないたのが珍しく、ランはその後姿を見つめた。
エノリアの草や枯れた葉を踏む足音に、鳥の鳴き声が重なった。
ランはふと山へ続く森に視線をやった。
そこはターラ山に続く森であろう。何か違うものを感じた。上手くはいえないが違和感というものだろう。そして、その意味を知る。
この山には、生き物がいる気配がするのだ。
いや、それはきっと本来なら当たり前のものだ。魔物の気配が濃くなってきた昨今では、人里離れた山は魔物の領域となってしまっている。だから、そこへ住む生き物も気配を潜めていることが多い。
ターラ山。《ターラ》という言葉の意味を、ランは思い出していた。
システィラをもう一度さすってから、ランは廃墟となった家へ向かった。エノリアは扉の前で立ち尽くしていたが、ランが近づくと振り返りもせずに言う。
「どうなっているのか見たかったの。でも、ひどいわね」
感傷を和らげるかのように苦笑を織り交ぜた言葉に、ランは返す言葉を持たず、ただ彼女の後ろに居た。
扉には施錠さえされていなかった。エノリアが扉をゆっくりと押し開けば、軋む音と共に屋内に日が差す。
エノリアに続いて、中へ入った。
汚れた窓から入るわずかな光が、残された家具の輪郭をなぞる。窓を全て開け放ち、埃を掻き出してしまえばなんとか住めそうだと思っている間に、エノリアは奥へ足を進めていた。建物の突き当たりの扉を開く音が、ランにも届いた。
手についた埃を払いながら、小さな部屋の前で立ち尽くしている彼女の横へ立つ。それ以上足を進めないエノリアを不思議に思いつつ、中を覗き込んだ。
向かって左の壁と突き当たりの壁に設けられた窓には板が無造作に打ち付けてある。他の部屋とは違い、光一つ漏れ入らない部屋。埃が一層積もっているように思われて、ランは少し咳払いをした。
温度が低い。
「ここはちゃんと窓を封鎖して行ったんだな」
「……私が住んでいるときから、こんな感じだったわ。この部屋は」
暗い声にランはエノリアを覗き込もうとした。それを制するように、エノリアは一歩踏み出す。
「少し、1人になっていい?」
「……ああ」
ランは踵を返した。心配になって振り返った彼女の姿は、闇に溶け込んでいった。声をかけようとしたが、やめた。『1人になっていい?』と言った彼女の声色が、ランを押しとどめた。
泣いているように、聞こえたのだ。
それを知られたくないだろうことも、痛いほど感じてもいた。
ランはその家を出て、入り口近くに腰を下ろした。頬杖をつき、背の高い草が生える丘を見つめた。白い小さな花が揺れている。
その向こうでシスティラの目が見えた。様子を伺うようにこちらを見ているそれに対して、ラルディは目の前の草を食むのに必死だ。
それを見てこみ上げる微笑をかみ殺した。ふと、ランはエノリアの後姿を思い起こしていた。
頑丈に閉じられた部屋の窓の重苦しさ。あれでは、日の光など入らないだろう。
エノリアの話を思い出す。自分が二人目のリスタル《太陽の娘》であることを隠して、山奥に暮らしていたと言っていた。
(隠すために)
(誰にも会わないように)
ランは弾かれたように立ち上がる。エノリアを1人にしてはいけないような気がした。あの部屋に、彼女を1人きりにしてはいけない。
再び家へ入ろうとしたランの目の前を、影が横切った。
いきなりだったので、思わず後ずさりした彼の目が捕らえたのは、エノリアの後姿だった。
「エノリア?」
エノリアは丘を駆け下りていった。唖然としてそれを見ていたランの視界から、彼女の姿が忽然と消えた。
焦ってランは駆け出す。
「エノリア!」
呼ぶ。声がしない。
慌てて転びそうになる自分の身体を支えながら、ランは声を張り上げた。
「エノリア!」
転んだのだろうか。ひどい怪我をしたのだろうか。
動けない、のだろうか。
「返事ぐらいしろ!!」
そう言って返事を待つ。聞こえるのは自分の呼吸と、草が擦れあう音だけ。
風が音を立てて渡った。
山に鳥の鳴き声が響いた。高く長く……そして消える。
訳の分からない恐怖が、鼓動を早めた。
「エノリア!!」
ありったけの声だった。そんな風に人の名前を呼んだ覚えがない。
そのとき、草の間から手が出た。緊迫感とかけ離れた空気をまとって、揺れている手を見てランは息をついた。
「いた……」
彼女の元に駆け寄った。荒く息を繰り返すランの思い等お構いなく、エノリアは仰向けになり右腕を空に向けたまま、揺らしていた。そして、ランの姿を認めると、ぱたりと落とす。目を覆うように落ちた右腕と、大地に触れる左腕。
「怪我、したのか」
「してないわ」
草に埋もれて、寝そべっている彼女を見てランはその場に膝をついた。
「返事ぐらい、しろよ……。何かあったのかと思っただろう」
「聞いてたの」
「何を」
軽い苛立ちを込めながら、ランがそう言うと、エノリアは珍しくのんびりとした声で答えを返した。
「ランが私を呼んでいる声」
エノリアの唇が微笑みを作ろうとした。それを見て、ランの心臓が大きく鼓動した。笑顔を見て、どうしてこんなに締め付けられるような思いをしなくてはならないのか。
「……悪くないなぁって。人にそんなに必死に名前を呼んでもらうの、悪くない。探してくれるの、悪くないなぁって」
エノリアは目を覆っていた右手を離した。きらりと光った目を誤魔化すように、身体を起こした。座り込んだまま、地面に視線を落とした。
「聞いてたら、ずっと聞きたくなっちゃって」
微笑みに微かな寂しさを見つけたら、ますます不安が重なった。不安を消し去るように、言葉を吐き出していた。
「探すぐらいする。
探されたくなかったら、……そう言え」
「そう言ったら、探さないでいてくれるの?」
「……多分」
「多分?」
「探す」
「……意味、ないじゃない」
エノリアはそう言って、ランの隣に座りなおした。
膝を抱えて空を見上げてゆらゆら揺れるエノリア。彼女が見ている天をランも見上げてみる。青空とは程遠い、暗い色に変わりつつあった。それがまた不安を引き起こしそうになって、ランはそれを払拭するために言葉を発した。
「どうした?」
「どうしたって」
「何をしに来たかったんだ?」
ゆらゆら揺れていたエノリアの動きが止まった。膝をますます抱えて、エノリアは視線を斜め前に定める。
「私、ここで捕まって、シャイマルークに送られたのよね」
言葉に込められた必要以上の明るさが、胸に痛い。ランはそう言うエノリアを見ながら思った。笑わないで欲しい。
無理して笑わなくてもいいんだ。
「なんでわざわざ」
「ちゃんと、捨てに来たの」
エノリアは唇に笑みを刻んだ。今度はきちんと笑うことが出来た。
「エノリア=ルド=ギルニアの名前を。
ただの、エノリアになりたかったの。ヴィリスタルでも何でもない。ただの、エノリア。
ここでならちゃんと捨てられると思って」
エノリアが視線を町の方へやるのを見つめていた。
背の高い草達が視線を遮ってしまっているけれど、その先にはこの場所を取り残してしまった、穏やかな町がある。
「ただのエノリアになったら、なんだか、すごく寂しくなったんだ。
捨てたいものは捨てられなくて、
捨てたくないものを捨てて。
何なんだろう。
こんな金色……いらないのに」
金色の瞳が潤んでいるように見えた。
捨てたいと言いながらも、捨てられないことは分かっている。
ランは自分の剣の柄に手をやった。ここにある赤い石。
彼女にとってその金色は、自分にとってのこの石なのだろう。
捨てたくても捨てられない。
ただ、自分は「これ」から逃げ続けているだけ。
彼女は自分のものとして金色を認めている。『捨てたい』という言葉は、願いではなくて弱音なのだ。
「そうしたら、ね。
ランが呼んでいたの。
ランが、私の名前を呼んでいて、それ聞いていたらなんか、安心しちゃった。
金色を捨てられない自分。ただの、エノリア。
なのに、ランは呼んでくれてた。
私はいらないと思ったのに。思っていたのに……。
そんなことないんだって、言ってくれているみたいで」
エノリアは微笑んだ。
「変だよね……。嬉しかったんだ」
ユセの言葉が呪いのように頭に響いた。
『その手を絶対に離してはいけません』
『決して、大切な人を離してはいけませんよ』
(離すものか!)
手を離してしまったら、消えてしまうのだ。そう思ったら、彼女を抱き寄せていた。
驚くように息を呑む音が間近で聞こえた。それで我に返っていたが、彼女を放すことが出来なかった。
(怖くなったからだ)
一瞬した言い訳を、ランは握りつぶした。
(違う……。この思いは、そんな言葉じゃない)
「捨てる必要なんて、ない。
お前と会ったとき。お前、追われていて、俺とぶつかったよな。
あのとき、俺……。すごく綺麗だと思ったんだ。
光《リア》が、飛び込んできた。そう思った。
お前は嫌がるかもしれないけど。でも、それをすごく・……。
すごく綺麗だと思ったんだ」
エノリアが少しだけ動いた。金色に戻りかけた髪の感触を頬に感じた。
「俺はときどき考える。お前が自分が二人目の太陽の娘だということに傷つくたびに、考えるんだ。
金色の瞳で、金色の髪。二人目の太陽の娘。だけどそれが、お前でなかったら?
エノリアでなかったら?
お前が『エノリア』という名前にもこだわるなら、それを抜きにして考えてもいい。
『お前』じゃなかったら」
ランは、エノリアをゆっくりと離した。そして、うつむいているエノリアに語りかける。
「俺は多分、途中でその娘を失っている。
守りきれないで……それとも、お前の言う俺の血の都合で」
エノリアが自分の腕の中で身じろぎをした。ゆっくりと顔を上げる気配を感じる。表情を確かめるような視線を受けて、ランは穏やかな顔を彼女へ向けた。
「こういうことも考える。
お前が金色の髪でなくて、金色の瞳でなくて、そして、二人目の太陽の娘でなかったら俺達は出会っていたか?
多分、出会ってなかった。
そうだから、出会った。
お前は、きっと……それが嫌だと言っても。そうでなかったら、出会わなかった。
だから、俺は良かったと思う。お前に出会えてよかったと思う」
真剣なエノリアの瞳の前で、今、語ってしまわなければと思っていた。今なら言える。何故だか分からないが、自分のためにもエノリアのためにも、思っていることを全て伝えたいと強く思った。
「少なくとも、俺には、お前はずっと真っ直ぐ前を向いているように見えた。
いろんなことがあって目をそらしたくなっても、それでも気丈に前を向こうとしていた。
お前の過酷な道……そう、運命から逃げ出すことだって考えられたと思う。だけど、ずっと立ち向かった。
俺は自分の道から逃げてばかりだったのに。
お前は真っ直ぐだった。
だから、どこまで真っ直ぐ行くのか見ていたいと思ったんだ。そんなものを抱えながら、いつまで笑っていられるのか。どこまで進んでいけるのか。
……そのうちに、できれば、いつまでもそうやって笑っていて欲しいと思うようになった。
その手助けがしたいと思った。
たったひと時の安寧を得るために、お前を殺してしまうことが許せなかった」
ランはエノリアに苦笑する。暗い笑みが零れ落ちた。
「ただ、その自分の中の思いは単純に肯定できなくて。
お前のことを守りたいと思っても。
お前がお前でいて欲しいと言っても。
いつも、自分を振り返っては踏み出せないでいる。
ただ、自分のためにそう思い込んでいるんじゃないかって。
自分の中に抱えているものを否定するために、お前を助けたいと思っているんじゃないかって、迷っているんだ」
困ったように自分を見てくる彼女に、ランは首を傾けた。
「俺はシャイマルーク王家の血から逃げたい。
それだけが俺の存在する意味だから。
その意味を強めるためだけに、お前を助けようとしているんじゃないのかって」
エノリアの問うような視線の前で、ランは一息つくと首を傾けた。
「お前、俺がシャイマルーク王家の血を引いてるって知ってるよな。
どれくらいシャイマルーク王家に近いと思ってる?」
「セアラが引き取るぐらいだから」
「だから?」
ランの真剣みを帯びた目を前に、エノリアの言葉は一段と小さく掠れてしまう。
「……でも、生まれて直ぐに……死ん……亡くなってるって」
「それは、誰」
「……弟」
エノリアの悲愴な瞳の光にランは、ふと笑った。エノリアはもう一度繰り返した。
「ゼアルーク王の、弟」
それが近く、そして、ひどく遠い響きだと思った。ランはそう思いながら、頷いた。
「ゼアルークの『ルーク』。それは、『イマルーク』の存在を残すための響きなんだ。
いつか、イマルークがこの世界に戻ってくるための、場所を用意するため」
ランはそう言って空を見上げた。風が黒い髪を揺らす。
「場所?」
「そう。場所」
目を瞑る。
「創造神・イマルークはいつか戻ってくる。その約束が『イマルークの血』」
「ゼアルーク王の額飾り……」
「あの石は、初代国王レーヤルークの物らしい。彼の血が結晶となったものだそうだ」
「血が結晶に?」
「イマルークに近ければ近いほど、空気に触れた最初の血が、石のように固まる。
そうやって、イマルークは目印を遺した。自分がいつかこの世界へ戻ってくるために。
だから王家に生まれた男の子供は、母の手から父の手へ渡される前に一つの儀式を受ける。
ここに、傷をつけるんだ」
エノリアへ視線を戻して、ランは自分の額を指し示した。
「現国王……ゼアルークの血は完全に固まらなかった。だけど、レーヤルーク以後初めて、それに近いものが生まれたという核心を周りの者に植えつけるには十分な結果が出たらしい。
次の子供はセアラに『男であれば、世界を滅ぼす』なんて大層な予言を受けてのに、すぐに殺されなかった。
次の子供はより『イマルークに近い者』ではないかという希望が勝った」
「世界を滅ぼす?」
エノリアがそう聞くと、ランは苦笑した。
「らしい。
仰々しいよな。
まぁ、ともかく、次の子供はその儀式だけはと受けさせられた。
予想通り、血は直ぐに固まった。まるで、ここに宝石がはまったように」
ランは目を細める。
ゆっくりと額を指し示した指を下ろして、自分の剣にはめられた赤い石に触れた。
「そう。俺は、ゼアルーク王の弟で。
……イマルークの『器』だそうだ」
遠く、なる。
語る自分の声が、遠くなっていく。
まるで、他人事のようだ。
「イマルークが戻るための『器』。
本当は意志を持たない『器』なんだ。
その証拠に、俺は生まれたとき泣きもしなかったらしい。
その傷をつけられたときも」
不意にランは我に返った。
エノリアがランの二の腕を握り締めていた。
こちらを見上げる悲愴な瞳。
その金色の光を見て、ランは自分が自分である感覚を取り戻した。
「俺にとっては、自分の血に抗うことだけが、俺が『俺』である証拠だった。
だから怖い。この思いは作られたものじゃないかって。
お前のことを助けたいって思っていても。
それは偽りなんじゃないかって。
お前のことをどんな風に思っても。
守りたいと思っても。
大切だと思っても。
それは、俺がイマルークの『器』だからじゃないのか」
「そんなことないっ!」
エノリアは声を張り上げる。
「貴方が言ったのよ。
光《リア》は巡ってくる。
なのに、それはお前じゃない。
お前がお前でなくなるのは嫌だって!
私、それに支えられている。 貴方の言葉よ。ちゃんと届いたもの!」
エノリアの金色の瞳から涙が溢れてきた。それを、ランは見つめていた。溢れた涙が、粒になって零れ落ちるのを見ていた。
「私、真っ直ぐなんか向いてない。
真っ直ぐ向いて、歩いているように見えてるなら、それはランのおかげなの!
何度もやめようと思ったわ。
あのときだって、本当に死にたいと……」
震えだす彼女をランは支えるように抱きしめた。
「悪い……」
「謝らないで。
だけど、その度に貴方がいたから。
だから、まだ生きているのよ」
その両頬を捉えて、エノリアはランの顔を自分に向けさせた。
しがみつくようなエノリアの指の感触。細く冷たい指先で、必死にこちらを向かせようとしている感触を、ランは心地よいと思った。
「私は好き。
貴方がそうやって自分の中のものと必死で戦って、真実を見定めようとする必死さが好きよ。
私を守ろうとする思いさえ、偽りなんじゃないかって迷うところも貴方よ。
私のことをちゃんと考えてくれているってことじゃないの。本当の部分で、私を見てくれてる証拠じゃないの?」
「エノリア」
「言ってよ。言葉にしてよ。
なんでもいい。私を見て、ちゃんと言って」
必死な瞳。きらめく金色の光。
美しいと思った。
強い光。生命の光。まさしく、そうだと……思って見つめていた。
「そうしてくれたら、私はその言葉を『真実』だと思うわ。
貴方が『偽り』だと恐れても、私はそれを『真実』だと言ってあげるから!」
ランは緑色の瞳を細めた。
「強引だ」
「だから何よ!」
怒りに任せて声を張り上げたエノリアが、言葉を詰まらせた。
そっと唇が触れ合った。本当に微かに。
一瞬だった。唇から暖かさが消えて、驚いているような金色の瞳を間近に見た。驚いているのは自分もそうだった。
お互いの真意を探るような視線のぶつかり合い。やめたのはエノリアの方だった。微かな笑みを唇に浮かべる。
「嘘?」
ランはすぐに首を振った。
「違う」
強く抱きしめた。
「……違う!」
エノリアの顔を見る。ぎこちなく微笑む彼女がとても愛しくて。
好きだとか、愛だとか、恋だとか。そういう『言葉』を知っている。だけど、どの言葉を使ったらいいのか、わからなかった。
「俺は……」
だから言葉がうまく出てこなくて、それでも彼女に伝えたくて。
その思いが自分を突き動かした。
ありったけの誓いを胸の中に掲げて、もう一度口付ける。
指と指、唇と唇。
触れている暖かさだけが、真実。
そこにあるのは、この言葉だ……。
囁きに願いを込めた。
この言葉以上の思いが、彼女に伝わるように。
そして、それがいつまでも『真実』であることを信じて。
|
|
| |
|