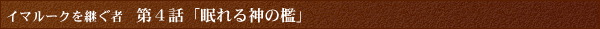 |
| |
|
|
| |
|
フェリシャは、小さな子供ながらにミラールの教えを一生懸命に聴き、ようやく音が出るようになった。
庭先でミラールの笛から音が出たとき、大はしゃぎし、それからは夢中に笛を吹いていた。
ぴー、ぴーと絶え間なく流れる音に目を細め、赤くなる小さな頬をほほえましく見つめていると、ミラールの鼻を清涼な香りがくすぐった。
庭へ続く部屋に、リタがお茶を運んできたのだ。
「少し休憩しませんか?」
ナスカータの高級な茶葉だろう。お茶にというか口にするものすべてにうるさかったセアラが、二番目に好んだお茶である。
それをここまで薫り高く入れる技に、ミラールは感心した。
「フェリシャ」
そう声をかけると、フェリシャは大きく首を振った。まだまだ拭いていたいのだろう。
「あと、すこしだけだよ」
そういうとこちらも見ずに、うんうんと頷く。
ミラールは席につく。それを見計らって、リタが茶を茶器に注いでくれた。
「かわいいお子さんですね」
そういうとリタは、微笑んだ。
「隣の家のお嬢さんです。
ときおりお預かりしてたのですけど、最近は毎日のように遊びに来てくれるんです。
私がさびしい思いをするといけないから、一緒にいてあげるんだって……。優しい子でしょう?」
心なしか寂しげな微笑と雰囲気に、ミラールは暖かな笑みを返した。
「宿の主人に聞きました。子供を預かってくれる方がいらっしゃるって。
リタさんだったんですね」
リタはそのミラールの微妙な変化に気づいたのか、気持ちを切り替えるように目を伏せる。
「ええ。
ここの町の人たちはとても優しくて。たった一人で暮らす私のために、様々な心づくしをしてくださいます。
せめてもの恩返しにと思って始めたことです」
「今日、お菓子を子供達に配っておられたのでは?」
「見ておられたの?」
リタはそう言って、苦笑した。
「子供がとてもとても可愛くて。
喜ぶ顔が見たくて」
満面の笑みを浮かべて、走っていた少年達の姿を思い出す。思わず笑みが深まるミラールに、リタはにっこりと微笑んだ。
「焼直せばまだ少しあるわ。そうそう。そうね。
ちょっと待っていてくださる?」
ミラールはあわてて顔を上げた。
「あ、いえ。お気遣いなく」
「私が食べていただきたいの。笛のお礼はそれぐらいしか出来ないから」
中腰になったミラールに『座っていらしてね』と言ってリタは再び屋敷の奥へ向かっていった。
それを見送ってから、ミラールは腰を落ち着ける。目の前を揺れる湯気に気づいて、茶器を手に取った。懐かしい香りを吸い込む。
(……セアラ)
『火傷をしないように気をつけて。そう、ちゃんと時間は正確に測るんだよ』
本当においしいお茶を入れられるようになるまで、セアラは側で何度も同じことを教えてくれた。
どんなお茶でも、セアラは『おいしい』と言う。だけど、それは嘘だと分かったから、心の底からの声が聞きたくて何度も何度も繰り返した。
僕がお茶を入れる姿を見ているときのセアラの目は、とても優しかった。
その目を見たくて、僕は何度も繰り返していたのかもしれない。
「お兄さん」
ミラールは我に返った。目の前にこちらを見上げるフェリシャの姿。
「どうしたの。休憩するかい?」
「これ、ありがとう」
笛を差し出すフェリシャ。その笛を受け取りながら、ミラールは首をかしげた。
「もういいの?」
「この笛は吹けるようになったの。だから、あの笛を吹いてみようと思って」
「あの笛?」
「うん。リタが持ってる笛よ。
リタ、その笛はふけないっていうの。
音が出ないって。
だけど、そういうたびにリタはすごく悲しそうな顔をするから。だから、私が吹けたらきっと喜んでくれると思って」
笛。そういえば『この笛』と言っていたなと思った。
「そうか。フェリシャは優しいんだね」
「ううん。優しくないよ。
だって、いつもお母さんを怒らせてばかりだもの。
リタは優しいの。リタは怒ったりしないの。
でも、でも……ちょっと悲しそうなの。
私、知らない振りしてるけど、ときどきリタ……悲しそうにしてるのね。でも、多分、知られたくないんだと思うんだ。
私も、お母さんに怒られて悲しいとき、お父さんには知られたくないの。お父さんも悲しそうな顔するから。
そういうことだと思うのね」
そう言ってから、フェリシャはにっこりと笑った。
「とってくるから、フェリシャの分のお茶、お砂糖入れて冷ましておいてね」
「わかったよ」
ミラールは自分の手の中にある笛に視線を落とした。
しばらくして帰ってきたのはリタのほうだった。甘い香りを引き連れて、ミラールの目の前に小さな焼き菓子が沢山入った籠を置く。
「いい香りですね」
リタはその言葉に返事をしなかった。不審に思ったミラールが顔を上げると、リタはミラールが卓上に置いた笛を見つめていた。
「リタ、さん?」
「あ、いいえ。とても素敵な模様ですね」
「何に見えますか?」
「そうね……。蔓……と、花かしら? 小さな、花」
リタはそれをじっと見つめていた。そのまま、ミラールへ視線を移した。
「そういえば、今更ですけど……お名前を最後まで伺っていませんでしたわ」
「そうですね。すみません、なんて礼のないことを。
ミラール=ユウ=シスランといいます」
リタは目を細めた。
「ユウ=シスラン……」
「リタさんは……。お名前は『リタ』というのですか?」
リタが視線を上げる。聞き返す視線に、ミラールは頭を振った。
「愛称かと思ったので」
「いいえ」
にこりと笑ってリタはミラールに真っ直ぐ向き直った。
「リタ=ノイ=シュスウと言います」
ミラールが改めて軽く頭を下げると、リタは少し首をかしげた。
「ミラールというお名前は素敵ね。柔らかな音だわ」
「《優美》という意味があるのだと、育ての親は教えてくれました」
「育ての親」
「ええ。僕は、両親を知らないから」
ミラールはそう言ってリタを見る。
「この笛は、僕の両親への手がかりなんです」
リタは静かに。ただ、静かにミラールの言葉を聞いていた。葉の落ちる音さえ聞こえるような静けさのなか、リタはようやく言葉を発する。
「辛いことをお聞きしたかしら……」
「辛くはないです。本当のことですから。
それに、多くの人が僕の境遇を知ると、『寂しかったでしょうかわいそうに』とおっしゃってくれましたが、寂しくはなかったので」
リタの視線を痛いほど感じていた。その視線に負けるように、ミラールの言葉は掠れ、視線は落ちていく。
何かを言わねばと思い、ミラールは顔を上げる。
そして息を呑んだ。
目の前の女性は、泣いていた。
何故泣いているのか。自分のことに同情して泣いているのか。
今まで多くの人が、自分の境遇を知って「寂しかったでしょう」と悲しい顔をした。そのたびに、その悲しそうな顔に腹を立てていたことがある。最近は、そういうものなのだと割り切れるようになった。
本当の両親を知らないことは、悲しくて寂しいこと。それが、世間の常識なんだと。
だけど目の前の女性が泣いているのは、とても辛かった。不思議と冷めた思いはやってこなかった。
そして、泣かない自分が不思議だった。
『寂しかったでしょう?』
何度もかけられた言葉。その度に『寂しくなんかありませんでしたよ』と返した。
だけど、今彼女にそう問われたら。
唇がわななく。堪えるように噛み締めて、卓上の笛に手を重ねた。
お茶から立ち上る湯気が柔らかく揺れる。その向こうで、リタはただ涙を流し続けていた。
◇
本当に穏やかな町だと思った。
ユセは念のために保存の効く食料を買い求め、馬の手綱を手にゆっくりと歩いていた。
歩みを速め、この空気を乱すことが罪のようにも思えた。
人の視線は温かい。
旅人を優しく迎え入れ、優しく送り出す。
そんな空気のある町だと思った。
全てが終わったら……と思う。
(アリアとトーヴァをここへ)
ひっそりと住んできた山奥から、この町へ住居を移そう。誰もを優しく迎え入れてくれそうなこの町なら、きっと彼女も彼も静かに暮らせるはず。
触れる風がユセを優しく撫でていく。彼の思いを反映するような風だった。
だが空気が急速に固まった。冷たさと重さを持って、ユセに激しく警告する。視線だ。方向の定まらない憎しみの一片が、ユセに向けられていた。
顔を上げた。驚きは表には出さない。
よく知った顔。
『殺したりなんかしない』
迷いを消して、挑むように言い切った言葉。強い視線の奥にある意志と優しさに、希望を感じた。
だが、目の前の男からはその欠片さえ見つからない。
意志の強さはある。だが、その強さは危険だった。
ゆがんだ唇から生まれる邪悪な笑み。指先が微かに動いた瞬間、ユセは顔を少しだけ傾けた。
頬を掠る風。微かな痛み。
風はユセに触れた瞬間に、四散した。
「カイネ」
男はそう呟いた。男との間には10歩分の距離がある。だが、その言葉は届いた。気づけば回りの喧騒がやんでいた。
人々は動いている。なのに、音が届かない。
「ザクー」
言葉に力を込めた。ザクーは少し痛みを感じたかのように顔をしかめ、振り払う。
「ザクーという名前はあまり強くないな。
名づけた者が死んだから、かな」
ザクーはそう言って、ユセに問うように首を傾げた。ユセはゆっくりとその言葉の意味を反芻する。
ザクー。
月の娘《イアル》から生まれた魔物。
そこから紡ぎだされる一つの仮説に、ユセは頭を弾かれる。
「まさか。月の娘《イアル》が」
「解き放たれた」
感情を一切振り払った言葉が、やけに痛々しい。ユセは目を細めた。
「カイネ」
ザクーはもう一度その名を呼んだ。
「お前が守ろうとしているものは、もうすぐに無くなる。
それでも、あいつらをあそこへ導くのか」
ユセは頷いた。
「必要なことです」
「介入しすぎだぜ」
「わかっていますよ」
ユセは微笑んだ。
ザクーは、首を傾ける。
「太陽の娘《リスタル》・月の娘《イアル》・大地の娘《アラル》。全てを欠いたシャイマルークに、何の意味があるんだ?」
「大地の娘《アラル》も……」
「もう、『奴』に留めさせる意志はない」
「『彼』がいます」
「『俺』がいる」
ザクーの眼の中にある強さに、ランの光と似たものが浮かんで消えた。
「俺なら、壊す」
「貴方には無理です。貴方は『彼』ではない」
「なれるさ。あんたが俺をそう呼べばいい。一度でいい。それで、少しでも近づけるだろ」
「それで私の前に姿を現したのですね」
「そう。わざわざ、結界の張られた街中にな」
ザクーは含みを持たせた邪悪な笑みを見せ付ける。その表情はランとはまったく違う存在だと改めて思わせるものだ。
「……脅迫ですか」
「察しが早いね。
大切な『奥さん』と『お子さん』のため。
あんな山奥にご大層に隠している大切な家族のため。
簡単だろう?
呼べばいいんだよ。俺をあいつの名前で」
ユセは拳を握り締めた。
「苦労した。あんたの足取りを辿るのは」
「名を与えても、貴方は『彼』にはなれない」
「じゃあいいだろう?」
ザクーは、彼に一歩だけ近づいた。一歩だけ、その近さがユセには辛い。
「渋るのは、可能性があるからだ」
「名に……重みがあるからですよ」
「大切な家族以上の?」
ユセが耐え切れずに一歩、下がる。彼がまた一歩踏み出す。
「あんたは何のために、一線越えて介入してるんだ?」
歪む笑みに、重苦しさがあることをユセは知った。
「家族のためだろう? タイセツなヒトの」
目の前に影が下りて、ユセは顔を上げた。ザクーが見下ろしている。黒い瞳。黒い髪。
ランではない。
だが、根にあるものは彼と同じだと感じた。ランはそれを隠し、ザクーはそれを隠さない。
注がれた愛情が真実だったか、偽りだったか。
それが優しさとなるか、憎しみとなるか。
その違いなのだろう。
ユセは彼の耳元に唇を寄せた。名を囁く。ザクーが頷いた。
それで終わりだ。
満足そうに笑みを浮かべるザクーから顔をそらせて、ユセは問う。
「貴方は何のためにそこまでするのですか。
彼女の望みを叶えられずに彼女を失ったなら、貴方は自由なんですよ」
長い沈黙が降りてくる。ユセはその間に視線をザクーへ戻した。ザクーはユセを静かな目で見つめていた。
答えるつもりはないだろう。ユセがそう判断したとき、彼は唇を開いた。
「気づいたんだ」
ザクーは視線を落とす。
「そんなものには意味がない。
意味がないものはつまらない。
意味があるのは、彼女の望みを叶える事だと」
「彼女?」
ユセのいつも優しさを讃えている瞳が、鋭くなった。
彼女。その言葉を指す方向が、ユセにはあやふやに感じられた。
「それは、シャイナ? それとも……ナーゼリア?」
ザクーは問われた意味が分からないようだった。一瞬、不思議そうに眉を寄せた。
「シャイナ、だ」
「間違えてはいけない」
ユセは自分に警告した。それは『見る者』の言うべき事ではない。だが、あえて踏み込んだ。
「本当の彼女の願いを」
ザクーはその言葉の意味を一瞬だけ考えたようだった。だが、すぐに視線をそらしてユセに背を向ける。
その姿が溶け込むように消えたとき、ユセの周りに喧騒が戻ってきた。
ザクーの消えた場所をしばらく見つめてから、ユセは再び歩き出す。先ほどまでのことがなかったような顔をしていたが、手に食い込むほど強く握り締めてた手綱が微かに震えていた。
|
|
| |
|