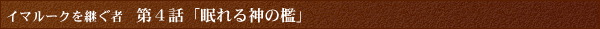 |
| |
| VI 神の麓
|
| |
|
銀色の細い糸に月の光が添う。それを見つめていた。
光の色に含まれる静けさを、ただ見つめていた。
「……ザクー……」
銀色の光から視線を薄紅色の唇へ移し、黒い瞳を細めた。
それは、自分の名前である。だが、彼女の呼ぶ先に、彼女の見つめる先に、自分はいない。
「シャイナ」
何かを求めるように伸ばされた手を握り締める。
苦しそうに閉じられた瞼に口付ける。
闇夜にも溶け込むことのない銀色の髪を梳き、頬をそっと撫でた。
「シャイナ。ここに」
「……ザクー……」
何度も繰り返される言葉。
貴方にあの男の本当の名を教えたら、彼の名を呼ぶようになるのだろう。
私の持たない緑色の瞳を思い出した。
(そうして、私は名前を失うのだ)
「シャイナ=フィン=シャイアル」
たった一人の月の娘《イアル》。その名に縛られた、可哀想な娘。そして、何よりも憎い存在。何よりも、愛しい存在。
「彼女が名前を捨てたよ」
囁く。うっすらと開き、漏れる銀色の瞳に自分の姿が映るのを見つめていた。
「エノ、リア……」
「そう」
「ヴィリスタル?」
それに、首を振って否定する。少し安堵するように息をつき、再び銀色の瞳は閉じられた。
「ザクー……」
「何?」
「……側に、いてね」
男は再び目を細めた。まぶしいものを見るかのように、そしてしばらくの時間をおいて、そっと囁く。
「勿論、ずっと」
白く柔らかな手を握り締める。そこから伝わってくる冷たさが暖かさに変わるように願いながら、口付けた。
優しく。
◇
その町は今まで通り過ぎた町となんら変わらない風景を持っていた。ただ、その町を囲むように控えた山が、圧倒的な存在感を持っていた。深い青色の稜線。そして、少しだけ冷たい風。
ドゥアーラ。そこは大きな街道から外れた山際の小さな町である。その美しい山の風景、そして、空と山の美しさを染め上げたような織物が特産の小さな町だ。
また風が通り過ぎた。その風にさらわれて、ひらめく肩掛けをかき寄せながら目の前の彼女も少し震えたようだった。
揺れた髪の色は、明るい茶色。
光にかざせば、それは金色に近い色となる。
その状況に危機感を感じているのは、自分だけだろうか?
光《リア》を感じ取れる得意な体質だから、分かるだけだろうか?
ミラールはそっとため息をついた。
「静かだな」
ぽつりと感想を漏らすランに、ミラールは目を向ける。
「穏やかな町ですね」
ランの言葉に答えるようにそう言ったのはユセだった。
人はまばらな上に、ゆったりと動いていた。それが、穏やかさと静けさを、他の街の賑わいを知る者に与えるのかもしれない。
ここはミラールも訪れたいと願った町だった。ここに自分の両親についての手がかりをもつ人物がいるかもしれない。
それは今まで得られた情報の中で、一番確信を持ち、自分を喜ばせ気持ちを昂ぶらせるもののはずだった。
だが、これほど静かで冷たい思いのままでいられるのは、この町がそれぐらい穏やかな空気を持っているからだろうか? それともこの冷たい風のせいだろうか?
ミラールはそう思いながら、周りへ目を向ける。
この町も中心部に大きな広場のある作りになっているようだった。オオガもメロサもそうだった。真ん中の広場を中心に、放射状に広がる道。だがその形は細長く、山と反対方向に延びている。また、広場の中心は噴水ではなく、花壇のようだった。
その広場の人だかりが目の端に入った。
人が少ないと思ったのは、あの人だかりのせいだろうか?
だが、よく見ればそれは小さな子供の集まりだということに気づく。
「祭でも、あるのかな?」
何気なく呟いた言葉に反応して、同じ方向を確認し言葉を返してきたのはエノリアだ。
「でも、終わったんでしょ? 誕生祭は」
「そうですね。終わったはずですよ」
ユセも呟いた。
子供ばかりの人だかりの中心には、髪の長い女性が立っている。その女性が子供に手を伸ばすたびに、歓声が起こっているようだった。
ミラールはその黒い服を着た女性の後姿を見つめていた。どうして気になるのか分からないまま見ていると、ランの声がその意識を遮った。
「宿、あそこでいいか」
誰も反対などしない。宿らしき建物は少なく、その中でも一番大きな建物だったのだ。旅人を笑顔で迎える亭主に祭のことを聞く。
「誕生祭は昨日終わりましたよ」
にこにこと笑いながら、そう答える亭主にエノリアは続けた。
「なんだか、広場に沢山人が集まっていたからまだ続いてるのかなと思って」
亭主は、ああと言って一層笑みを深めた。
「子供達ばかりじゃなかったですか?」
「そうね。そういえば」
「この先に住んでいるご婦人が、時折お菓子を作って配ってくれているんですよ。それで子供達が集まるのです」
相槌を打つエノリアに、亭主は聞きもしないのに続けた。
「忙しい親に代わって、子供を預かってくれるご婦人ですよ。
この私も昔は大変お世話になりまして」
「ご婦人?」
その呼び方に引っかかるものを感じたのか、エノリアがそう聞き返すと、亭主は再び、ああと笑った。
「そうなんです。
ここらの生まれの方じゃない、ちょっと高貴な雰囲気を持ってらして、私らずーっとそう呼んでます。
お部屋はこちらとこちらです」
そう言いながら通された二階の部屋。エノリアの1人部屋とラン・ユセ・ミラールの3人用の部屋だった。
ミラールは部屋の隅に荷物を固めると、窓を開け放つ。冷たい風が吸い込まれるように入ってきた。
歓声を上げながら、子供達が走っていく。それぞれの手に、小さな袋を持っていた。
見ていると思わず口元が笑ってしまう。子供達を迎える親達も、微笑んでいた。お菓子を貰い損ねたと気づいた子供達が、再び広場へ向かって走っていく。
走り出すのが遅れた子供を急かしながら、先頭を走っていく少年に視線を向けた。時折振り返りながら、追いつくのを待っている。
ミラールはその少年が、道の向こうに消えてしまうまで見つめていた。
「ミラールさん」
声をかけられて弾かれたように、ミラールは視線を戻した。
ユセが近くに立っていた。
「私達は明日の準備を整えるために街に出ますが、ミラールさんはどうします?」
ランはユセの後方で出掛ける準備を済ませているようだ。
「僕は……」
返答を遮るように、扉が二度叩かれる。
「どうぞ」
ユセの言葉に扉を少しだけ開けて、覗き込んできたのはエノリアだった。
「あの……ターラ山に行くのは明日よね?」
日は傾きかけている。山へ入ってしまえば、完全に日が落ちるだろう。
「そうしたほうがいいだろうな」
ランがそう答えると、エノリアがちょっと遠慮がちに笑った。
「あの、私、ちょっと行きたいところがあるのよ。
……付き合ってもらえないかなぁと思って」
ちらりとエノリアはランを見て、そして、ユセとミラールを見た。
「これから街に」
ランの言葉を、ユセが遮った。
「そう遠くに行かれるわけではないのですね?」
エノリアはこくこくと頷いた。
「馬ならすぐよ。でも、ちょっと町の外れなの。それに……」
「私は用がありますので無理ですが、ランさんとミラールさんが行ってくだされば」
「僕は少し休みたいな……」
ミラールは寝台に腰掛けながらそう言った。ランがそれを見て、何かを言いかけたのを遮るように、ミラールは続ける。
「ちょっと疲れて」
「大丈夫か?」
「そうよね。疲れてるよね」
同時に心配そうな顔をする二人に、微笑みながら首を振る。
「こっちこそごめん。大丈夫。そんなに遠くないなら、二人で行っておいでよ」
そうして、心配そうな表情をしているランに苦笑する。
「本当に平気だから」
「だけど」
「エノリア。早くランを連れて行ってよ。こんな心配性が側にいたら、休むに休めないよ」
「私も心配だわ」
倒れた一件が後を引いている。それはもう大丈夫なのだけど、と思いかけた瞬間、あのときのことを思い出した。
ザクーから、受け取ったあれのせいなら。
ミラールは深刻になりそうな気持ちを抑えて、二人に肩をすくめてみせる。
「うーん。じゃあ、僕、薬師か医者を探してそこに行くから。その間、行っておいで。もう明日にはターラ山行くんだから、僕もそのほうがいいし、僕を待ってたら、エノリアの用が済まないでしょ」
「付き添いとか」
「あのねぇ。何歳だと思ってるのさ。
本当に大丈夫だから。あんまそんな深刻な顔しないでよ。
ちょっと休めば明日には元気になるんだからさ」
「そうか?」
「そう!」
ミラールが強い調子でそう言って、困ったような顔を今度はエノリアに向けた。
エノリアは、それにどう答えていいか分からない様子を見せていたが、ミラールが頼むように頷くと、ランの腕を引っ張る。
「じゃあ、ランだけで我慢するわ」
「そうしてよ。ごめんね」
「すぐ、帰ってくるからね」
「こっちは心配ないから、早く行きなって」
「本当に医者、探すんだな!?」
「しつこいって、ラン」
引きずられるようにしてランが出て行き、扉が閉まる音を聞いて、ミラールは思わずため息をついていたのかもしれない。ユセの視線を感じた。
何かを言いたそうなユセの視線に、ミラールは完璧な微笑を返す。
「疲れているというのは、本当ですよ」
ユセはそれに微笑を返した。
「それでは、私も出掛けてきますね」
ミラールは自分の言葉の余計さに十分気づいていた。だが、それに何も返さなかったユセの言葉によって、その余計さを強く感じる。
苦い。
ミラールはそう感じて、1人残された部屋の窓から、再び外を見つめた。
ランとエノリアの後姿と、ユセの後姿。
ほんの一瞬だけやった視線を、すぐに空へ向けた。
「……言わなくてもいいこと、だった」
そう言ってから、ミラールは直ぐに部屋を後にした。
小さな町だ。誰かに聞けばすぐにわかるだろう。
さきほど人だかりが出来ていた中心部へ足を運ぶ。
数人が真ん中に作られた花壇の淵に、腰をかけているだけだった。ミラールもひとまずそこへ腰掛ける。
「ミレリータか」
座ってしまうと、足は動かなくなった。誰かを呼び止めて聞く気力もない。
肌身離さず持っている笛を取り出した。その模様を目で追う。
いつも持っていたこの笛を、意識したのはいつごろだっただろうか?
大切なものだから大切にしなさいとセアラに言われ、その通りにしてきた。
ランが大怪我をしたあの夜、この模様をじっと見つめて過ごした。
あのとき初めてこの笛を吹いたんだと思う。
その音だけが、暖かかった。
優しくさすってから、唇にあてた。
息を吹き込んだ。柔らかな音が空気に溶け込んだ。
同じ音を長く吹いて、そして、ミラールは目を瞑る。
長く一つの音を吹いていたが、それはまるで風を辿るように『歌』になっていく。
いつもこの音が側にあった。
寂しいときも、この音が側にあった。
『きっと、ミラールのお父さんかお母さんが置いていってくれたものだよ』
セアラがそう言ったとき、やっぱり自分はこの人の子供ではなかったのだという寂しさが先にあった。
セアラはまずランを見た。そして、次に僕を見た。
そう確信したのはランが居なくなってからだ。けど、それはきっと、小さな頃からどこかで感じ取っていたんだと思う。
それでもよかった。
ランの後でもよかった。
二人ならば。
あの館でセアラとランと僕で、ずっと過ごしていくならば。
もしくは、出会ったのがエノリアでなかったら……。
『これは、君の両親への鍵』
両親。お父さんとお母さん。
(会いたいのか)
会ってどうするのだろうか。
今更、親に会って。そして、そこから先は?
(僕は、あの『約束』から逃げたいんだ)
ランと交わしたあの『約束』。
両親を見つけて、そうしたら離れられる。
曲はゆっくりと収束していった。
(逃げたいのは……ランからだ)
ランとエノリア。二人から。
離れることは簡単だ。
だけど、それでも離れられないんだ。
側に居たいんだ。
側にいればいるほど、苦しいのに。だけど、離れたくないんだ。
ただ、欲しいのはきっかけ。自分では造ることの出来ない、きっかけ。
二人から離れて、カーラたちと共に行くための。
ミラールは、笛を膝に置いて、再び息をついた。
どうしたいんだろう。
僕は、ランとエノリアに何を望んでいるんだろう?
『好きなのね、あの子が』
そうだよ、カーラ。
だから、辛いんだ。
ランの優しさもエノリアの優しさも、触れるだけで痛い。
僕は少しも優しくなんかないのに。
『好き』だという思いは、このままで終わったりしない。
欲しくなればなるほど、傷つけて壊して、動けなくしてでも、手に入れたくなる。
ミラールは再び、笛を唇に当てる。
ただ優しい曲を選んだ。大切な人を思うような優しい曲を選んだ。
音楽を奏でているときだけ、本当に自分が優しくなれる気がする。
風を撫でて、そして、この空間が優しい響きで満たされるといい。
その先に思いを馳せながら、ミラールは心の中で頷いた。
(離れよう)
この町を出たら、カーラたちと一緒に行こう。
ランの強さがあれば、僕は一緒に行く必要はない。
そうしよう。そうすれば、誰も傷つかなくて済む。
そう思いながらも、どこかで何か渦巻くものがある。それを溶けてしまうことを願いながら、より一層優しい旋律を求めて笛を吹き続けた。
|
|
| |
|