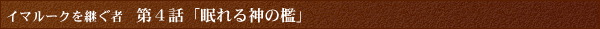 |
| |
|
|
| |
|
自分の部屋までどう帰ってきたのか、よく覚えていない。
でも、そこは自分の部屋だということはわかった。そこに人影があった。優しい青紫色の瞳が間近で光って、ジェラスメインは身体を強張らせた。
「ラシ……」
その瞳は悲しそうに伏せられた。甘い香りがして、それがラシータでないことを知る。
そう、彼はいない。
あまりにもラシータに似ていて、ラシータがよみがえったのかと思った。
自分が、選択を誤ったのかと思った。
「母、上」
「ジェラスメイン」
「ごめんなさい……」
ジェラスメインは思わず謝った。急に音が遮断された。雑音がなくなる。高い耳鳴りが空気を支配した。胸がつぶれる。つぶされる!
私を見つめる青紫の瞳。ラシータが受け継いだ青紫の瞳。そして、たった今、断ち切ってしまった瞳の色だ。
私は、選択を誤ったのだろうか?
キャニルスを捨てて、兄をよみがえらせた方がよかったのだろうか?
母が笑ってくれるのならば。
そのほうが嬉しかったのではないだろうか?
訝しげにこちらを見る母の目に、悲壮なものを感じてジェラスメインはあわてて取り繕った。
「あの……お休みのところを起こして、ごめんなさい……」
そのとき、急に濃くなった甘い香りと暖かさに驚いて、ジェラスメインは気づいた。母に抱きしめられていることに。
「は……」
「愛しているわ、ジェラスメイン……」
囁くような言葉に、ジェラスメインの目が熱くなった。一気にあふれ出す涙を、どうすることもできなかった。
「放してください……」
「どうして」
「私は、母上のお体に障る!」
叫び声だった。こんな暖かさ、今はつらいだけだ。だが、母はますます強く抱きしめてきた。熱い。人の体温はこんなにも熱い。
「どうして放せると思うの」
「はなして……ください。抱きしめてもらう資格が、ない……」
ジェラスメインは母を押しのけた。
暖かさが離れる。たちまち、冷たい空気がジェラスメインにまとわり着いた。
「ラスメイ?」
「……出来たんだ」
ジェラスメインは頭を振った。
「私には出来たんだよ?!」
叫び声は部屋に響き渡った。荒く呼吸を繰り返し、次の言葉を静かに待つ母の気配に向けて、ジェラスメインは半ば自暴自棄に言葉を続ける。
「私は、ラシータをよみがえらせることができたんだ! 闇《ゼク》の力で、できたっ!」
ジェラスメインはその場に膝をついた。床に両手を着いて、身体を支える。それが精一杯だった。
「蘇らせて、そして、一緒に暮らせた!
ラシータと、母様と!
笑いあって、普通にっ!
毎日、ただ、一緒に居られるだけでいいのに」
床に引かれた大輪の花を描いた絨毯が、大粒の涙を吸って濃い色に染まる。
「……大好きだった。大好きだった!
生きていて欲しかったよ! どんな形でも、生きていて欲しかったよ!
だけど、出来なかった……!
ラシータより、キャニルスを継ぐことを選んじゃった。
ラシータより、自分のこと選んじゃったの!」
涙は音を立ててこぼれる。
「自分の、
ことだけっ!」
その場に伏せて、ジェラスメインは泣いた。
声を押し殺して、だけど、涙を一杯流して。
しばらくして、ジェラスメインの頭にそっと母の手が載せられた。
「よいのよ」
優しい声だった。
ジェラスメインは恐々と顔を上げる。母が微笑んでいた。首をかしげて、混じっている金色の髪がきらめいた。
「……でも、ラシータにいて欲しいでしょ?」
年相応の幼子の声に、母はゆっくりと首を振った。
「私は貴方がいてくれたらいいわ」
「ラシータが死んで悲しいでしょ!?」
母はそれに同じようにゆっくりと、だけど、今度は頷いた。
「悲しいわ。
でも、ジェラスメイン、貴方が居るわ。
貴方が居てくれれば、耐えていけるのよ」
「私は、闇《ゼク》だよ?」
その言葉に静かに首を振り、ただその小さな手を取った。上体を起こさせる。
「あなたを抱きしめると、辛いときもあったわ。それは事実よ。
抱きしめてあげられなくて、あなたよりラシータのほうを愛していると思わせてしまったのは、私のせいね。
だけど、どちらも私の子なの。どちらも大切な子供なの。だから、同じように愛しているのよ」
「だけど、私……」
「ラスメイ。ラシータを愛しているのなら、闇《ゼク》で留めるなんて悲しいことはしてはいけないのよ。あなたは自分を偽ることに、耐えていけないでしょう?」
ジェラスメインは食い入るように母を見つめていた。母は、微笑を絶やさないで、ジェラスメインの艶やかな黒髪を撫ぜる。
「そして、その姿に、ラシータも耐えていけないはずだわ。あの子も、あなたのことをとても愛していた……いえ、愛しているから。
だから、あなたのしたことは正しい」
「母様、知って……?」
「正しいの。ジェラスメイン」
ふわりと抱きしめられる。
暖かい。その暖かさに、ジェラスメインは目を瞑った。
ふわりふわり。ゆらりゆらり。
闇《ゼク》に触れれば、母が辛い事がわかっていた。だけど、このままでいて欲しいとも思った。
気持ちよくて、そして、眠くて。
『いいのよ』
何度も、何度も、母はそう呟いた。
その呟きを聞くごとに、ジェラスメインの瞼は重くなっていく。
「おやすみなさい」
泣きはらした目で、自分の腕の中で眠りについた子供にそう呟いて、母は微笑んだ。
そして、閉じられた瞼にそっと口付けをする。
デュラムは、早朝、いつもよりも騒がしい階下の気配に息をついた。夜通し起きて、この屋敷の中で起こることを一晩中、神経を研ぎ澄ませて探っていた。
襟を正し、唇を引き締めた。
喧騒へ向かって歩む。
喧騒は玄関で起こっており、その中心には、あの娘がいた。
デュラムの気配に気づき、階下からこちらを見上げる。そこには強い紫色の光があった。
玄関へは棺が運ばれていく途中だった。
見慣れた姿の人物が二人いた。1人は王付きの薬師、もう1人は王の側近であるセイだ。
(薬師か)
それと、あの棺。そこから結論を出すのは容易い。
だが、その結論にさえ、デュラムは顔色を変えなかった。
後から駆けて来た、ラーデイルがデュラムの横で、身を乗り出した。
「何をしているの!」
「おはようございます。義姉上」
「その棺をっ!」
「クィールクスタという花は、花の都・フュンランでは珍しくない花だそうですね。小さく可憐な花。私もフュンランに行ったが、思い出せない。そういう花は沢山あった気がするので」
ラーデイルは青ざめた顔を隠しきれなかった。救いを求めるようにデュラムを見る。
「その根は地中に張り巡らされるとか。花から花へ繋がって、そうやって増えていく種なのだと。
それが、横へ広がれば可憐な花で済むが、縦に長く伸びた根は痛みを抑える薬になるんだと、フュンラン城の薬師から聞きました。
だがそれは、強い毒にもなるんだと」
「何が、言いたいの」
「言わせたい?」
ラーデイルは言葉に詰まった。ジェラスメインはラーデイルから視線をそらし、デュラムを厳しい視線で捕らえた。
「兄上の身体にはその毒が、しっかりと残っていた。勿論、普通の医者なら気づかない……」
薬師は頷く。ジェラスメインはそれ以上を言わず、デュラムを見上げていた。
ラーデイルは震える声で、続ける。
「それが……何だというの! その毒を、誰がどこでどうやって、ラシータに与えたと? 私? 私だと思うなら証拠はどこに!」
「ラーデイル」
上擦った声に制止をかけたのは、デュラムの低い声だった。
「でもっ」
「騒々しい」
片手をあげて、娘の言葉を遮る。ラーデイルの顔が赤くなっていくさまが、ジェラスメインからもよく見えた。
デュラムは、ラーデイルが黙ったのを確認すると、すっとその手を下げた。そして、またジェラスメインをじっと見つめる。
「……お前なら、あちらを選ぶと思ったが」
「言いました」
ジェラスメインは目をそらさずに、一歩踏み出す。
「頂きたい、と」
デュラムはその目を見つめ、そして、息をつく。
「あの人の孫だな」
囁くような言葉は、ラーデイル以外に聞こえただろうか?
「やろう」
ラーデイルは非難するような目を父へ向けた。だが、デュラムはラーデイルに見向きもしない。ジェラスメインから目を離さない。
「お前にその座を」
ジェラスメインはかすかに目を見開いた。容易くその言葉が落ちてくるとは思わなかった。そして、その言葉を聞いた瞬間に、一つの疑問を口にしていた。
「どうして、ラシータをのこしたのですか」
デュラムはかすかに眉を上げたようだった。
「私があちらを選ばなかったら、こうなることはわかっていただろうに!」
デュラムは、上げた眉をふと元に戻した。
「忘れていたのだ」
何を? 問いかける紫の瞳をいつもよりも穏やかに見やるデュラムは、億劫だとでもいうように唇をもう一度開く。
「お前が、ノーラジルの孫だということを。『私の娘』ではない。あのノーラジルの孫だと」
「ノーラジルの」
「そして、私も……」
それ以上の言葉を飲み込んで、デュラムは口をつぐんだ。次の言葉は、少しだけ安堵したような声色をしていると思ったのは、ジェラスメインの気のせいか。
「猶予は1日でよい。お前が城へ行っている間に、私たちは姿を消す」
「父上!」
禁じられていたが、我慢できずにラーデイルが声をあげる。
「それでよいか」
ジェラスメインは頷いた。
デュラムはそれを見届けると、奥へ足を向けた。それをあわててラーデイルは追いかける。それを見送って、ジェラスメインは棺を馬車へ乗せるように合図をした。
「よかったのか」
それを見て、セイが低く問いかける。
「何を」
ジェラスメインは暗い声でそれにまた問いかけた。
「罪に、問わなくても。毒殺は……」
ジェラスメインは、ただセイを見上げた。
セイはその目に、少し気おされるように息を呑む。ジェラスメインは沈黙を保ったまま顔を背けると、馬車の方へ駆けて行った。残ったカシューがセイの傍らに立った。
「試しておられるのですか? キャニルスに泥を塗るようなことを、望むと?」
「それは貴方の入れ知恵か」
「あの方は解ってらっしゃる。解っておられないことは、私が教えて差し上げればよいだけのことです」
「……それでは、一つ忠告しよう」
セイはカシューへ無表情な瞳を向ける。
「キャニルスはキャニルスのをお持ちになったほうが良い。
王の薬師と私に頼るなど」
「キャニルスの醜聞は、王にとっても強い火の粉となると思いますが」
「それも謀っているのか」
「謀っているのではありません。あの方は、重要な方だ。キャニルスにとって。それは……そういう意味ではありませんか」
カシューはそう言って、セイを見やる。セイは、その言葉に何の反応も見せず、ただこう続けただけだ。
「埋葬が済めば、そのまま城へ。任命式は今日だ」
カシューは一礼した。セイは薬師を伴って、小柄な馬車に乗る。それを見送ってから、もう一つの馬車へ足を進めた。棺と共にジェラスメインが座っており、カシューが乗ったのを見届けて、御者は馬に鞭打つ。
しばらく揺られて、ジェラスメインが口を開いた。
「カシューさん」
「はい」
「もし、あのとき……。私が……」
言いよどむ彼女に、カシューは穏やかな笑みを浮かべた。それを見たジェラスメインは、恥じたような顔をして口をつぐんでしまった。
「……なんでもない」
ジェラスメインはそのまま窓の景色へ顔を向ける。その表情をしばらく見ていたカシューは、その表情に誘われるままに言葉を口にした。
「私はどちらでも」
ジェラスメインは少しだけ眉を寄せ、そして、低い声で問う。
「それは、私がノーラジルの孫だからか」
「いいえ」
カシューは微笑んだ。
自分の娘よりも幼い主人に、ただ静かに。小さいころ見た自分の父がノーラジルに仕える姿を思い出しながら。
「ジェラスメイン様、だからです」
そうして、そう言うことで笑ってくれたらとも思った。だが、少女はこちらから視線をそむけ、ただ小さな声で「そうか」と呟いただけだった。
その頬が少しだけ赤らんでいたのは、自分の気のせいではないことを願いつつ、カシューはそれ以上の答えを言葉にはしなかった。
|
|
| |
|