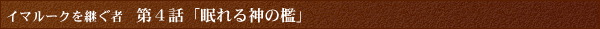 |
| |
| V キャニルスの血
|
| |
|
静寂はときに冷たさを思わせる。硬質の空気に満たされたその部屋の中心に男は立ちつくしていた。
静寂よりさらなる冷たさを湛えた瞳の先に、おかれた黒い石造りの棺もまた静寂。
男は細く長い指を自分の唇に当てた。微かに青みを帯びた肌の色と、削げ落ちた頬が、彼の印象をその瞳の冷たさよりも一層、冷たいものにしていた。
囁くような低い声が辺りを満たす。部屋は冷気を帯びた。
水《ルーシ》の囁きが、微かな嘆きに聞こえる。
この棺の中にいるものの死を、嘆く声を男は何度聞いたことか。
珍しく水《ルーシ》に愛された者だった。その血筋にふさわしく。
死んでしまってからも、嘆きは続く。
(その血筋にふさわしく)
男は思い返して、眉をひそめた。
(血筋)
この重い石棺の蓋の下にある冷たい身体を思い出す。
『そんなに憎いのですか』
棺の蓋に手を置いた。そっと撫でる。ざらついた感触。
『苦しんで死に逝く姿を見たいほどに』
ぎゅっと拳を握り締めた。
『私で、終わりにしてください……』
血を吐く苦しみの中でも、顔を歪めず、最後の力を振り絞り、私の首を両手で掴んだその姿を思い出した。
『妹は……そっとしておいて……下さい。父上』
引き寄せて、血の臭いのする言葉を吐きかけた。
『あなたの、娘です……』
(お前も、私の息子だっただろう)
なのに。自分の血にまみれ、そして、この下に居る。
そして、お前の思いなどに関係なく、あの娘は私の元に来るだろう。
かき混ぜる必要もない。彼女はやって来る。
あれは、ノーラジルの血を引く者。ノーラジルの面影を持つ者。
だから、やって来る。
男は、棺から手を離すと背を向けた。
嘆きが聞こえる。
私が愛せず、愛されなかった水《ルーシ》の嘆きが。
ただ悲しみを悲しむだけの嘆き。
『愛している、と、一言でいいのよ。デュラム』
与えられなかったものを、与えることなどできない。
憎ませることでしか、その絆を繋ぎとめておけない。
そういうことしか、知らない。
◇
与えられた一室で、齢500歳の青年は長椅子に寝そべっていた。赤い瞳を閉じて、いつもよりも喧騒につつまれた王城の気配に逆らうかのように、嫌味なぐらいにのんびりと。
明日はキャニルスの新しい当主が決まるらしい。それだけで王城がこれほどに騒がしくなることはないのだが、王宮魔術師の筆頭席も埋まる。その任命式とやらをするそうだ。
キャニルスの次期当主とやらを、彼は一度だけ遠目に見た。力を父から、容姿を母から受け継いだ、なんとも優美な、そして脆弱な娘だと思った。
その娘は、私の視線にさえ気づかなかった。
セアラは口元をゆがめた。
(キャニルスの血も、衰えた)
欠伸をかみ殺しつつ、そう思う。そして、狭い長椅子の上で器用に寝返りを打った。背もたれの方へ顔を寄せて、目を瞑る。
通り過ぎる人の気配を追って、それが十分に遠ざかった頃にふと瞳を開いた。茶色い落ち着いた色の大輪の花が目に入る。
キャニルス家の血統はシャイマルーク家と同じぐらい長い。初代当主の顔を、彼は思い出すことができた。レーヤルークの良き友として、常に側にいた女性を。
彼女を思い出し、一言で表せと言われたら、こう答えただろう『芯の強い女性だった』と。
長く艶やかな黒髪と、何を考えているのかわからない紫色の瞳。その瞳も時折強い光を帯びることがあった。星が瞬くようだと思ったこともある。口にすると怒るので彼女に伝えたことはなかったが。
毅然と顔を上げ紫色の目に確かな光を湛え、レーヤルークと同じ方向を真っ直ぐに見据えていた。その存在と美しさは、疲弊してゆく兵士たちに、戦う勇気と力を分け与えていた。
レーヤルークにだけに向ける、柔らかな笑顔……。
セアラはそれを思い出して、くすりと笑った。
だが、その美しい目は自分に向けられるたびに疑いの光を孕んだ。
幼子に向けるような目つきではなかっただろう。
『レーヤルークに災いなすなら』
疑惑の塊を隠そうとしない、冷たく澄んだ声はとても心地よかった。それが敵意の含まれた言葉だということは、まったく問題にならぬほど心地の良い響きを持っていた。
精霊から愛される声だ。尋常でない魔術を行使できる声だ。
それに酔った。だから、何を言われても平気だった。
『子供だろうが、私が殺す』
キャニルスの女性は強い。
常に強く、シャイマルーク家を守り、その傍らにいた。シャイマルーク家と婚姻を結んだものも中にはいる。
彼女はレーヤルークを愛していた。だが、レーヤルークは他の女性を愛していた。
だから、彼女はレーヤルークの傍らで、彼を守ることを望み、彼を守るための血統を残すために、他の男と結婚した。
ノーラジルもまた同じだった。
ただ、血統を残すために。
だが、その残した血統があれでは。それを継ぐ者があれでは。
(意味がないだろう? ノーラジル)
『冷たい花』と呼ばれた女性の、切れるような視線を思い出す。
無理に結婚を進めたときの激昂。普段、感情を表に出さない代わりに、その胸にある思いは凝縮されて熱く渦巻いていた。
それが自分に寄せられているものだと、わかっていたのだ。わかっていたのに、知らない振りをし続けた。
(応えることは、できなかった)
『あなたが望むものと結婚する。子供を産む。そして、キャニルスを守る』
私を睨みつけながら、低く言った。とても美しい顔だと思った。怒りと悲しみと私への想い。すべてを含んだ美しさだった。
『そのかわり、貴方と約束を』
それに否と、答えられたか。
『私の後に続く者を……』
「君はどこまでわかっていたんだい」
セアラはふと口元に笑みを浮かべる。そして、再び仰向けになって両目に掌を押し当てていた。
私の何が見えていた? 見えていたなら、それでどうして愛することができた?
セアラという名の、この塊を。
肩が震える。
感情の発露が、笑っているのか、泣いているのかわからない振動を生み出していた。
しばらくして、セアラの震えは止まった。
じっと、ただ顔を覆って、息だけを繰り返す。
青年は瞳を開く。そして、その場にがばっと身を起こした。
視線の先にある、彼の瞳の色に負けない赤い花を見つめ、狂いのない美貌に、笑みを浮かべた。悲しく。
「来たね」
小さな気配が大きな力と共に、戻ってきた。彼が張った魔術の守りに触れ、揺れる。大きな揺れが空気を震わせ、そして、それは心地よい鈴の音となって彼の耳に届いた。
葬儀を思い出す。幼いころの彼女に似た顔を赤くして泣きはらした目で見上げていた小さな娘。
白い花を彼女の亡骸の上へ落とすと、それを不思議そうに見つめていた幼子。
あの純粋な紫色の瞳が焼きついて離れない。
キャニルスの瞳だ。キャニルスの娘の瞳だ。
ノーラジルとした『あの約束』の先にいる、娘。
彼はその場に立ち上がり、鈴の音が続く空間を横切って、窓へ足を向けた。
強い力。強い意志。そこに見え隠れする弱さ……。
だが、ときおり揺れる弱ささえ、強さにできるのが人というものだ。
それを私の横を通り過ぎていった、多くの人々が教えてくれた。
「君との『約束』が生きるだろうか……? ノーラジル」
|
|
| |
|