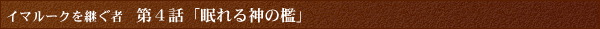 |
| |
|
◇
|
| |
小さな手を握り締める皺のある大きな手。それを紫色の瞳で感慨もなく見つめながら、少女の心は既に遠くにあった。
この手の持ち主がどんな権力を持っていようと、また、どんな賛辞をかけられようと、少女の心に感慨をもたらすものは何もなかった。
社交的な挨拶を一言二言交わして、それで役目は終わりだと感じていた。残りの時間、彼女の心は徐々に、早々にその場を立ち去りたいという思いに占められていく。その態度は、おそらく失礼にあたることであったが、彼女の若い……幼いと称してよい年齢と、それは一国の王を目の前にしての緊張から生まれる態度なのだという周りの勝手な想像によって、ほほえましいという好意的な印象を引き出していた。
それでも受け答えは、彼女の年齢の割にはしっかりしていて、その場に居合わせた人々に、聡明な印象を刻み込む。そして何よりも目の前の少女は彼らの命の恩人とも言える存在だったのだ。
彼女の名は、こうやってフュンランという国の最高権力者たちに刻まれることになった。彼女の持つ家名はあまりにも有名で、彼女の意志とは関係なく、シャイマルーク国への「恩」という形となってつながるであろう。その存在が闇魔術師《ゼクタ》だということは、王とその側近以外は知らぬことではあったが。
重い扉が閉まる音を背中で感じつつ、彼女はその城の明るく広い廊下を躊躇なく歩き始めた。扉を守る衛兵の、普段は余計な感情を排除しているはずの目に、好奇心と畏怖が混じる。この小さな少女が、一国の王や国を支える貴族達の命を支えたのだと。
その視線さえ振り放して、少女は真っ直ぐに前を向いたままこの城から立ち去ろうとしていた。そんな彼女の気を引いたのは、同じぐらいの身長の少女の影。
ふと、少女の紫色の瞳に現実というものが映った。
「アルディラ」
「お早い解放ね」
愛らしい顔を少しだけ傾げて、彼女は微笑んだ。栗色の髪が柔らかく揺れる。言葉を捜し続けている少女に、アルディラは笑みを深めた。
「帰るんですって?」
「ああ」
紫の瞳の少女――ラスメイはそう言って笑おうとした。笑おうとしたが、あまりにもぎこちなくて、右手で唇を覆う。
「アルディラには挨拶もせずに」
「構わないわよ。また来るんでしょ?」
その言葉にラスメイは小さく微笑んだ。出来ない約束はしたくないから、うんとはいえない。
「……ミラールたちを追いかけたりしないのね?」
「しない」
きっぱりとそう言って、ラスメイは廊下の先に視線を馳せた。壁に長身をもたれかけさせ、こちらを伺う人物。ゼアルーク王の腹心、セイ=シャド=レスタの紺色の瞳が監視するように光っている。
「シャイマルークへ帰り、家を……」
小さな握りこぶしを作って、ラスメイははっきりと言葉にする。
「継ぐつもりだ」
「……ラスメイ」
「奴らには渡さない……」
アルディラは心配そうな顔で彼女を見つめた。自分よりも2つ年下の少女。まだ10歳だと聞く少女の顔は、既に同年代のものだとはいえなかった。
「あの、ね。これ、渡しておくわ」
アルディラは右手に握り締めていた小さな袋を少女の目の前につきつけた。
ラスメイが不思議そうな顔でそれを受け取る。
「何?」
「あなたがおいしそうに食べてたから、きっと喜んでくれると思って」
頬を赤らめるアルディラ。こういう贈り物には慣れていないのだろう。ラスメイも思わず頬を赤らめてしまった。
そう『友達』から何かを貰うことなど初めてだと気づいた。
袋の中にはあの夜、アルディラと一緒に食べた焼き菓子が入っていた。
「……私もちょっとだけ手伝ったのよ、それ作るの」
ぽそりと呟く少女に、ラスメイは驚き、そして微笑んだ。
アルディラはフュンランでも王家に次ぐ高貴な家の姫君だ。彼女が厨房に入り、おろおろとする料理人の間で、粉をこね、形を作り、焼く姿を想像すると、うれしさがこみ上げてきた。
「ありがとう」
「それから、これも」
アルディラは不意に自分の首にかかっていた小さな首飾りをはずす。青い石のはまった、かわいらしい首飾り。
「急にあげたくなったわ」
「いいの?」
戸惑うようなラスメイの表情に、アルディラは正直ほっとしていた。そして、ラスメイの胸に押し付ける。
「私があげるって言ってるのよ。貰ってよ」
ラスメイはしばらく自分につきつけられた手を見ていたが、ふと音なく微笑んでそれを小さな手に受け取った。
開いて、そして、感慨深そうに見つめ、今度はアルディラを見て微笑む。
「うん」
「それ、水《ルーシ》の守護がかかってると思う。私が生まれたときに作ってもらったものなの」
アルディラはこともなさそうにそういった。ラスメイのほうが驚いて、思わず付き返そうと手を出した。
「そんな大切なもの、貰えない」
「そうなの、すっごく大切なのよ。水と火と風と大地、一つずつ貰ったのよ。そのうち一つがかけちゃったら、ちょっともったないわよねっていうぐらい、大切なの」
「だから、貰えないって」
ラスメイが焦ったように手を突き出す。だが、目の前の少女は楽しそうに笑って、両腕を後ろに組み、絶対に受け取らないという態度を示した。
「それぐらい大切なものをあげるから、私のこと忘れないでってこと」
棒読みの台詞にラスメイは目を丸くする。彼女が見つめるとアルディラの顔はますます赤くなってきていて、あまりにも面白いのでじっと見つめてしまった。
「何よ」
「なんでもない」
「……忘れないでね。私、あなたのこと好きだから」
ラスメイはふと真顔でアルディラの口元を見つめた。はっきりと開く唇の動きを見つめ、そして、真っ直ぐに向けられた瞳を見つめる。
「好きだから。あなたは私のこと嫌いで、こんなの迷惑かもしれないけど。私、あなたのこと好きだからね」
「嫌いじゃない!」
大きくかぶりを振って、そして、ラスメイはぽつりと呟いた。
「……どうして」
「いやなことあっても、あなたが誰かにひどいことして傷つけられたり、誰かを傷つけて、自分のこと嫌いになっても。そんなことにとっても辛くなったりしても。
私はあなたのこと好きなの。無条件で好きなの。その証」
「どうして、そんなに私なんかのことを」
アルディラはすっと手を出して、ラスメイの手を握り締めた。
「好きになるのに理由がいる?」
「違う、だって、私は……」
「貴方が何者でも、私は、あなたが好きなの!!」
最初は喧嘩するほど仲が悪かった相手でも、たとえ、闇魔術師《ゼクタ》だと知っても。
「だから、……ひとりぼっち、みたいな顔しないで」
ラスメイは目を見開いた。零れ落ちそうな紫の光。アルディラは微笑む。
「忘れないで」
アルディラの目の前でラスメイが微笑む。ぎゅっとその首飾りをにぎりしめて、うんと答える。
だけど、アルディラの言葉の奥にある本当の意味を、ラスメイは気づかなかっただろう。気づかなかっただろうということを、アルディラは気づいていた。
(忘れないで)
遠慮がちに手を振る彼女を見送って、アルディラは心の中で祈りをささげる。
(まだ子供なんだよ)
遠い目をして、厳しい顔で、ずっとずっと向こうを見つめてる少女の目をこちらに向けておきたかった。
ラスメイの小さな背中が、冷たい目をしたシャイマルーク王の使いのもとへ近づいていく。
(ラスメイ)
アルディラはきゅっと自分の拳を握り、唇につけた。そして、祈るように目をつぶる。
(忘れないで!)
まだ子供なの。
そんな厳しい顔して生きていかないで。
『好きなんだ』
彼女の言葉が耳によみがえった。2人で夜、ラスメイに渡したあのお菓子を食べながら話したことがある。そのときに、彼女はすごく切なそうにそういった。だけど、今よりとても暖かな声で。今よりずっと楽しそうな声で。
今の声と比べたら、とても辛くなるぐらい、生きた響きがあって……。
ふとアルディラは廊下の先を見つめた。もう彼女の背中は見えない。
(助けてあげて、誰か!)
アルディラの脳裏には一人の男が浮かび上がる。黒い髪に緑の瞳。凛とした視線を前に向けて。
いつか神話の描かれた絵本で見た、あの神の姿に似た青年。
(ラスメイを、助けてよ……!)
「シャイマルークにはどれくらいで着く?」
自分の隣、漆黒の馬にまたがった少女が、小さく聞いてきた。美しい紫色の瞳に浮かぶのは強い決意の色。そして、ときどき見せる迷い。不安定に入れ替わる光を、セイ=シャド=レスタは無表情な紺色の目で見ていた。
「馬を休ませつつ……20日ほどか」
「そんなものなのか」
ラスメイはそう呟いた。ランとミラールとエノリアと、途中寄り道しながら辿ってきた道が、たったそれぐらいで折り返される。
だが、急ぎたい。
「急ぐのだろう? キャニルスも次代の長を決めねばならない時期だ。ゼアルーク様には事情をお伝えしたが、キャニスル家は大きい。国王でさえその当主の継承にあまり口出しはできないだろう。
とくに、君の存在は長い間表立ってはいないのだから」
「……本当に、おにいちゃ……、いや、ルシータは……亡くなったのか?」
揺れた。セイは目を細める。
弱い表情の奥で、ゆっくりと何かが形成されていた。
「本当だ」
迷いを決意に変える方法は簡単だった。セイにとって、否、ゼアルークにとって、この少女をシャイマルークに繋ぐことは、有効な事のように思えた。
エノリアとの繋ぎとしても、そして、シャイマルークを守るためにも。
「殺された?」
頬をぴくりと動かしながら、ラスメイがそう聞く。セイは明確な答えを持っていなかった。だから、わからないとしか答えなかったのだが、その答えにさらに質問を重ねることをせずに、少女は黙り込んでしまう。自分の愛馬にそっと手をやり、その鬣を何度も何度も撫でていた。
「早く帰りたい」
ぽつりと呟いた少女の声音は、もう震えてはいなかった。
表情までは伺えなかったが。
ただ、その手がきゅっと握り締められたのを、セイは見逃さなかった。
小さな拳。まだ、幼い子供の拳だ。
セイは同じように決意で握り締められた小さな拳を知っていた。真っ直ぐに前を見詰める黒い瞳。光が差し込めば、深い緑色になった真剣な瞳。
友が欲しいと。隣にいてくれる、ときには背中を預けることが出来る信頼できる存在が欲しいのだと、ただそれだけを純粋に思い続けた者を知っている。
私の存在を許すのかと問うた。
決して裏切るなという答えが返ってきた。
『裏切るな。裏切らず、私のために働いてくれるか。それを誓うなら許す。お前が何者であろうと許す』
彼は、あの言葉を覚えているのだろうか……。
それが彼の『望み』だ。
セイは懐かしさに目を細めた。そして、馬を駆けさせる。それをぴたりと追ってくる小さな闇《ゼク》を感じながら……。
|
|
| |
|