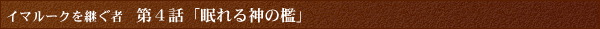 |
| |
|
◇
|
| |
顔に光の暖かさを感じて、ミラールはふと目を開いた。あのあと、火の番を買って出たスーライに任せて、体を休めたことを思い出す。
ミラールがたどり着いた時と同じくして、周りを囲んでいた魔物の気配は不思議と消え、皆が不審な表情を浮かべて顔を見合わせた。ただミラールだけが、その理由を知っているような気がしていた。
まだ誰も起きていないようだ。ミラールは緩慢に体を動かす。もさりとした感触が背中をうごき、ようやく自分に毛布がかけられていたことに気づいた。
自分がかけて寝た覚えがない。その毛布を手にとってしばらく見つめた。
(カーラかな)
おそらくそうだろう。ずっと自分のことを心配してくれている彼女の視線は、ありがたい。だが同時に、辛い。
ミラールは毛布をその場にぽそりと置いた。そして、まだ寝起きの気だるい思いを引きずりながらも焚火の方へ足を向けた。
もう、火は既に小さい。それを座り込んだまま見つめている人物がいた。
「交代したの?」
そっと囁くと、人影が振り返る。ランだった。スーライはそこから少し離れたところ、木の根元に寝転んでいる。
「ああ、目が覚めたからな」
同じように囁いて返事をするランの隣に、ミラールは座り込んだ。
昨日のことを思い出す。自分のことを言うべきだろうかと迷った。ザクーに会ったこと、そして、ザクーからもらったジュラのこと。それから察することが出来る『自分のこと』。
『自分のこと』話せば、ランはどうするのだろう?
僕のことを、どう思うのだろう?
深い闇を怖がりながらも覗かずにはいられない、深い森を前にした子供のころの思いによく似ている。似ているが、そこにはあのときのわくわくとした思いがない。森の闇は闇でしかないことを、もう知ってしまった。そして、ときには命を奪う魔物の住処であることも。
「体……大丈夫なのか」
くすぶっている焚火の火を見つめたまま、ランはそう聞いてくる。もう枝を足す必要はないのだろう。
「大丈夫。心配かけたよね」
「小さいころ、体弱かったよな? 忘れてた。すまないな」
「ランが謝る必要なんかないよ。僕もずっと忘れてるぐらい調子がよかったんだしね」
「お前が倒れて、昔のこと、思い出したんだよな」
火に入れるために集めた乾燥した枝の一本を取り上げて、ランはそれを手持ち無沙汰に振った。
「俺、いつもミラールを引っ張り出してさ。セアラにしこたま怒られたっけな。体調のことなんて無視して、自分が遊びたかったからってだけで」
「僕は嬉しかったよ。一人ぼっちにされるのは嫌だったし」
笑いながらミラールは答える。そうか、と言って笑うランに目を細めた。
「結構大きくなるまで、ランしか友達いなかったしさ。ランだけ外に遊びに行くの、ちょっと辛かったし」
「そうだっけな?」
「そうだよ。ランは、すぐに誰とでも仲良くなって。僕が寝込むと平気で放っておいたりしてさ」
「でも、セアラがいただろ」
「セアラはいたけど。でも、寂しいのには変わらなかったって」
そうかぁと気の抜けた声で相槌を打って、ランはまた枝を振る。その動きを見つめて、ミラールは目を細めた。
「なぁ、ラン。僕ら、こうやって話すのは久しぶりかもね。旅に出て、いろんなことがあってさ。2人だけで顔を合わすことも少なくなって」
「そうか? そうかな」
「ランが本音を言わなくなったのは、随分前からだけどね」
「……」
「家を出て行くちょっと前からかな」
ランは唇を閉じた。そして、首をかしげる。
「そんな風に思ってたんだな」
「ま。僕も言わないことがたくさんあるから、おあいこなんだろうけどさ」
ミラールは近くの枝をひろって、意味もなく焚火に放り込む。一瞬微かに火は勢いをみせ、2人の顔を赤く照らす。本当に一瞬だった。
「ランがいない間、セアラはとても寂しそうだったよ」
「お前がいるから大丈夫だろうって思ってさ」
「ランはラン。僕はランの代わりにはなれないよ」
火はさらに勢いを弱めた。ランはただそれを見つめている。その顔を少しだけ伺い見て、ミラールは膝を抱えながら同じように火を見つめた。
揺れる炎。
人を惹きつけるのは、光を持つからか、それとも暖かさを持つからか。それともその色ゆえか?
「ラン」
「ん?」
「エノリアのこと、好きなの?」
ランが少しだけ息を止めたのがミラールにはよく分かった。改めて問われることが予想外だったのだろう。
「どうしたんだよ」
「……僕は好きだよ、エノリアのこと」
穴が開くほど見つめるランの視線を感じた。だから、ミラールはランのほうへ顔を向ける。
「譲ってって言ったら、譲ってくれる?」
挑むように視線に力を込めた。ランの表情が変わる。驚きはゆっくりと焦燥を含む。完全にそれに支配される前に、今までにランから感じたことがない、人の闇を含んだ感情の色を見た。
ミラールは目を細めた。
その変化を見るのが嫌だった。だけど、確かめずには居られない。
心が、きしんだ音がする。表面には現れずに、ミラールの中でだけ響く音。
きっと自分は、どこかで変わらずに居て欲しかったんだ。『あの約束』のころ、そのままで。そのままでいられるはずがないのに。
多分、あのころが一番幸せなときだったから。
「ランの表情は言葉より物を言うね。
嘘だよ。譲るとか譲らないとかエノリアに失礼だ」
ミラールはまた膝を抱えこんだ。
「だけど、これだけは本当だよ。僕はエノリアに惹かれてる。恋だとか愛だとかそういう言葉にはめられないけど」
ミラールは目をつぶる。
(待ってる?)
ミラールは自分に問いかけた。
何を待ってる? ランからどんな返答を待ってる?
何なら僕は満足できる?
息をついて、髪をくしゃりと握りしめた。
(満足、ね。勝手だな)
微笑してミラールは立ち上がると、茂みへ足を向けた。何かを考えているようなランを見下ろす。
「顔、洗ってくるよ。この先に、泉があったよね」
「ああ」
狐につままれたようなと言った表情で、ランはそう返した。ミラールは完全にランに背を向けた。
背後で焚火がはぜる音がした。ただ、それだけだった。
ミラールが泉の方へ向かってからしばらくして、1人2人と体を起こし始めた。その間、ランはじっと焚火を見つめつづけていた。
「ラン」
ぽんっと肩を叩かれて、ランは顔を上げた。ミラールがいつもの顔でランを見下ろしている。
「火、消えてるよ。もういいでしょ?」
「ああ、そうだな」
ランは重い体を起こして、先ほどまで言っていたことを忘れたようなミラールを見る。
「早く出発しないとね」
そう言って、今度は泉の方へ向かおうとしているカーラとエノリアに近寄って挨拶をする。
交わされる笑顔を見ながら、その場に立ち上がりランは大きく伸びをした。
『譲ってって言ったら、譲ってくれる?』
ミラールは嘘だと言ったが、そこには真実が含まれているような気がして仕方なかった。
(譲るも何も)
ふと笑いがこみ上げた。
エノリアは俺の物じゃない。
2、3度髪を乱暴に撫で付けて、ランはエノリアとミラールから顔を背けた。
愛馬に近づいて、黙々と出発の準備を始める。主人の暗い感情に気づいてか、ラルディは鼻をこすりつけてきた。
「ラルディ」
【恋人】という名前を持つ愛馬に、ランは薄く笑う。
「俺は不器用か?」
ラルディは知ってか知らずが鼻を鳴らした。それに自嘲したような笑みを浮かべて、ランはその鬣を撫で付ける。
『器』
その単語がランの意識を捕らえて離さない。
何が本当で、何が偽りなのか。
問うて答えが返ってくるのならば、叫びたい気持ちに狩られる。心配そうにこちらを伺うラルディの首に額を押し付けた。
「大丈夫」
決意の色を瞳に浮かべて、ランは頷いた。
「やり遂げなくちゃな……」
|
|
| |
|