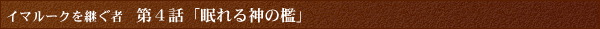 |
| |
|
◇
|
| |
膝を枕として貸している青年を覗き込んで、カーラは彼の呼吸の深さを探った。ゆっくりと緩んでいく周りの空気に、彼女は目を細めた。
彼女の記憶の中でのミラールの顔は、今よりも幾分幼い。今の顔にそのころの面影は残っている。微笑みのよく似合う柔らかさがあり、誰も拒まない優しさがある。
(知らない部分もある)
会わなかった年月分と言い切れない何かがある。カーラはどこかで寂しさを感じていた。もちろん、それは自分の勝手な思いだということも自覚していた。
厳しい顔だと、思うときがある。ふと思い返すと、幼いころもそういう顔をしていたのかもしれない。年齢にそぐわない影を、自分が見落としていただけなのかもしれない。自分の中に、それを拾い出せるほどのものがなかったのかもしれない。
茶色の柔らかな髪をそっと撫でた。
与えてくれた人だから。自分に『何か』を与えて、見せてくれた人だから、苦しい顔をしていてほしくない。
彼のために何かをしたい。そう思う。
そんな彼女の視界で影が揺れた。気配で近づいてきた者が誰なのかはすぐにわかった。彼女が分かりきれない気配を持つ者は、この場には1人しかいない。
一緒にいるミラールたちの中でも、その人の持つ空気がなじんでいないことは感じ取れていた。
「疲れてるみたい」
カーラは独り言のように言った。相手に届いていても、届いていなくても、どちらでもよかった。その独り言を受け取ったのかどうかはわからないが、ユセは無言で彼女の隣に座った。
「繊細で誰よりも感受性が強くて……無防備すぎる」
ミラールのことをそう呟いて、カーラは隣に座った男を見つめた。目の前のこの男性も、カーラには興味深い存在であった。
どこにもなじまない。浮かべる穏やかな笑みが、他人へ向けた壁であることを彼女は感じ取っていた。
「あなたの属性は?」
ユセは突然彼女へ問いかける。カーラはさすがに驚いたように顔を上げ、そしてにこりと微笑んだ。
「不躾だ」
「何か……見えてらっしゃるのでは」
カーラの言葉を受けて、遠慮がちに……だがはっきりとユセはそう問いかける。カーラはそれに微笑を向けた。ミラールの髪を梳くように撫でる。答えない。ユセは構わずに続けた。
「人を魅せる力を持つ者には、闇《ゼク》を持つ者が多いのです」
「それは初耳」
「そうでしょうね。他の要素で隠れる程度です。表に発現するほど、強くありませんから……。誰も知らない」
ユセはそう言ってミラールを見下ろした。
「微量の闇《ゼク》。人の勘を多少鋭くした程度の予感。声に音に、魅了の力を持たせる程度。貴方の歌声を、私は聞いてみたいですね」
「高いよ。1人で聞くには」
「……でしょうね」
ユセはそう言って燃える炎を見つめていた。
それ以上、何かを言うこともなく。
カーラは、それに安堵して同じように炎を見つめる。
「この世界に、何人いるのか」
ぽつりと呟くカーラの言葉を、ユセは無言のまま先を促す。
「闇《ゼク》を持つ人間が。そんなに少なくはないと思うんだけどね。隣人にいなくても、同じ町には数人いるかもしれない。光《リア》を持つ者がようやくわかる程度なら」
ユセは目を伏せた。カーラは息をつく。
「あんたの思うとおり。私には多少の闇《ゼク》があるらしい。両親はそれを煩わしく思った。だって、母は少しの光《リア》を持っていたから……。
属性って何だ? 親から継がれる物でないのはよくわかっている。だが、光《リア》を持つ者から、闇《ゼク》が生まれるのは残酷だ」
カーラは声を殺して笑う。そして、また愛しそうにミラールの髪を撫でた。
「煩わしいついでに、金に困ったときに放り込まれたのよね。娼館にね。人を魅せる力ね。確かに役には立ったかな。本人が望まぬところで。多くの人間が私を抱きたがった。おかげで契約が切れるのも早かったけど、娼館が私を手放したがらなかったのも事実」
カーラは優しく微笑んだ。
「そんな中、この子との出逢いは私にとっては宝物だった。たとえ、私の歌声が闇《ゼク》の産物だと言われようが、あの場所から抜け出す機会をあたえてくれた」
母親のような優しさをこめてミラールを見つめるカーラをしばらく見つめて、ユセは視線を揺れる炎に戻す。
ユセもカーラも随分長い間言葉を発しなかった。
呼吸の音が、周りへ溶け込んだような気がした瞬間、ミラールががばっと身を起こした。突然の動きに多少驚きながらも、カーラは何かを探すように周りへ視線を向けるミラールに、遠慮がちに声をかけた。
「どうしたの、ミラール」
返事はない。彼は立ち上がった。
「あの2人なら、少し離れてるだけよ」
「違う」
ミラールは視線を一点に定めた。周りから見ると異常なくらいに空気が張り詰めていく。カーラとユセは顔を見合わせた。
何があるというのだろう。
ミラールの視線の先を見つめた。焚火の明りが届くか届かないかの境界で黒く影を落とした木の枝が揺れた。
が、それに気づいたのはミラールのみ。ゆれる焚火の明りが作り出す灯火の場の外へ、痛いぐらいに神経を集中させていた彼のみだ。
「探してくる」
「え?」
聞き返すカーラにミラールはにこりと微笑んだ。
「心配、しないで」
カーラの制止の声は耳に届かなかった。ミラールは、さきほどまで寝込んでいたとは思えない機敏な動きで、森へ走り出した。
ユセがその後を追おうとした。その足元を何かで作り出された力が直撃する。飛び跳ねた石に額を弾かれ、ユセは一瞬だけそちらに気を取られた。その瞬間にミラールの後姿を見失ってしまう。
まるで闇に飲み込まれるように消えた。
ユセは明りの作る境界線まで脚を進め、そして、ようやく額の痛みに気づいたかのように、右手を上げる。
「ミラール……さん」
カーラが駆け寄り、闇を見つめるユセを覗き込む。
「ミラールは?!」
ユセは黙ったままその先を見つめているだけだ。カーラがその先へ進もうとすると、彼女の二の腕を掴むものが居た。
コウトールが静かに彼女をとどめる。
「コウトール! でも、ミラールが」
「落ち着きなさい。これ以上は……危険です」
「どうして!」
「聞こえないのですか!? 獣の息遣いが!」
滅多に聞かないコウトールの強い声色がカーラを我に帰らせた。耳を澄まし、闇に目を凝らす。
パチリと焚火がはじける音がした。3人の背後を照らす炎の明るさが強くなって背後に気配を感じる。
スーライが松明を掲げているらしい。カーラの目の前の闇が収縮したように光に飲み込まれた。その向こうに光った1対の明り。
松明の角度を変える。
と、もう1対。2対……と光が見えた。
「何故」
かすれた声でカーラが呟き、唾を飲み込んだ。
「襲ってこないの……?」
「見張っているのでしょう」
ユセの声が囁くように返される。
「……我々がここから先へ行かないように」
「ミラールは?」
返答の変わりにユセは眉間に皺を寄せた。優しい顔が険しくなる。それがカーラの不安をあおった。
「ミラール……」
◇
何故それを『呼び声』だと思ったのか。
ふらつく頭を支えながら、ミラールは木の間をすり抜ける。不思議と枝が避けてくれているような気がした。頬を掠める枝はあっても、傷が付くことはなかった。
呼ばれていると感じたその声は、どちらかというと歓迎できない類のものだ。呼ばれつづけるのが不快だから、声に従うことにしたというところだった。
カーラの声をすり抜けて、魔物たちの息遣いを側で聞きながら、どこかで襲われることはないだろうという確信をもって、森の深みへ足を進めた。
正直言うとどちらでもよかった。
罠であることも覚悟していた。
ただ自分がしたいように、足を進めただけだ。その理由が『不快感を拭い去るため』であっても。
危険を回避することを本当に望んでいたら、『不快感を拭い去るため』など、危険に踏み込む理由にならなかっただろう。
ミラールは足を止めた。
目の前にある人影。それがミラールを招いた『呼び声』だった。
足を止め、息をゆっくりと吐いた。眩暈は消えていた。冷たい空気が不思議なほど心地良い。
「ミラール=ユウ=シスラン?」
自分の名の響きに、ぴくりと体が震える。
「ミラール」
こちらに背を向けていたそれが、ゆっくりと動く。その正体を見て、ミラールの体がもう一度だけ震えた。
「……ザクー……という魔物?」
「ああ、聞いてるんだ。残念だな。驚きもしないなんて」
ランと同じ目で、ランと違う笑みを浮かべる。ミラールはその顔の造作一つ一つを見つめていた。ランと違うところを探すために。
「何故、呼んだか、聞かないのか?」
ザクーはそう言ってから首をかしげた。
「呼ばれたと思ったから来たんだろう?」
「そうだけど……」
擦れたような声の先を取って、ザクーはふと微笑んだ。
「殺してやろうと思ったからだよ。ミラール=ユウ=シスラン」
その言葉をミラールは、当然のように受け止めて意識の中で消化した。
「そう」
簡単にその言葉が出た。
「……お前は、『あいつ』にとって、大切な存在の一つだから、殺してやろうと思ったけれど……。会ってみて分かった。お前『も』必要なんだ」
「あいつ?」
「……だけど、お前の望みはシャイナと同じで。シャイナよりも深く苦しく憎しみにさえ近づいている。いつか私にはお前が必要になるだろう。お前も多分、私が必要になる」
「必要?」
すぃっと闇をわたるように、気づけば目の前までザクーは近づいていた。ミラールの胸の辺りに突き出された拳。それを彼はゆっくりと開いた。
掌にあるのは小さな珠。鈍い光を放つ珠だ。
「これをやるよ」
ミラールは不思議そうにザクーを見つめた。ザクーの目を見つめ、そしてその掌に視線を返す。
「僕はこれを見たことがある……」
「あるだろうな。これを持っていたらいい。少しは体が楽になるだろうから」
問いかけるように視線を上げるミラールに、ザクーはふと目を細めた。彼の右腕を掴んで、掌を反させ、そこへ珠を落とそうとする。
「!」
強く右腕を引っ込めようとしたミラールの動きに対応できず、珠は彼の掌を掠めて地面に落ちた。ザクーはミラールの右腕を握り締めたままだった。
ザクーは不満そうに転がった珠を見つめていたが、ミラールの右腕を離さずに腰を曲げてそれを拾い上げる。
人差し指と親指で摘み上げて、目の前で検分するように見つめた。
「やると言っているのに」
「……ジュラ」
呟いたミラールを驚いたようにザクーは見つめ返す。
「知っているんだ?」
「セアラが……」
熱に浮かされるようにそう呟いて、ミラールは首を振った。
「夢だ……。あれは。忘れろって。……違う。『そのとき』はまだのはずだよ……」
「そうか。なら忘れてるといい。だけど、苦しそうだな。足りないんだろう?」
ザクーはその珠をミラールの目の前でちらつかせる。それをミラールは空ろな瞳で追った。手が出かけるのだが、自分の中の何かがそれを受け取ることを拒否し続けていた。
「やる。早く取り込めばいい」
「……取り込む?」
「そうか。忘れているんだな……。じゃあ、飲み込めばいいよ」
ザクーは目の前でちらつかせていた珠を、ミラールの唇の前へ持っていった。
「ほら」
ミラールは顔を背ける。第一彼の頭の中は混乱していた。ジュラという名前を聞くと、意識は紗がかかったような緩慢さが強く支配する。だが、その得体の知れないものを飲み込めと言われて、素直に聞けるような状態ではない。朦朧とした意識と警戒心がミラールの中でせめぎあった。
右腕が一瞬だけ離され、突っぱねていたミラールの体が揺れた。後ろ向きに倒れかけたところの体制を立て直す。ザクーの腕が腰を捕らえるのを感じた。逃げなくてはと思ったが、体を引き寄せられる。
強烈な力で頬を押さえられる。そむけていた顔が強制的にザクーへ向けられた。
「飲めよ。楽になるんだから」
仕方ないなとまるで聞き分けのない子供に言い諭すかのような声色が、ミラールの機嫌を損ねる。
「お前なんかから……!」
口を開いた瞬間、口を覆われた。一瞬で混乱したミラールが自分が何をされたのかに気づいたのは、小さく冷たい感触が喉を滑り落ちようとしたときである。
揶揄するようなザクーの笑みを前に、ミラールは口を両手で覆って、激しく咳き込みだした。中途半端に喉に入った異物が、吐き気を同時に催させる。体から出そうと激しい咳が続くが、それは喉をゆっくりと下っていった。
何度か咳き込み、うっすらと涙を浮かべたままミラールはザクーをにらみつけた。
「……飲ん……だ」
「薬みたいなもんだって言っただろう? 気分は?」
笑みを浮かべた目を睨みつけて、ミラールは体を起こした。先ほどまでの体の辛さがまたたくまに消えていく。
自分の中で拒否し続けたジュラが、ゆっくりと体に浸透していくのが分かった。
初めてではない。これを飲み込むのは……。この感触を体が覚えていることに気づいた。
ミラールは唾を飲み込む。
「どういうこと」
呟いた一言に、ザクーは眉を上げただけだった。
「あれは一体何?」
唇を引いて笑みを作る。だがザクーは答えない。
「ジュラって一体何!?」
一歩踏み出したミラールの真剣な表情を、ザクーは微妙な瞳の光で以って受け止めた。
「ジュラは、闇《ゼク》だ。闇《ゼク》でも、罪から生まれた闇《ゼク》だって聞いてるな」
闇《ゼク》。
ある程度は想像していた。ラスメイに見えていたものが、明らかに自分の中にあることを、覚悟できていた。あの闇《ゼク》を持つ少女の強さは、自分の中にあるものを認めさせてくれるものでもあった。
「たとえ僕の要素の中に闇《ゼク》があるって言われても、受け止める準備は出来てる……。だけど」
ミラールの呟きをザクーはただ聞いていただけだ。
「……僕は、何だ?」
搾り出すような声に、ミラールは答えを求めてはいない。ザクーから答えが欲しかったわけではない。ジュラを取り込むことが出来た自分は、あの少女とはまた違う存在だ。
不安がっていたラスメイを思い出す。
彼女には見えていた。
「僕は……魔物?」
ミラールの言葉にザクーは目を細めた。嘲笑が消えた。
「僕はお前達と同じものなの?」
「……違う。俺とお前は同じではない。同じなら、俺にお前は必要ではない。お前が『人間』でなければ……。だけど」
ザクーはミラールの耳元に囁いた。
「人と同じでもない」
ミラールは拳を握り締める。そして、うつむいた。
「揺れ続ける、哀れな人間……。強い光《リア》や『イマルークの血』に近づかなかったらよかったのに……」
ミラールの耳に、風の音のように伝わったザクーの言葉には、微量の優しさがこもっている。
「呼べばいい。そのときになったら」
「そのとき?」
「揺れるのを、止めたときだ」
空気が揺れる音にミラールが顔を上げたとき、すでにザクーの姿はなかった。気配だけを残して消えた彼の顔を、ミラールは思い出すように目を細めた。
ランに似ている、全く似ていないその存在を、ミラールは嫌悪感とは違うものと一緒に意識の中にとどめて踵を返した。
とぼとぼと歩いて来た道を帰る。うつむいていたミラールの瞳に赤い光が入った。
揺れる炎をこれほど暖かく思ったことはなかった。
ずっとそうやって待っていたのだろうか。ユセとカーラとコウトールとスーライの心配そうな顔。それに、エノリアとランの顔も加わっていた。
エノリアがこちらへ歩み寄る。歩み寄って、そして抱きつかれた。ミラールは目を丸くした。
「エノリア?」
「無事でよかった!!」
ミラールは自分の顔から力が抜けるのを感じた。暖かな光とエノリアの暖かな体温、そして気持ちが伝わってきて強張っていた顔が緩む。
「私たちを探しに行ったって聞いて! 心配したんだから!! 魔物はたくさんいるし!」
「ああ……そうか。ごめんね」
ミラールはエノリアの肩越しにランの顔を見た。安心したような顔をして、ランは頷く。ミラールはそれを見つめてから、ゆっくりとエノリアを引き離す。そして、柔らかく微笑んだ。
「ごめん。大丈夫だから」
と、エノリアはミラールを見上げて、そして微笑んだ。
「よかったぁ……。顔色もよくなったね」
その言葉に少しだけひっかかるものを感じながら、ミラールは笑みを崩さなかった。
カーラも近寄ってきて、ミラールの頭に手を置く。
「もう、心配させないで」
「ごめん、カーラ……」
あらゆるものが持つ暖かさに泣きたくなる。
ミラールは微笑んだまま、皆を見渡した。
相容れないものを持ち続けたまま、微笑を絶やさない。自分の中にあるしこりのようなものを感じながら、ミラールは目を伏せた。
僕が何者でも。
この思いが変わらなければいい。
大切だと思わせていて。
大好きだと思わせていて。
君たちを何よりも大切なんだと……思わせていて……。
|
|
| |
|