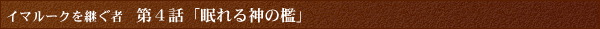 |
| |
| III 偽りと真実と |
| |
小さく縮こまった背中を、僕はいろんな気持ちで見ていた。
ランが叱られている。僕とあの森へ行ったことで、ランが叱られている。
セアラは諭すような怒り方をする。だけど、今日は執拗なぐらい何度も同じ言葉を繰り返して叱っている。
僕のことで、ランは叱られてる。
あの暗い森に、僕を連れて行ったことで。
あの暗い森で、一晩過ごしたことで。
森で僕の前を走って、ひっぱってくれたランの背中は、とても頼もしかった。だけど、今、僕の目の前にあるランの背中は、小さく震えていた。
セアラの言葉の端々から、ランが僕のことで責められているのを感じていた。
ミラールが……。ミラールを……。
僕は何度も僕のせいだと叫ぼうと思った。でも、怖くてできない。セアラはランのことばかりで、意識は、僕にはなかったから。
僕はランの背中をぼおっと見ていた。
セアラのため息。そして、ようやくセアラは僕へ瞳を向ける。
言おうと思った。僕も悪いと。
だけど、セアラは怒らなかった。
僕を怒ったりはしなかった。ただ、微笑む唇と微笑まない瞳で見つめていただけだ。
『ごめん、ミラール』
震える声。
『一緒にまた、行こうな』
震える唇。ぎこちない笑顔。
そればかり、思い出す。こんな森で夜を過ごすことなんて、あの時以来だったから。
もつれそうになる足を交互に動かすので精一杯だろうエノリアを、ときおり引っ張りあげながら、走る。
大丈夫かとは聞かない。エノリアの走る意志が伝わっていたから。もつれてもこけても、弱音一つはかずに、彼女は再び立ち上がって走りだした。
不穏な空気を感じて、ランは立ち止まった。エノリアは急に止まれず、ランの背中に軽くぶつかってようやく足をとめた。何? と聞きたそうな空気をひしひしと感じている。だがランは無言で剣に手をかけた。かちゃりと左腕にはめている2連の腕輪がぶつかって音を立てる。
切迫している。エノリアの不安がひしひしと伝わる。だが先に逃げろとは言わなかった。ここで離れるのは上策ではないだろう。
相手に、心当たりがある。
「結界も意味ないな」
吐き出すように呟いて、ランは剣の先を目の前に広がる闇へ向けていた。
「警鐘にしかならない」
「逃げないのか?」
奥から聞こえた声に、エノリアは顔を上げた。ランにも聞き覚えのある声だ。
「……無理だろ」
「安々と引っかかってくれたね。本当に旧道を選んでくれるとは思わなかった」
闇から嘲笑がもれた。ランが消えた松明に火を呼んで向ける。そこにあったのは自分とそっくりな顔。だが、彼ならば決して向けないだろう暗い嘲笑が、張り付いている顔だった。松明の揺れと共に、顔におちた影も揺れた。
ザクー。
ランの姿とそっくりの青年。違うのは髪の長さと目の色だけ。その体は闇《ゼク》で占められている。シャイナの……月の娘《イアル》の願いから生まれた、魔物。
「引っかかる?」
「おかしいと思わなかったのか? あの状況……とても都合よく船は修理に出され、大人数で海路をわたるのは難しいだなんて」
ザクーは指折り数えるように、言葉を繋げる。
「妙な胸騒ぎがして、神殿へ急がなくてはならないような気がする。どうしてそんな予感に振り回された?」
ランは少しだけ目を見開いた。ザクーは満足そうに微笑む。
「俺はお前に影響されるけど、お前に影響を多少は与えることができるらしい」
不快そうなランの表情と反比例してザクーの表情には喜色が混じる。
「何故」
吐き捨てるようなランの言葉に、ザクーは既に答えを用意していた。
「俺はあそこに居たんだ。お前が最初に血を流した場所に。存在していた」
ますます怪訝そうなランの表情をサクーは楽しむように唇をゆがめる。
「そして、待っていた……。どこかで俺の意識をつなげてくれる純粋な望みが生まれることを」
そう言って何かを問いただそうとしながらも、適切な言葉を見つけることの出来ないランのもどかしさを、笑う。
「場の話を聞いたんじゃないのか?」
ザクーは一歩足を踏み出した。影が揺れる。
「……その場さ。意識して作られた結界の中。最高魔術師によって作られた最高の結界。ほころび目のない壁は一体何のために作られた? 中のものを守るためだと? 外から内へ入れないためだと? あの、最高の場所。光《リア》が集まり、彼が眠る……」
エノリアがはじかれたように顔を上げる。
「お前が産まれた場所」
「黙れ」
気迫をこめてランは剣をあげる。切っ先はザクーの眉間へ突きつけていた。
「この森のように、内から外へ出さないための結界……というのも存在する」
そう言ってザクーは一歩後ろへ下がった。ランが剣を突き出して一歩踏み出したからだ。
切っ先からの距離を一定に保ったまま、ザクーは張り付いた笑みを消そうとはしなかった。エノリアのほうへ顔を向ける。
「ほら、彼女にはわかった」
エノリアは驚きを隠せないでいた。それを内へ内へ収めるようにしていたが、確認するような視線がランへ向かう。
「ラン……」
「言ってないのか、ラン」
大仰に驚きをこめて、ザクーはそう言う。
「君が、何者なのか!
早く言ってやれよ。
自分がいつか、『君を殺す側に回るかもしれません』って」
「黙れ、ザクー!」
ひどく不思議な光景だった。同じ顔がにらみ合いながら、かたや嘲笑、かたや焦燥を浮かべていた。
「彼女はうすうす勘付いているさ。お前がどんな人間なのか。鮮やかな美しい緑色の瞳……シャイマルーク王家の直系にだってそうそう生まれやしない。育ての親はあの大魔術師だって? そして、剣の柄にある赤い石」
ランは荒く息を繰り返し、エノリアを振り返った。エノリアの喉の動きをランは見てしまった。
「気づいているんだろ」
ザクーの言葉は止めだ。ランはザクーに剣を向けてはいたが、意識をエノリアに向けてしまっていた。
「……平気よ、私は」
何が平気だと言うのだろう? ランはエノリアを見つめていたが、エノリアは首を振って見せた。
「触れられたくないことなら、聞きたくないもの」
「ラン、君が要らないなら俺が貰う。君の証も、光《リア》も」
耳元でその声は大きく響いた。ランが背筋を伸ばすと、ザクーの手が肩にかかる。彼は背後に立ち、その耳に囁いた。
「俺ならお前の代わりをやってやれる。血と証と肉さえあれば……出来る話だ……。お前はどうせ『器』でしかない。
かえって邪魔なんだ。『お前』は」
ザクーはそうやって言ってから、ランの荒々しい感情がこもった剣の一閃を避けるように跳躍した。体が空を飛び、ランの剣の切っ先が、決して届かない枝へ着地する。
自分の剣に振り回されるようにして、ランは体をふらつかせる。思わず支えようと手を出したエノリアの腕から離れて、上から見下ろすザクーへ顔を上げた。
「お前は何しに来たんだ」
「予告もせずに奪うのは卑怯だろ?」
にやりと笑うザクーに、ランは疲れたような目を向ける。
「知らないまま奪われるのも可愛そうな話だ」
唖然とするランの視線を受けて、彼はよく似た瞳を細めた。
「頂く。お前が持ってるもの、全てだ」
そう言って彼の体は闇へ溶け込むようにして消えてしまった。
その虚空を見つめるラン。今度は振り返るのが怖かった。
エノリアに、何を言えばいいのだろう?
「ラン」
ぴくりと手が震えた。振り返ると、金色の瞳が恐ろしいぐらいの静けさをもってこちらへ向けられている。
「エノリア」
「早く、行こう」
ふいっと瞳が反らされることがこんなに心苦しい。
背中を向けられて。
「エノリア!」
「私を殺して解決するなら、殺せばいいのよ?」
闇に溶け込みそうな背中、ランはそれを見つめていた。震える? 自分の両腕を抱きしめて、エノリアは何かをこらえるようにうつむいている。
「側にいて、そうしたいと思ったときにそうすればいい! ランの中の血がそうするのが一番だって言ってるんだったらそうすればいい! 何度も助けてくれてありがとうって、笑ってあげるわ。
恨み言一つも吐かずに、そう言って死んであげるわよ!」
エノリアはそう叫んで、最後にぽつりと呟く。
「シャイマルークの王族でしょ? ラン。
確信があったわけじゃないけど、そう思ってた。その、赤い石を見たときから……」
吐き出すような声に、ランは一歩踏み出した。その背中を前に、自分が何をしたいのか。
気丈な声に混じる泣き声が、ランを動かす。松明を手放した。湿り気を帯びた地面と草、ランから途切れた火《ベイタ》がその明りをかき消す。
闇が落ちる。厚い木々の枝の合間から、月光が落ちる。
ひどく、静かだ。静けさの中に重なる空気の重さをランは感じていた。自分の中にある重みが、空気に混じりこんでしまったようだ。
エノリアが我に返ったように顔を上げ、息を吐き出す。そこに含まれる感情に、ランの思いが揺り動かされる。
ランはこらえるように眉を寄せた。
エノリアの感情の動きが、自分の中の混乱を弱さにする。毅然としていなければと思った。だから、エノリアにはこれ以上何も言ってほしくない。
息を吐く音さえ、心を揺らす。
ランは首を振った。その仕種に、エノリアが心配そうな声を発する。
「ラ……」
「……思ってるとおりだよ」
囁くようにランはそう呟いてしまった。
明るい月。顔を上げれば、エノリアの気遣うような表情がむけられている。先ほどまで怒っていたのに、自分の感情の動きを察して、今度は心配してくれている。
優しいなと思った。
だけど、今は、怒らせておきたい。怒っていてほしい。心配などされたくない。
自分のわがままだろうが。
「俺はあの王家の血を引いてる。緑の目だってこの赤い石だって、その証だ。
だけど、俺は捨てたんだ。
全て捨てたんだ。王家の血を引く自分も、本当の名前も。
自分の血にしたがって、お前を殺そうなんて思ってない。
俺は自分の意志にしか従わない。お前と一緒にここまで来たのだって、その先も一緒に行こうとしているのだって、俺の意志だ。セアラに行けって言われたからじゃない。言われなくたって、そうしていた。
そうしたいと思ったからだ」
「……私を守ったって、いいことないよ」
「俺がそうしたいんだから、そうしてる」
「ランにも目的があるからでしょ? 捨てたって言っても……その赤い石だけは捨てられない?」
強い光と声の静けさ。不釣合いなその二つに、ランの手から力が抜ける。
「ランにだって目的がある。私と一緒に行く目的が。そう言ってくれたほうが楽よ」
「エノリア」
「分かってるつもり。ランが私を一生懸命守ってくれてるってことは。だから、感謝してるの……。本当に感謝してるのよ、ラン」
だけど、とエノリアは視線を地面へ落とした。
「素直にそう思えないの。私が二人目だから? って思うの。
こんな風に思いたくないのに、私がこの……いろんなことが起こってる鍵を握ってるみたい……ううん、握ってるから、ランが側にいてくれて、こうやって守ってくれてるんだって思うのよ。
私って何? って」
月光が彼女の金色の瞳を映し出す。茶色い髪に少しだけ光が反射する。揺れる。
「馬鹿でしょ。そんなこと考えたって仕方ない。だって事実だから。
だけど、私は……二人目で特殊で、ずっとそれが付きまとって。
……素直になれない……」
「エノリア」
「……ごめん。大丈夫」
エノリアは地面に落ちている松明を拾って、ランに手渡した。
「急いで戻らないと」
「ああ」
「信じるわ、ラン……。取り乱してごめん」
自分に言い聞かせるようにしてそう言い、前を歩き出すエノリアを見ながら、ランは火《ベイ》を呼ぶ。あたりを明るく照らす光に目を細めて、ランは剣の柄に手を当てた。
これだけは何故か手放せない。捨てても戻ってきて、いつのまにかそばにある不思議な石だ。セアラが面白がって剣の柄にはめた。それから、持ち続けている。捨てようと思えば何度でも捨てられたはずだけど。
(捨てたと思っても、振り回されてるだけだ)
彼女が視界へ入っているうちに、ランは足を進める。
頼りない背中。だけど、どのときよりも頼りなく感じた。
『恋しいと、側にいたいと、抱きしめたいと思うことは? 笑顔を見るだけで、幸せになれる人は?』
恋しいと……思う。側にいたいと……思う。強く抱きしめたいとも思う。笑顔を見ればとても嬉しい、愛しい。
だけど、その思いが偽りなのかもしれないなら。
俺も、彼女の中の光《リア》しか見てないのかもしれない。
『器でしかない』
拳を握り締める。
この思いが、作られたものなら?
この赤い石を捨てられない。俺はこれを捨て切れていない。全てから逃げ切れない。まっさらの、ただのランになりきれない。
ただのランになれないのなら、この思いも偽りかもしれない。
……偽りなら、彼女への思いも偽り。
彼女を抱きしめたいと思う願いも、彼女を愛しいと思う思いも、偽りなら。彼女の光《リア》しか見ていない結果なら?
それはエノリアを傷つけるだけだ。
(傷つけたくない)
『守る側に回るのだと決心したのなら、その手を絶対に離してはいけません。決して、大切な人を離してはいけませんよ』
そう、ただ、守りたい。
ランは首を振った。それ以外の言葉を振り払うように。
それだけは本当の気持ちだと確信していた。
ランは彼女の隣に駆け寄る。
「急いで戻る」
固い響きの声でそう告げて、ランは走り出した。今度は彼女の手を握り締めることもなく。彼女が後ろをついて歩いてくることを感じながら、どう声をかけていいのかも分からずに。
|
|
| |
|