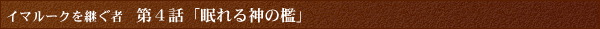 |
| |
|
◇
|
| |
背後に彼女の気配を感じて。目の前に広がる血の海に瞳を向けて、頭に熱い空気が降り注いでいるようだ。
背中に頼りなく当てられた彼女の指の感触だけが、自分の意識の中ではっきりと捕らえられていた。
守りたい。
その意識とは裏腹に、自分の呼吸の不確かさも感じていた。
なんて頼りないのだろう。
どうして、彼のように守れないのだろう。
守ろうとした背中の後ろで、彼女は別の男の名を呼ぶ。
その名を、自分の後ろから呼ぶ。
その声を聞くたびに、拳に力が入る。こんなところで倒れるわけにはいかない。
だが視界が揺れた。自分の右手に地面の石が食い込む。落ちる影が誰のものか、考えなくともわかっていた。
向けられた同情の緑色の光に、吐き気さえ覚える。
いつだって僕は後ろだ。
いつだって、僕は君の後に続く者だ。
あのとき、
あの日からそうだ。
ちゃんと謝れなかった僕は、君より弱い。
そんなこと、ずっと……ずっと感じてたんだ。
『謝れなくてごめんなさい』
脳裏から離れない、言えなかった言葉がその証拠だ。
『一緒にまた、行こうな』
泣きそうな顔をして、笑顔を向けられたときから、自分が君の跡に続くものでしかないと自覚していた。
僕は、ずっと君になりたかった……。
僕は願う。誰よりも、強く。
ただ、それだけで狂いだすことを知りながら。
『命をかけたんだぞ!』
わかってる。
だけど、僕は愛しているから。
愛しているから。
壊すぐらいなら、
先に、自分が壊れてしまう方がいいんだ。
ふと顔に当たる暖かな気を感じて、ミラールは目を開けた。
目に入ったのは燃える火がうごめいている様子。自らが産む上昇気流に揺れる火の向こう側に疲れたように座り込んだスーライとコウトール。エノリアの姿は見えず、視線を上に向けるとこちらを覗き込む漆黒の瞳が目に入った。
安堵がもれそうな瞳に、ミラールは目を細めた。
暖かい……。
「カーラ……」
「大丈夫? ミラール」
「僕は……」
状況を判断しようと記憶を探り、そして、目をつぶる前に目に入った情景を思い出した。力が抜けて、そして、大きく息をつく。
(倒れた。守れなかった……)
ぼうっとそのことを考えている彼の頬に、白くて長い指が伸ばされて、そっと触れた。
「あんたは相変わらず、苦しむのが好きだね」
苦笑に慈愛が混じって、柔らかな空気がミラールに触れる。あまりの心地よさに、ミラールは目を閉じる。
「何故、泣くの?」
カーラの言葉をミラールは目をつぶったまま聞いていた。自分の頭をカーラが膝に乗せてくれていることに気づいたが、暖かさと心地よさに甘えることにする。
「泣いてる? 僕が」
カーラはうなずいたようだ。空気がそのように動いた。ミラールの顔を上から覗き込んでいるような形だったので、うなずいた拍子に髪がはらりと落ちてミラールの頬をくすぐった。
「泣いているよ……」
彼の頬に触れていた彼女の白い指が、ミラールを慈しむように優しくその曲線を撫でた。甘い香りだ。ミラールはその香りを吸い込んだ。ゆっくりと頭が覚醒する。
「起きたい……」
ミラールがそう呟くと、カーラは彼の体を支えてその場に起き上がらせた。まだふらつくのに耐えていると、カーラは彼の後ろにある木の幹に持たれかけさせる。
用意していたのか、側に置いていた器に入った水をミラールに進めた。ミラールはそれで喉を潤しながら、この火の回りにいる人間を確かめる。
スーライ、コウトール。そして、離れたところにユセ。
ランとエノリアの姿が見えない。
「ランとエノリアは?」
「ランは回りに結界を張るんだって出て行ったよ。エノリアちゃんは……さて、ついていったか」
「そう……」
ミラールは器をカーラに返す。おかわりを聞かれて首を振った。
「大丈夫。気分、良くなったから」
「うん、さっきよりは顔色が良くなったね。安心したよ」
「ありがとう」
カーラは無言で器を脇に置くと、膝を折ってミラールの隣に落ち着く。ミラールは茶色い瞳で、炎を見つめていた。
ときどき枝のはぜる音がする。その音に反して森の静けさを感じた。揺れる炎を見つめていると、いろんなことが頭を巡った。
いくつもの言葉が、なんの連なりもなく浮かんでは消える。その言葉達を論理だてることをせずに、ただ言いたいがままにさせていた。
その混濁が心地よかった。
「あのさ、ミラール」
「ん?」
その混濁はカーラが言葉をかけることでゆっくりと消えていく。
ミラールが顔を向けると、カーラは気まずそうに両手の指を組み合わせ、何度か右の人差し指で左手の甲を叩いていた。
そして、何度か叩いて、思い切ったように顔を上げる。
「ミラール……あ……」
ミラールの静かな瞳がカーラを見つめていた。
「あの、体、大丈夫?」
ミラールは静かに微笑んだ。
微笑むだけで、何も言わない。
「カーラ……いつから、こんな風に旅を?」
カーラが薄い肩掛けをかけようとするのを断りながら、聞いてみた。カーラは柔らかく断られた肩掛けを自分の膝に置きながら、微笑む。
「あんたと会って、しばらくしてからかな……。
あの店、抜け出してね。追いかけられてるところ、コウトールに助けられて」
カーラがふとコウトールの方に視線をやった。彼は、スーライを隣に楽器の手入れなどしている。
「それで一緒に旅をしてるのさ」
「そうなんだ」
ミラールの相槌に、カーラはにっこりと笑った。ミラールはふと昼間のことを思い出す。今のコウトールの姿と、昼間のコウトールの姿はまるで別人のようだ。
「すごい、使い手だよね」
「そうかい? あんたの連れほどじゃないさ」
「そうかな」
ミラールは膝を抱きかかえて炎越しにコウトールの姿を見つめた。コウトールとランが手合わせをすれば、どちらが勝つのだろうとふと思う。ミラールはランが負けた姿を見たことがない……。その姿は思いつかない。だけど、コウトールも、そしてスーライも並みの使い手ではない。
だからこそ、聞いてみたくなった。
「……どうして、カーラは僕達と一緒に行こうだなんて思ったのかな」
「そりゃ、そのほうが楽だと思ったからね」
「少なくとも」
カーラの答えに素直に納得できないミラールは、ふとカーラの腕に目をやる。白い布が巻かれていた。
「そんな傷を作ることはなかったと思うよ。コウトールさんとスーライさんがいたら」
「ラン君がやっつけた魔物、私達じゃ無理だったさ」
「……あんな魔物がいるなんて知ってたの?」
「いや、それは予想できるはずが……」
カーラはそう言って、大きく息をつく。ミラールはにこにこして彼女の表情を見つめていた。
「冷静に考えればさ、カーラ。僕の腕もランの腕も知らなかった君が、僕らと一緒に行こうだなんて、おかしいよね」
ミラールの言葉に、カーラは大きく息をついた。照れくさそうに顔を両手で覆い、そして、キッとミラールを冗談交じりに睨みつける。
「……本当にわかってるんだか、それともそれが人から話を聞く手なのか、あんたは本当によくわからないね」
「この笑顔、便利なんだ」
ミラールはくすりと笑った。
「後ろめたいことがあったり、いいにくいことがあったりすると、どうも居心地が悪くなるみたいだね」
「そんな優しく微笑まれたら、嘘なんかつけないね」
「……でも、本当に言えない事には通じないんだよ」
ミラールは膝に頭を乗せて、カーラを覗き込んだ。
「言いたくないことや言えないこと、そんな意志の強さには通じないんだ」
カーラは固まったようにミラールを見つめる。茶色の明るい瞳は深くて、そして、どこか哀しそうだと思った。
「……言いたい事、あるんでしょ。カーラ。僕に」
「ただ、心配だったんだよ。私が、ミラールを」
ため息混じりに、そして、観念したようにそう呟いて、カーラは体の力を抜いた。
「つらそうな顔してるからさ」
「……そうかな」
「私は、あんたの小さいころ知ってるからね。あのときの天真爛漫な笑みとは違うよ」
「そりゃ、僕だって成長するよ」
「そういう笑顔じゃないさ。……何か、心配なんだ」
カーラの言葉に、ミラールは微笑んだ。
微笑んで、そして、そのままカーラを見つめる。カーラは上目遣いにミラールを見つめた。そっと首をかしげる。
「……言わない?」
「言えない」
ミラールは微笑んだ。拒絶するために意志を編みこんだ笑顔が出来るようになったのはいつのころからだろう。
カーラは髪をかきあげながら、遠い目をしつつ呟いた。
「あの子のことが好きなんだ?」
そう呟いてからカーラは呟いた言葉に彼女自身が驚いているようだった。そこまで踏み込むつもりはなかったのだが……。ミラールはカーラのほうに視線を移さず、ゆっくりと焚き火の炎を見つめる。
カーラは恐る恐る彼の表情を確認した。笑顔は消えていたが、代わりに覆ったのは無表情。
そして、それは緩やかに静けさを含んで、言葉を落とした。
「わからない」
「ミラール……」
「わからないな……。僕は一体どうしたくて、ここに居るんだろう」
消え入るような声で呟いて、ミラールは膝を抱えた。そして、目をつぶる。
カーラは黙って彼に寄り添っていた。
「カーラたちはどこまで行くの?」
「一応ノウレルまでね」
「……じゃあ、そこでお別れだね」
カーラはその言葉に戸惑った。こちらを見ようとしないミラールの横顔。拒絶するような空気は、触れると痛いんではないかと思われた。静かに、それ以上の言葉を求めない。踏み込めない領域をミラールは作り出そうとしている。だが、カーラは力を振り絞るようにして、拳を握り締めた。思い切ってミラールのほうへ手を伸ばし、肩を勢いよく抱きよせる。
「カーラ?」
「一緒に来ないか、ミラール!
しがない旅芸人さ。だけど、楽しいことはたくさんある。
あんたなら、きっともっと楽しくやれる! 人にももっともっといろんなものを与えられる。
私にしてくれたように……」
ミラールの頭にカーラは唇を寄せる。小さな子供をあやすように、頬を寄せた。
「……どうしてそんなに優しいの」
「ばかだねぇ。優しいのはあんただよ。
私はあんたに救われたんだ。あのどん底の世界で、さまよってた私に、あんたは声をかけてくれた」
「……なんて?」
「『綺麗な歌声ですね』って」
ミラールは彼女を見つめた。カーラは輝いた目をミラールに向ける。ミラールは首をかしげて聞き返すのが精一杯だ。同時に過去の記憶を手繰り寄せようとしていた。
「そうなの?」
「忘れているのかい。そうだね、無理もない。
ささいな言葉だった。
あんたはそのころ、私がいた娼館に、本当に時々だけど顔を出していって、音楽を紡いでくれたね。あんたは知らないかもしれないけど、どれだけあの音楽に癒されたことか。
まだ幼い顔の残る少年が、夜の帳が落ちる前にニコニコして現れるのを心待ちにしてたよ。
あんたの調べにつられるように、思わず歌っちまった私の声を聞いて、あんたは楽器を奏でるのをやめてしまった。
あのときはハラハラしたね。下手な歌を歌うなって怒鳴られるのかって」
「……あ、ああ……」
「ふふ。思わず構えた私に、あんたはにこりと笑っていった。綺麗な歌声ですね。もっと、歌ってくれませんか?」
「そうだ。それから、カーラはいつも僕の演奏に歌をつけてくれた」
「あんたがふつりと来なくなってね。それからすぐに私はあの娼館を逃げ出したんだ。追手は来たが、途中助けられてね。コウトールに」
カーラは遠い目をした。
「それから、歌手として歌い始めたんだよ」
にっこりと微笑むカーラの前で、ミラールは熱に浮かされるような顔をしていた。
「……そんなことで」
「そんなことだって、大切なこと。
あんたは私を助けてくれた」
カーラはミラールの頭を抱きしめた。
「助けてくれたんだよ」
ミラールは彼女の柔らかさを感じていた。
そういえば、誰かに抱きしめられるなんて、ずっとなかった。
暖かい。
自分を包み込もうとする優しさが、心地よい。
「……一緒においでか……」
ミラールは呟いて、目をつぶった。
何度も何度も、僕には違う道が用意されている。何度も、楽になりなさいと言われていると感じていた。
ミラールは炎の揺れ見つめていた。
「少し、待ってよ。カーラ」
カーラの体温に眠気を誘われたミラールは、かすれる声でそう呟いた。
「ドゥアーラで確かめたいことがあるんだ……その後でいいかな。返事」
「いいよ。私達もノウレルで稼いだ後、ドゥアーラまで行くよ」
「……カーラ」
「何」
「ありがとう……」
ランはコウトールとスーライに火をまかせ、少し離れたところで気配を探っていた。松明であたりを照らし歩きながら、大地に刻印をしていく。力を少しずつ落としながら、丹念に結界を張っていった。彼には珍しい念の入れようだった。
時折、足を止めて松明に手をかざした。火《ベイ》を持続させながら、またランは足を進めようとした。
「ラン」
後ろで草がかさりと動いたのと同時に、かけられたエノリアの声にランは振り向いた。
「何?」
「少し、休んだら?」
心配そうなエノリアの顔に、ランはかすかに笑ってみせる。
「平気だ」
「……平気そうじゃないわよ」
「心配しすぎ」
低く抑揚のない声でそう呟いてから、ランは再び歩き出す。それに従うようにエノリアが後を追った。
「だって、ラン……」
エノリアが自分の動揺を察しているのには気づいていた。だが、あまり触れられたくなくてランはその場に立ち止まる。
「……そっちこそ、どうしたんだよ?」
「え?」
「何か、心配事でもあるのか?」
「どうして?」
ランは再び歩みだす。エノリアも歩みを合わせる。
「やたらと側に居たがるなって、思って」
「何よそれ」
怒気を含んだ言葉に、ランはようやく振り返った。
「自意識過剰、なんじゃないの?」
「ユセの言ったこと、気にしてるんだろ」
エノリアの言葉に、いつもならむきに言い返すランも今は少し違った。
「変なこと、考えるなよ」
「変なことって何」
「……変な、ことだよ」
エノリアの瞳はうつろがない。口にしたランのほうが少しひるんでいた。
「……考えないわよ……。……でも」
「でも?」
エノリアはその先を飲み込んでしまった。
「ときどき、いいかなって」
「……死にたいって?」
あまりにも直接的な言葉に、エノリアはかえって目を見開いた。ランはその瞳を覗き込む。
「死にたくなんかないわ」
「だったらいいんだ」
あっさりとそう言って、再びランは歩みだす。エノリアを待たない歩き方に、エノリアが小走りになって追いかけてくる気配を感じた。
「ラン、ミラールは、どこか悪いの?」
返したのは沈黙だった。拒絶に近い。だが、どこかに綻びが見えている沈黙だったから、エノリアはさらに言葉を繋いできた。
「前も、倒れたよね。メロサで!」
「……もともとそんなに丈夫じゃない。あいつは」
「でも、今まではそんなこと」
ランはしばらく黙っていたが、ぽつりと呟く。
「俺が持ってるのは火《ベイ》と大地《アル》だからあいつの風《ウィア》は探れない。だけど、ああいう人間を見たことはある」
「ああいう人間?」
「要素になんらかの変調をきたした人間。病気とはまた違うんだ。セアラはそれを一括りにして『呪い』って呼んでた」
「呪い?」
エノリアが聞くと、ランは近くの木の枝に手を伸ばした。葉を引っ張って離す。反動でかさかさと揺れる枝を、ランは凝視していた。
「カーディスのこと、聞いたんだろ。お前」
「うん……」
「カーディスもそうだった。……呪いじゃないけど、何かの魔術だったらしい。だから俺に命を……」
「何、それ」
「よくわからないけど。命が削られるとかなんとか」
「ちょっと待って、どういうものなの、それ?」
「さぁな。セアラには聞いたけど、教えてはくれなかった。俺には必要のない魔術だから。というより、高度で使いこなせないだろうってさ」
「ミラールがその呪いってのにかかってるって言うこと?」
「似てるって言ってるだけだ」
ランは揺れる枝をはっしと掴んで、力を込める。若木が折れる音がした。
「メロサで倒れたときは、疲れがたまってるんだろうって思ったけど。今回はどうかな……」
「ねぇ、誰かに見てもらったら? 魔術なら、魔術師に。風魔術師《ウィタ》なら街に1人や2人いるはずよ?」
その言葉に、ランは首を左右に振る。
「言っただろ。高度だって。言葉を知らないやつが、知るはずがないんだ。それにそうだって決まったわけじゃ」
「でも、そうかもしれないじゃない! 見てもらおうよ!」
エノリアの意気込みをそらすために、ランは深くため息をつく。
「……セアラから離れすぎたのかもな」
「……どういうこと?」
「あいつは自分の身に起こってること自覚してるよ。言おうとしないだけで」
「聞けばいいじゃない!」
「聞けるかよ。あいつが語りたくないことを、無理矢理聞けるか?」
いらだったようにランがそう言って、そして怒鳴ったことを恥じ入って彼女から視線をそらした。
「俺は、あんまり信頼されてないんだ」
「何、言って……馬鹿じゃないの?」
突然弱気になった発言に、エノリアが眉をひそめた。嫌悪ではない。ただ寂しさだけが漂った。ランはその空気を感じながら、ため息と同時に言葉を吐き出してしまった。
「この森……よく似ているんだよな……」
小さく呟いた声に、エノリアは視線で問い返してくる。ランはそれに答えることができない。次の言葉を話すことで、呟いた言葉をなかったことにしようとした。
「無茶、させてんのかな」
ランがそう呟いた。心配そうな顔でそう呟いて、黒髪を引っ張る。
「あいつ、辛くても辛いって言わないしな」
そうだった。あの時も。
あの、セアラにこっぴどくしかられた森の一件でも、黙って自分についてきた。寒くても寒いといわず、怖くても怖いと言わず。
ちょっとした冒険心を満たすために、禁じられた森へミラールを連れて行った。セアラに堅くとめられたけど、好奇心の方が勝って。途中で道に迷って、出られるかどうかわからない森を二人で徘徊した。
そのときもミラールは誘った自分に文句も言わず、付いてきてくれた。挙句の果てに、火の番を忘れてしまった自分の代わりに、焚き火をずっと見てくれていて。
セアラに怒られたときも、ずっと恥じ入っていた。
いつもミラールは自分に巻き込まれてばかりで……。
「今回もそうなんだろうか」
「戻る? シャイマルークに」
あっけらかんとした彼女の言葉に驚いて顔を上げると、彼女はくすっと笑う。
「うれしそう」
「だけど、お前、今度あそこに戻ったら」
「別に、私は戻らないわよ。あんた達だけで戻ったらいいじゃない」
エノリアはそう言って、微笑む。
「私一人で神殿へ行くわ」
「エノリア」
「あのね、ラン。私、あんたにたくさん守ってもらったわ。あんたもミラールも、ラスメイも傷ついて……。本当は私一人でしなくちゃならないことなのに」
晴れやかに、本当に晴れやかに微笑もうとしていた。ひとかけらでも不安を残さないように。
「ミラール、心配でしょ?」
「俺は、お前も心配だ」
真顔で、ランはそう呟く。微笑むエノリアの、微笑もうとするエノリアの努力が、分かってしまったから。
「でも、ラン。本当は貴方には関係ないことだから」
「お前、どうして平気でそんなこと言えるんだ?
もし、ここで別れたら
もう、あえなくなるかもしれない」
エノリアは少しだけ目を見開いた。彼女は驚いて、そして、自嘲するように笑う。
「……せいせいするでしょ?」
「本気で言ってるのか?」
思わず出た言葉には、彼女を怖がらせるぐらいの怒りがこもっていた。ランにもそれは自覚できた。怒る理由などないのに……。
怒りを振り払うようにランはエノリアから目をそらした。そして、なんとかやり過ごして、エノリアに目を戻すと、彼女の金色の瞳に翳りが落ちていた。
「馬鹿は私だわ。そんな問題じゃない……」
エノリアは瞳をそらして、周りを見渡すように視線をやる。その視線をこちらに定めさせたかった。
「エノリア」
名を呼ぶ。こちらを向いた金色の瞳には、少し前からずっと付きまとう不安が拭い去れることなく張り付いていた。美しい金色の光が、少しだけ曇っているようだ。
「俺さ……」
何を言えば彼女が安心するのか、考え込みかけたランの耳に、何かはじけるような音が聞こえた。それに反応するように顔を上げ、そして、エノリアの手首を掴んで自分に引き寄せる。
「ラン?」
「しっ」
彼女の肩を抱いたまま、周りに視線をやった。
微かな風を受けて揺れる木々。葉がこすれあう音さえ、しない。どこかを核にして広がる緊迫感に、ランは目を見開いた。
闇を見定める。
木々が深く落とす影が作る闇の引力を前に、心を落ち着かせる。
進化の速度の早い魔物たち。
魔物たち。
場。
(場、か)
光《リア》が場。
こちらを赤い顔をしながら見上げるエノリアを見下ろした。強烈な光《リア》がここにある。
「どうしたの」
「静かに」
身じろぎするエノリアに声をかけると、エノリアもようやくランの緊迫した雰囲気に気づいたのか黙り込み、そして周りを見渡していた。
エノリアが場を作るのか。
(まさか……)
ふわりと何か柔らかい光が凝らしたランの視線の先でひらめいた。
銀。
「……月の娘《イアル》?」
その言葉にエノリアもぴくりと反応する。
場を作る。
結界で閉じられた森。月の娘《イアル》がいるとしたら、ここは最高の場だ。月の娘《イアル》とエノリア。
「いるのか?」
この森に、彼女が。
そして、ザクーが?
オオガでのライラは、魔物を操ることができた。ザクーだってそうだった。いるなら、そういう魔物に理屈が通るか?
「エノリア、戻る……」
戻るぞと言いかけて、ランは彼女を抱きしめたまま、その場を飛びのいた。小さなエノリアの悲鳴と重なるように、自分達が立っていた場所に大きな力が落とされる。
「ラン!」
ぎりっと唇を噛み締めて、ランは彼女の手を握りなおした。
「走るぞ」
「えっ」
ランは木々の間を駆け出した。
付いてくる小さな足音に、ふとよぎる既視感に懐かしさを覚えながら、心臓だけは早鐘のように打っていた。
『ラン』
小さな声が耳を打った。
この森はよく似ている。だから、こんなことを思い出すのだろう。
セアラに止められながらも、忍び込んだあの森での一夜。
本当は怖かった。あのとき。
『僕は、怖くないからね』
暗い森を震える手を引っ張りながら歩いた。
『ランは平気?』
平気なんかじゃなかった。怖かった。
でもミラールが付いてきてくれてたから。
自分の勝手でミラールを傷つけちゃいけないと思ってたから、今のように走り抜けることができたんだ。
ついてくるエノリアの存在感。
(守らなくては)
強く心に決めたから。
『守る側に回るのだと決心したのなら、その手を絶対に離してはいけません。決して、大切な人を離してはいけませんよ』
ユセの言葉が頭に浮かんだ。
(そんなことあんたに言われなくたって)
彼女の手を握り締める手に、力を込めた。 |
|
| |
|