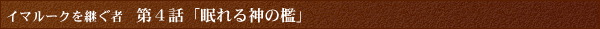 |
| |
| II 混迷の森 |
| |
チュノーラでのみ行われるこの『誕生祭』の形式はいたって単純である。3日にわたって行われる祭のほとんどが音楽と踊り、芝居といった華やかな催事で彩られる。少し昔までは『誕生祭』は、同じ日に一斉に行われていたのだが、昨今では近隣の町はそれぞれ時期をずらして行うようになっていた。ささやかな非日常を長く楽しむために……。今では本質は忘れさられ、人々が心から楽しむ日となっていた。
とは言うものの、『誕生祭』としての面影もかろうじて残っていた。それは祭り二日目に行われる。この日、町中の人々は分宮《アル》に足を運ぶ。耳に色とりどりの花を飾った巫女《アルデ》たちは人々を迎え入れ、大人には果実酒を子供には焼き菓子や果実酒を振舞う。ときにはナスカータの最高級のお茶を振舞うところもあった。それほど大きな町でなければ、街中の人々を呼んでささやかな宴が一日中続くのだ。3人がナダムにたどり着いたとき、その2日目であった。だから、次の日は3日目。そろそろ人の心は落ち着き、最後の余韻を楽しむ時期である。
「お前、ほんとうに買い物好きだな」
ランはほとんどため息混じりに、目の前を軽い足取りで行く、薄いベールをかぶった頭に向けて言った。上下に動いていたその頭が止まり、くるりと振り返る。ベールが軽く揺れた。
「別に好きなんじゃないわ。必要なものを買いに行くのに付き合ってって言っただけじゃない」
「ミラールでもいいじゃないか」
「あんたが一番暇そうだったからね」
ミラールはこれから旅に必要そうな物を揃えに行った。主に食料の類を。
エノリアはひとまず今頭にかぶっている薄いベールを買った。ラスメイと離れてから、髪の色が金色に近づいてきてしまっている。ラスメイから染料をもらってはいたが、慎重に使うためにいつもよりも量は少なめにしていたし、どうやらラスメイが近くにいるということが、色が長持ちする大きな要因だったらしい。
明るい茶色程度でとどまっていたが、金色の瞳とあわすと目立つ。薄いベールを女性がかぶるのは、ナスカータではあまり珍しいことではなかった。美しい淡い色合いを楽しむ人も多い。
エノリアはベールをいくつかかぶって、そのたびにランを振り返り意見を尋ねる。ランはその様子を少し複雑な気分で見ていた。
わざとらしく明るいような気がしたのだ。
「ああ」とか「似合う」とか答えていたら、エノリアは不機嫌な様子になってきた。どれでも似合うと思うから、そう答えていたのに……。
結局最初に気に入ったのを買って、帰ろうとしたランをエノリアは引き止める。もう一軒行きたいところがあるのだと。
ランはそんな彼女の後ろを歩きながら、周りに視線をはせる。こういう店を巡るのは嫌いではなかった。未だに宝飾類の店を見ると関心を示してしまう。それは、いつもセアラへの土産をその手の店で見繕っていたからではあるが。
小さな耳飾が目に入った。そういえば、エノリアはいつも付けていた耳飾をはずしてしまった。新しいのを付ける気も買う気もないのだろうか。金のことを心配しているのだろうか。彼女が持たされた路銀はあの月の娘《イアル》が用意したものだったな。
そう思いながら、ランはフュンランでのことを思い出した。あの月の娘《イアル》は今どうしているのだろう。自分と姿形の同じあの【魔物】の存在が脳裏に浮かんだ。最近は、いつもそのことが気になっている。
『殺されるべきお前が、何故生きている?』
黒い瞳でそう問いかけられた。
ランは無意識のうちに額に手をやる。
セアラに、何故自分を育てることになったのかを問いかけたことがある。セアラは微笑んだ。あのときほどの、美しくて柔らかくて優しくて、そして、とても切ない笑顔を見たことがない。だから、記憶は幼いときのものでも、鮮やかに残っている。
微笑んで、抱きしめてくれた。それだけだ。
何故、生きてる?
ランは突然心臓を叩かれたような気がした。眼を見開く。
何故、殺さないのですか。
エノリアを。エノリアを、何故殺さない?
(馬鹿らしい!)
貴方の血。貴方のその瞳。
赤い宝石が眼に入った。
貴方の、額の証。
『無駄だよ』
セアラの赤い瞳がゆがんだ。メロサで出会った幻影が、消えかけた記憶の中の言葉の先をつむいだ。本当にそういったんだろうか。セアラはそう言ったんだろうか……。
「ラン」
びくりとランは身体を震わす。視線を向けると、同じように驚いたような金色の瞳があった。自分の左腕に遠慮がちにかけられた右手。その指にはまっている赤い石の指輪。
右手でその手を握り締めかけて、やめた。
「どうしたの? ラン?」
心配した声音に、ランの意識は完全に戻った。美しい色の瞳をもう一度見て、首を振る。
「なんでもない」
ベールから見え隠れしている耳に視線を向けた。ふと、無意識にその耳に手を伸ばしていた。エノリアの身体が一瞬こわばって、ランもそれ以上手を伸ばすのをやめておろす。
「何?」
「いや、もう、付けないのか。あの耳飾」
彼女は視線を少しだけ動かす。そして、そのままの表情で呟いた。
「もう、いいの」
「そうか」
その声音に軽い拒否を感じて、ランは店先を見つめた。エノリアが明るい顔をして覗き込んでくる。
「なぁに? 買ってくれるの?」
「……あ、あぁ。別にいいよ。気に入ったの、あるのか?」
あっさりとした返答に、逆にエノリアは眼を丸くする。
「いいわよ」
「なんで? 気に入ったのないのか?」
「いいのっ。それよりも見て欲しいのあるのよ」
エノリアはまだ店先の方へ顔を向けているランの服のすそを引っ張ると、ぐいぐいと3軒先の店にひっぱっていく。そこは武器や防具といった類の置かれている店だった。
「私、剣をなくしちゃったのよね。ちょうどいいの欲しかったの」
「前に持ってたのと同じようなのがいいのか?」
「うん」
「軽さも、長さも?」
「そうね」
「それは無理だろ」
あっさりとしたランの答えに、店の中を覗き込んでいたエノリアは思わず振り返ってしまう。
ランはその少しだけ怒気の含まれた表情を、肩をすくめてそらそうとした。
「あれ、結構いい品だったからな」
「……シャイナから貰ったの」
シャイナという響きに、極力感情を排除した努力のあとが見られた。その努力の後が見られた時点で、彼女の努力は無駄になる。ランはそれを感じながら、知らないふりをした。
「特注だろ。同じ長さはあるかもしれないが、軽さはどうだろうな」
「でも、何か持ってないと」
ランは苦笑する。
「不安か」
「当たり前じゃない!」
苦笑を嘲笑と受け取ったエノリアが、噛み付くように言うと、ランは彼女のその表情を吟味するように見てうなずいた。
「そうだな。まぁ、俺も四六時中一緒に居るわけにもいかないしな……。ザクーがこっちの場所をまったく知らないという可能性は保障できないし」
といいながら、ランは店の中へ入っていく。
「剣を振り回させるようなことさせたくないけど」
エノリアの目の前を通り過ぎるとき、ランはそう呟いた。
「俺が斬られそう」
「誰がっ!」
そう叫んでからエノリアはふと眼を細めた。ザクーはこっちの場所を完全に把握している。全然目の前に現れないのは、まだシャイナの傷が癒えてないからか、それとも機会を狙っているのか。
自分の近くには常にランかミラールがいる。意識的に彼らがそうしてくれている。街には一応の守りがある。フュンラン城に入れたザクーに、この街の守りが効いているのかは謎だが。
自分の唇をぐいっとぬぐった。ザクーから受けたくちづけが、一体どんな作用を及ぼしているのかはわからない。あの瞬間を思い出すと未だに寒気がする。
相手が……相手の姿が違ったら、もっと割り切れたんだろうか?
ランと同じ姿のザクー。シャイナの願いが作り出した魔物……。
品々を真剣に見つめて、手にとって見るランの姿を見ながら、エノリアはため息を少しだけ落とす。
「エノリア、ちょっと」
ランに呼ばれて、エノリアは気持ちを切り替えて駆け寄る。
「お前さ、自分の選ぶんだろ?」
「ごめんごめん」
ランから受け取った剣は、今まで持っていたものよりも重さは多少重く、長さは多少短い。
「これぐらいだ。この長さでこれぐらい軽いのは。強さもまぁ、申し分ないと思う」
「そうなの」
今まで持っていたものの良さを実感した。抜き身をしげしげと見つめるエノリアに、ランは低い声で言う。
「選ぶけど、これは使って欲しくないけど」
いつもと違う声音と、言葉の響きにエノリアはその剣を持ったまま振り返る。
「あぶねっ」
「どういうこと?」
「……危なくなったら、まずは俺を呼べ。自分でどうにかするって考える前に、とにかく呼べよ。お前にこういうもん渡すと、ギリギリまで呼ばない気がするんだよな……」
「……ちゃんと呼ぶわよ」
「あんまり、俺が怪我するとかどうするとか考えるなよ。考えるだけ無駄だから」
「無駄って!」
「いいから、とにかく呼べよ。あのときみたいに」
あのとき?
エノリアは首をかしげた。
「どのとき?」
「フュンラン城でお前、必死に呼んだだろ。……俺のこと」
「あのときはっ」
エノリアはそう言いかけて、止まった。今更ながらに思い出した。ランの上に飛び降りてしまったこと。そして、そのまま抱きしめられたこと。ふと眼を上げると、同じように硬直したランと眼があった。
ランも同じように思い出しているのだろうか? あのあと、いろんなことが立て続けに起こって、ゆっくりと思い出すこともなかったけど。
そう改めて思うと微妙な空気が残ってしまう。こう考えるのは自分だけだろうかとエノリアは思った。あのとき、抱きしめられたとき。頭上で「無事で、よかった」という声を聞いたとき、自分は何かが繋がったような気がしたのだ。空気とか、時間とか、……想いとか。
(気のせい?)
そんなの、気のせいだ。というより、何考えてるんだろう? 自分は。振り払うようにエノリアは首を振った。
「あのとき、お前」
びっくりした。エノリアははじかれたように顔を上げる。ランの緑色の瞳は影が落ちていて、とても深い色合いになっていた。
ランの眼は綺麗だ。本人は否定するけど、光の差し込み方でいろんな色合いを見せる。
一番好きなのは、光が真っ直ぐに飛び込んで移す、鮮やかな新緑の色……。
「重かった」
「は?」
「……気が、する」
そう呟いて、ランはエノリアの手からそっと剣を抜きとった。
これでいいんだな。はい。金、払っておくぞ。はい、お願いします。
ランが目の前から店の奥に足を進める。その途端、エノリアはその場に座り込みたくなった。かろうじて彼女を支えていたのは、自尊心だったであろう。
(あほだわ)
軽く自分をののしって、エノリアはため息をついた。
「ばっかみたい」
小さく呟くと、行き場のない羞恥心が少しだけ収まった。もう一度呟いて完全に立ち直る。戻ってきたランに値段を聞きだし、別に構わないと言うランに、きちんと自分の財布から支払いをして、エノリアは店を後にした。
よくわからないといった顔をしているランを振り返って、もう一度呟く。
「ばっかみたい」
聞こえてなかったんだろう。ランが問いかけるような表情をした。その顔にエノリアはにっこりと微笑む。
「帰りましょ。ミラールが待ってるわ」
いつもかけないような優雅な声の響きに、ランが少し面食らったような顔をした。それがおかしくて、エノリアはにんまりと笑った。それでもう少しだけ気が晴れた。 |
|
| |
|