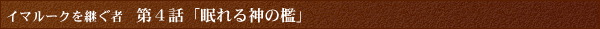 |
| |
|
◇
|
| |
エノリアは自分に割り振られた部屋の窓から見える路地を眺めていた。暗くなったというのに、各建物の軒に焚かれた煌煌とした灯火の間を行く人の流れは絶えない。時に肩を寄せ合い、手を繋いで大路へ向かう恋人の影。逆に流れるのは家路を急ぐような小さな子供たちの影。
何故か胸が締め付けられる。灯火はそこに生活というものを思い起こさせた。はじけるような笑い声がかすかに届く。
幸せそうな声。
ここに、不安の要素はない。
エノリアは金色の瞳を細めた。
そして、自分には遠い。
誰かと手を繋ぎ、ただその人のことだけを考える。
家族のことを考える。
目の前に広がる町並みは、そんな生活が溢れているんだろう。
そう思うと遠くて。
エノリアは目をもう少し遠くへはせる。
遠くなったと感じるようになったのはいつからだろう?
海際の町で私は生まれたと聞く。そして、すぐに山奥の町へ移り住んだ。ターラ山脈の麓、この祭のときさえ、穏やかな時の流れる人の少ない町だった。
小さなころは、町には少なかったが同じような年頃の子供と遊べた。だけど金色の瞳だけは隠せなくて、人たちが私の金色の瞳のことを口にするたびに、母は……。
『愛しているから』
エノリアは両腕を抱きしめた。
暗闇の中、何度も繰り返された。母の甲高い声。
毎日を母はどれだけの不安な思いを抱えてすごしたんだろう?
私の金色の瞳が話に出るたびに、母は強張った笑みを貼り付けた。
今はどうしているんだろう? 少しは解放されたんだろうか?
私がいなくなって、母はどうしてるんだろう?
『私にはずっとあなたは太陽の娘《リスタル》に見えるの』
シャイナの声が頭に響く。
いなくなってしまえば、みんな楽になれるんだろうか? ランもミラールも普通の生活に戻れるんだろうか?
魔物もいなくなるんだろうか。
『ここから先、永遠に太陽は二つ』
ユセの言葉がそれを引き止める。
違う。すがりついている。
私が死んでも、終わらない。
そう信じたいと思っていることが、いけないことのような気がした。
「私は……確かめないと」
ぽつりと呟いた。
確かめた先に覚悟が必要なら……。
エノリアは堅く目をつぶる。
怖いと思うことを、打ち消してしまいたい。もっと強くなりたい。もっと……もっと強く!
そのとき扉が物音を立てた。はっと我に返って、エノリアは振り返る。もう一度軽く扉は叩かれ、そして、よく知っている声が自分の名を呼んだ。
「何? ミラール? 入っていいわよ」
扉が開くと、その隙間から光が差し込む。そこで、やっと自分のいる部屋に一切の灯りがともっていない事に気づいた。
ミラールがひょっこりと顔を出した。
「エノリア?」
「あ、ここ」
ミラールの視線が寝台のほうを向いていたので、エノリアはそういいながらミラールのほうへ足を向けた。
「暗いから寝てるのかと思ったよ。何、してるの?」
「ううん、別に」
「ランもユセさんも帰ってこないみたいだから、僕たちだけでもご飯食べない?」
そういわれてエノリアは自分が空腹であることを思い出す。
「何やってるのかしらね」
微量に含まれた怒りの矛先は、ランに向けられていた。ミラールはくすりと笑う。
「ここの宿でも食事できるみたいだけど……」
「町に出かけちゃ駄目かな?」
首をかしげながらそう言うエノリアに、ミラールは優しく微笑んだ。
「少し、出ようか?」
「うんうん」
エノリアはにっこりと笑うと、近くにおいていた外套をひっぱった。ミラールは彼女が部屋から出るのを、扉を押さえながら待った。
いってらっしゃいませと言う宿の主人ににこやかに答えながら、エノリアの足取りは軽い。先ほどまでの不安を無理矢理、拭い去ってしまうように。ミラールは彼女の少し後ろを歩いた。
エノリアはすれ違う人、すれ違う人を見ながら歩いている。
「あ、ミラール。あそこにしよう」
指差した先に、食堂の看板。本当に宿から少し歩いたところにあった。窓からこぼれる光が、とても優しい。玄関へ入る階段は両脇を花で飾られていた。
「うん」
ミラールは静かに微笑んで、エノリアの足取りをゆっくりと辿った。店に入ると思ったよりも落ち着いた雰囲気だった。もちろん、外の雰囲気と比べてという意味である。喧騒と比べれば、幾組かの家族連れ、恋人達、仲間達の集った店の賑わいは落ち着いてきていると形容しても支障がないように思える。
二人が入ると愛想の良いおさげの少女が店奥の円卓へ案内する。すぐに注文をして二人は料理が来るまで、周りの様子へ視線をはせた。
「賑やか、だね」
エノリアがそう言って目を細める。そんな彼女の表情を見ながら、ミラールがポツリと言った。
「どうしたの」
「え」
エノリアが聞き返すと、ミラールは組み合わせた手に視線を落とした。
「うん、まぁ、元気ないなって」
「そうかな?」
「気のせいならいんだけどね」
茶色の瞳が柔らかく微笑んで、ミラールはそれ以上エノリアに何を聞くでもなく右手の人差し指で左手の甲を叩いていた。
エノリアがそれを見て、そして、そのまま言葉をつむぐ。
「ミラールって、両親に会いたい?」
ふと、ミラールの手の動きが止まった。しばしの沈黙に不安になってエノリアが顔を上げると、ミラールはいつもと変わらぬ表情で彼女の視線を受ける。
「随分、直接的に聞くんだね」
苦笑交じりの言葉にごまかされそうになる。
「うん、聞いてみたかったの」
「……会いたいのかな。そうだね……もう随分とそんなこと考えてなかったな」
遠い目をするミラールを、エノリアはじっと見つめている。
「会いたいとか会いたくないとかじゃなくて。会うことが僕の目標になってたから……。会いたくないって思ったら、ちょっと困るな」
「ちょっと困る?」
「目的が、なくなるから」
笑いながら、ミラールは決してエノリアと目をあわそうとはしなかった。
「僕もランも、セアラと……ニナに育てられたんだ。だから、二人が親だって言ってもいいかなって思うよ」
「ランの両親は」
「察しのいいエノリアさんのことだから、なんか予測してるんじゃないのかな」
軽くそう言って、ミラールは首をかしげた。
「ミラールは、ランの両親を知ってるのね?」
エノリアがそう聞いても、ミラールの表情は変わらない。エノリアが引き出したい答えはまったく違うものだった。だから、どう聞いていいのか迷った沈黙が続く。と、ふとミラールが口を開いた。
「結局、違うんだよね」
ふと落とした言葉だった。エノリアがその意味を問いただそうと顔を向けたときには、既になかったことにされるような小さな言葉だ。
思い切ってその意味を聞いてみようかとエノリアが口を開く。だが、その二人の間に影が落ちた。店の少女がにこにこしながら、湯気の出ている料理を二人の前に置く。
熱いうちに食べてくださいね。
二人の間にあった空気をがらりと変えてしまう明るい声で言って、少女は足取り軽く次の円卓へ足を進めた。新しく入った注文をにこやかに受ける。
それをエノリアが見つめているうちに、ミラールはさっさと目の前の料理をつつきはじめてしまった。一つわからないように息を落として、エノリアも目の前の料理に手をつける。
自分の料理をつつきながらエノリアは、ラスメイとの別れ際に、彼女からささやかれた言葉を思い出していた。
『ミラールが心配だ』と。
いつになく暗い瞳で、そして、何度も逡巡した挙句の台詞であった。エノリアに伝えるべきか、そうすることでエノリアに心労をかけないか。それを考えていたんだろうなと、エノリアは思い返した。
ラスメイが傍からいなくなって、そう日にちは経っていないのに、彼女と旅をした日々がとても懐かしく感じられた。それはやはり別れ際のラスメイの目が、もう遠くを見ていたからかもしれない。
エノリアは付け合せの果物を一つ取って、そのつややかな赤を見つめた。チュノーラ特産の小さな実・アコ。エノリアは幼いころこれをよく食べた。シャイマルークでもときどき食べることがあったが、チュノーラほど頻繁ではなかった。
小さな実を一口で口の中に入れる。皮は柔らかく、噛むと甘い汁が口の中に広がり、さわやかな芳香が鼻を抜けた。
これをラスメイにいっぱい食べさせてあげたかったな。香りのきつい果物は苦手そうだったけど、きっとこのアコなら気に入ってくれただろう。
「ラスメイ、どうしてるかなぁ……」
赤い実を見つめながら、エノリアはそう言葉を落とした。ふとミラールが視線を上げたのに気づいて、エノリアも顔をあげる。
「元気だよ、きっと……」
「泣いてないかしら」
ミラールはふと口元に笑みを浮かべた。
「心配?」
「そりゃ、もちろん」
ラスメイが感じていた不安。その最悪の予感が的中したとしたら、彼女は最愛の兄を失うことになる。
多分、あれは確信に近い。闇《ゼク》を持つ者が無意識に持っている予感があったからこそ、ラスメイはシャイマルークに引き返すことを選んだのだ。
「あの年で覚悟なんてさせたくないよね」
ミラールの呟きは俄かに賑やかになった店内の音にかき消されることなくエノリアに届く。
気づけば夕食を食べ終わり、お酒が入った客たちが歌を歌い始めていた。その荒削りながら見事な調和に、周りの人々があわせて手を叩き始めた。
それにミラールとエノリアは、視線をはせた。ぽつりと取り残されたような感覚に、エノリアは目を細める。
そのときふと、客の一人がミラールの腰にある笛に目を付けた。
「兄さん、楽師かい?」
「あ、ええ」
「ちょっと吹いてくれよ。景気のいいのをさ。ほら、こっちで」
「えっと、あの……」
腕をひっぱられたミラールはエノリアに視線を向ける。エノリアはにっこりと笑った。
「行ってきたら? 私も聞きたいな」
ミラールは穏やかに微笑み返すと、人々が輪を作り歌を歌っているところへ足を進めた。
歌を歌っていた人は、興味津々といった風にミラールを見つめ、ミラールはさすがに慣れているのか、物怖じもせずに進められた椅子へ座った。期待の篭った人々の視線の中で、愛用の笛に唇を付ける。
流れ出した曲は、思わず微笑んでしまうようなかわいらしい曲だった。人々は手拍子を始め、太鼓を持っていた人は楽しそうに合奏へ加わる。
やがて、人々が円卓を脇に寄せ、手を取り合って踊りだすのをエノリアはにこにこと見つめていた。
とても穏やかな流れがここちよい。不安がゆっくりとぬぐいさられていくのを心地よく感じながら、残っているお茶に口を寄せる。
と、くぃっと服のすそを引かれる感触に、意識は音楽からそちらへ向いてしまった。彼女のゆったりとした服のすその先を小さな手が握り締めていた。
エノリアを笑みで満たされた瞳で見つめる小さな少女がいる。
栗色の柔らかな曲線を描いた髪、そして、金色に近い茶色の大きな瞳。唇はエノリアに何かを話しかけたそうに動いていた。
こんなところに少女が一人。少し不審に思ったが、この店の客の子供だろうと思い、好奇心にあふれた目に微笑み返した。
「どうしたの、お嬢ちゃん?」
「おねーちゃんのお名前はなんていうの?」
高い声で少女は聞く。
「エノリアというのよ?」
それを聞いて少女は、にっこりと笑った。ふくふくとした手を上げて、エノリアを指し、その指を自分に返す。
「私と一緒。私もエノリアっていうの」
「そうなの」
微笑むと、小さなエノリアははむかむように笑った。
「おねーちゃん、とっても綺麗な目をしてるから、話しかけちゃった。お邪魔してごめんね」
「いいのよ。エノリア……ちゃん。エノリアちゃんはこの町の子なの?」
「ううん。もっとずっと向こうの、海の近くの町から来たの。お父さんがお仕事で、この町に来てるの。それについてきたんだよ」
「そう、お父さんはこの店にいるの?」
「うん」
大きく首を振る姿がとても愛らしくて、エノリアはその髪をそっと撫でた。
「お父さんのところに戻らないと、心配しない?」
「そうだね。んじゃあ、おねーちゃん、また会えるといいね。明日までこの町にいるの。お祭り、見るんだ」
「うん、じゃあね」
小さなエノリアはたたたっと小走りに店の出入り口に走っていった。そこにはちょうど店から出かけている男性の後姿が見えた。白髪交じりの後頭部。壮年を少し過ぎたぐらいの中背の男性だ。その後姿にくっついて、小さなエノリアはこちらを見て手を振った。
エノリアが手を振り返すと、ひときわ輝く笑顔が返ってくる。
小さなエノリアとその壮年の男性の後姿を見ながら、エノリアは頬杖をついていた。
自分の父の後姿に似ていると思った。背の高さはちょうどあれぐらい。だけど、白髪はないしもっとしっかりとした足取りで歩く人だった……。
お父さんか。
エノリアは目を細める。
父のことを思い出すと、とても柔らかな気分になる。あまり家にいない人だった。抱きしめてもらった記憶もほとんどない。
『すごいなぁエノリアは』
家の前の木に登っていたときにちょうど帰ってきた父は、私を見上げてそう言った。母に木登りをさんざんとめられていたときだったので、怒られるかと首を縮めた自分に、父はにっこりと笑ってそう言ったのだ。
そして、両手を差し伸べてくれた。
『でも、エノリア。危ないよ。心配だから降りておいで』
父は私を抱き上げて、木から下ろしてくれた。
『登るなとは言わないけど、お母さんに心配をかけたりしちゃ駄目だよ』
柔らかな声。
それでも私は木に登った。私が木に登っているときに、父が帰ってくることはなかったけど……。
それでも、登って待っていて、父が帰ってきてくれたら、また抱き上げてくれるのかなって。
『すごいなぁ』
って、ほめてくれるかなって。
目を伏せてエノリアは笑みを殺した。
そんな思いをより一層深めるかのように、ミラールの笛の音はいつのまにか懐かしい響きを帯びて、子守唄のような旋律を奏でていた。
『心配だから、降りておいで』
それは優しい父の面影に重なった。
その後、父と一緒に母に叱られたんだっけ? あんなところに昇るのをほめるなんてって。父は苦笑いしてたけど、その背中の後ろでずっと自分で謝る機会をうかがってた。そのころからもう母はいつも神経質に私の一挙手一投足に反応してた。
異常なほどに父に食いかかる母の姿。自分のために怒られる父の姿に、すごく苦しくなって。
でも母にごめんなさいって言えなくて……。
繰り返される母の言葉。
ごめんなさいと謝りたかった。
お父さんを怒らないで。
……違う。
謝りたかったのはもっと別のことだった。
私がこんな髪で、こんな目でなかったら。
もっとお母さんは普通に、暮らせたのに。優しい笑顔で、優しい言葉で、優しい時間だけをすごせたのに。
エノリアは胸を押さえた。
ようやく解放されたミラールが、上気した顔で戻ってきたとき、その顔をまじまじと見てしまった。
自分に優しく問いかける茶色の瞳が、とても温かくて、エノリアは思わず呟いていた。
「お父さんとお母さんに会えるといいね」
ミラールは驚いたようにその言葉を受け止め、そして、微かにエノリアから視線をそらしてうなずいた。 |
|
| |
|