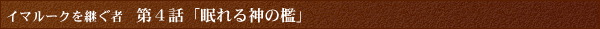 |
| |
|
◇
|
| |
酒場は喧騒で埋め尽くされていた。かろうじて窓際に残っていた席につく。卓上の木目を、ランは睨みつけていた。注文を取りにきた少女に果実酒を頼むユセの声に我に返り、ランもそれをもう一つと言って同じものを頼んだ。
「瓶で頼めばよかったですね」
「いや、俺はそんなに飲めないから」
「飲まないではなくて?」
「飲めないんだ」
強調して言葉を返すランに、ユセはにっこりと笑う。嫌味や皮肉とは無縁の笑顔だ。二人に、酒場の真ん中で陽気に踊る人の影が落ちた。ひらひらとゆれるような手の動きに、ユセは少しだけ目を向ける。
「あんたは、一体何者だ?」
ランが少女から果実酒がなみなみと注がれた酒杯を受け取り、自分の目の前においてから単刀直入に聞いた。ユセはその赤い液体に口をつける。そして、おもむろに置いてランの真剣な瞳と対峙した。
「歴史学者です」
「ただの、じゃないだろ」
ユセは微笑んではぐらかした。その微笑みは板についている。ずっとこうしてはぐらかしてきたのだろうと、ランは思った。
「あなたは、自分の素性を私に話せますか?」
ユセが逆に聞き返すと、ランは目を細めた。それを見たユセの反応で、ランは自分がはぐらかすのに失敗したことを悟る。あと数年、年を重ねれば目の前の男のようにはぐらかすことが上手くなるのだろうか?
ユセの指がすっと上げられ、ランの額を指す。
「ただ、私はその下にあったものが何かを知っている、家系なのです」
ランはユセを油断なく見ていた。真実と虚構を見分けるかのように。ユセの視線はランの左耳に向けられる。小さな赤い宝石を見て、ユセはささやいた。
「その耳飾のもう一対を誰が持っているのかもわかりますよ」
ランはその言葉を聞いて長く息を吐く。目の前の男の方が一枚も二枚も上手だ。そして、この笑顔が……目が嘘だとは思えない。たとえこれが嘘だとしても、自分では見抜くことはできない。
「……奴らはあんたの存在を知ってるのか」
「おそらく」
「……セアラも」
「そう、ですね」
「どうして、今頃。この時期にあんたが現れるんだ?」
緑色の瞳は鋭く光った。それをユセはむしろ頼もしく見ている。
「貴方たちが動かなかったら、私も永遠に動かなかったでしょう。貴方たちが動いたので、私も動くことにしたのです」
ランは目の前の酒に口につけた。半分ほどを一度に飲み込むと、ゆっくりと息を吐く。
「何か、食べるものを頼みましょうか」
ユセが手を上げて、くるくると動き回っている少女を呼んだ。ランに構わず2,3の料理を頼む。
少しだけ顔が赤くなっているランに、ユセは微笑んだ。
「本当に弱いんですね」
「あんたは、一体何を狙ってるんだ。俺たちにそういうことを教えて、『忘れられた神殿』とかいうところに誘導して」
「家系です。それが、私の使命ですから」
「使命? 使命だけで、こんなやっかいなことに首をつっこむのか?」
「そうですねぇ……。別にそこに私情がまったくないわけではないですよ。そう、なぜと問われれば……私には美しい妻がいます」
少女が頼んだ料理を3つ同時に持ってくる。一つは鶏肉を焼いて透明なソースがかかっているもの。もう一つは薄くのばして焼かれたパン。あとは、新鮮な果物を切って盛り付けたものだ。
ランは少し手を上げて、少女に感謝を示した。だが、その目はユセに向けられたままだ。
「そして、かわいい息子が一人」
突然始まった家族の話に、ランはいまいち彼の狙いが飲み込めないで居た。だが、話の腰を折るようなことはしなかった。黙って聞くことに決めているようだ。
「私の妻は、小さいころからよく知っている少女でした。いつも私のことを『兄』と呼んで慕ってくれていた。本当に、赤ん坊のころからよく知っている、恋愛対象にもならない身近な存在でした。
だけど、彼女は生まれたとき既に、私の妻になると決められていたのです。そして、私は彼女を妻に迎えた。それが、カイネ家の掟でしたからね」
ユセは酒を一気にあおる。そして、いまいちつかめないといったランの顔を見て笑った。
「やはり、瓶で頼みましょう」
ユセが再び少女を呼んで、新しい酒を追加注文している間、ランはユセの言葉の裏を一生懸命に考えていた。
「カイネは……イマルークが去った後、精霊語を残すことを許された家系です。だけど、我々の一族は響きというものを奪われました。強烈な呪いの力は、カイネの精霊語を紡ぐ血を封印しました。精霊語とともに託された真実もね。
だけど、『いつか来る時』に備えて、語れる者を生む必要があったのです。それには呪いを上回る濃い血が必要でした。その身に、強い風を宿しても、耐えることのできる肉体と血が……」
「あんたの妻って」
ランがそこで目を見開いた。ユセは微笑を崩さずにランを見る。目で肯定する。ランの言葉の先を感じて、そして、うなずいた。
少女が小さい瓶に入れた酒を持ってきて、ユセの前においた。ユセはさっそくそれを自分の酒杯に入れる。
「あなたは人を愛したことが?」
また言葉がかわり、ランはユセを見つめた。ユセはまだ半分満たされているランの酒杯にも、構わず酒を注いでいく。答えないランに次の言葉を重ねた。
「恋人は?」
「いない」
「だけど、好きな人はいるのでは? 恋しいと、側にいたいと、抱きしめたいと思うことは? 笑顔を見るだけで、幸せになれる人は?」
ユセはランの表情を観察しているようだ。ランはわずかながらに心の揺れを示した。ユセは息を吐く。これ以上問い詰めることをやめて、視線を和らげた。
「他の人を狂おしいほど愛しながらも、一緒にはなれない。これは悲劇だとおもいませんか?」
ふとランは、オオガで出会った巫女《アルデ》のことを思い出した。エノリアの激しい慟哭がよみがえる。エノーリアのことを思い出した。自分が彼女を恋人から引き離してしまったことを。
「そういう犠牲の元、私はここに存在するのです。だから、私は使命を果たして、カイネの血を早く解放したいのです。言ったでしょう? かわいい息子がいると。私が言葉をつむがねば、かわいい息子がこの荷を負うのです」
「だから、俺たちに近づいたって」
「……わかっているでしょう? 逃げたって、否定したって、あなたはこの混乱……そうですね、【混乱】と呼んでいいかもしれませんね。それからは逃げられないんです。彼女も……エノリアさんも、同じですよ。
生きている限りは。いえ、エノリアさんは、命を絶てば解放されるでしょう。ただ、次の少女に託されるだけなのですから」
「エノリアの命を絶つ?」
言い放った瞬間、心臓がドクリとうごめく。耐えるように眉をひそめた。頭に流れる血が一瞬だけ早くなった。酒のせいだろうか……。
「それは、望まないでしょう? もう二度と、彼女は彼女として生まれてくることはないのですから」
ユセが目を細めた。ランは緑色の瞳を強い光で輝かせている。
「エノリアは、一体何なんだ?」
「口にはできません。それは、貴方が見極めなければ」
「あんたはどこまで知ってるんだ」
ランの強い瞳。
「おそらく、全てを。だけどそれは、貴方にとっては真実ではないのです」
「力ずくで教えろって言ったら?」
「貴方にそれができますか?
いえ、たとえできたとしても、私は教えません。教えることは、道を一つにすることになる。だから、こんなに回りくどいことをしているのです。
貴方に教え、私にとって最善の方向に誘導することはできる。だけど、私にそれは許されていないのです。物理的には可能ですが、世界はそれを許さない。
だからこそ、私はただの『ユセ』として生まれました。
貴方が『ラン』と名づけられ、彼女が『エノリア』と名づけられたのと同じように、私の行動はその名に阻まれるのです」
「ユセ」
「ユは【目】。セは【器・受ける者】。ユセで【見る者】。私はその名を以って、必要以上の介入を許されていないのです。いえ、私自身が許していない……」
ランはユセの目を見ていた。その強い意志のある目を。そして、根負けしたように息を吐き出す。
「あなたは、この道を……どう捉えているのです?」
ユセの問いに、ランは前髪をかきあげた。視線は目の前に置かれた3つの皿に注がれる。せっかくの料理だが、ユセもランも手を付けていなかった。
「道か」
「そう、エノリアと共に旅をしているという道。その額の傷から目をそらしながら」
「そらしているわけじゃ……」
目の前にある残った果実酒を一気にあおると、ランは首を振った。
「エノリアが、自分の存在の意味を知りたがってる。だから、俺はそれに手を貸したいだけだ」
「それだけでは終わらないでしょう」
ユセはランの緑色の瞳を見る。突然ランの耳に、周りの客の歓声が響いた。心臓が叩かれる。それはその声か、それともこの目の前の男の不思議な目のせいか。
金色に近い目。
「貴方自身の役割は、何一つ終わってないのですよ。始まってもいない」
無言のランに、ユセは初めて厳しい光を浮かべた瞳を向けた。
「貴方は、彼女を殺す側にだって回れるんです」
ランはゆっくりと顔をおこした。ユセの目をまっすぐに見つめる緑色の目は、彼をにらみつけているようでもあった。その気迫を感じながら、ユセは言葉を続ける。
「巡るたびに殺す側に」
ユセは穏やかな口調でそう言うと、ランの反応を観察する。ランは思い出していた。エノリアに会ったとき、彼女を助けて館に戻ったあと、セアラが言った言葉を。
見捨てることはできたのだと。だけど、それができなかった。それは、ランがランである所以と。
ランは唇を噛み締める。
エノリアを殺す? 想像してランは思わず乾いた笑いを口に残した。血の味がするようだ。
エノリアを殺す。
自分が自分の血に従うなら、その道もあるだろう。自分の中に流れる血を認めるなら。
(馬鹿な、ことだ)
ランは首を振った。
彼女を殺したりなんかできない、自分は……。
(自分はエノリアを……)
「殺したりなんかしない」
ユセは微笑んだ。
「守る側に回るのだと決心したのなら、その手を絶対に離してはいけません」
酔いのせいか、ぬれたような光を浮かべるランの緑色の瞳は、ユセの唇を見つめていた。
「決して、大切な人を離してはいけませんよ」
そして、目を閉じる。ユセはそんなランの様子を見ながら、瓶に残った最後の酒を一気に注いだ。
ランは耳に残るざわめきが、いとしいと思えるのが、心地よかった。
人の気配。人の怒声。人の笑い声。物の落ちて壊れる音さえ。
そのとき、ランの耳にあの言葉が入ってくる。
ドゥエルーラ・トゥ・トエスタ!
人々はそう言って、手の中の杯を合わせた。ランはそちらを見やって、そして、ユセに視線を返す。
「あの言葉……」
「聞き覚えが?」
「さっき、あんたが言ってたじゃないか」
「それ以外にも聞き覚えがあるのでは?」
念を押すユセの様子を訝しがりながら、ランは記憶を探った。
(いつ?)
……ルーラ……。
眉を寄せる。
(あの、声は)
どこだ。
メロサ。
メロサの森だ。
「……子守唄」
……ルーラが消してくれるから……。
瞠目するランに反して、ユセは目を細めた。
「子守唄ですね」
「そうだ、子守唄。ルーラ……そうだ」
ランはまるで熱にでも浮かされてるようにそう呟く。目の前のユセが真剣な表情で問う。
「誰に歌ってもらった子守唄ですか?」
「ニナ……? 違う……。……エノーリア?」
「その子守唄は、ふたつの地方に残っています。このチュノーラと、あとはルスカ」
ランは前髪をくしゃっと握った。そして、手を下ろす。
「シャイマルークでは歌われない歌です」
「ドゥエルーラって、何だ?」
急に我に帰ったようなランの言葉に、ユセは重々しく口を開いた。
「忘れられた神の名前です。つまりは、調和神の」
「……ドゥエルーラか。トゥ・トエスタってのは」
「望みの言葉です。シスタ……【願い】よりも強い【願い】。
チュノーラの人々は、呪文のように唱えます。その意味も知らずに……そうやって、言葉だけは引き継がれているのです」
「調和神を望むっていう意味か。
調和神ってのは、どうして消えてしまったんだ?」
ランの言葉にユセは曖昧に微笑んだ。
消えそうな語尾は、ランが完全な回答をユセにもとめていないことを示していた。語れぬと言った自分に、彼は追い討ちをかけたりしない。
(優しい人だ)
そして、かわいそうな人だとも思う。だが、その魂の強さに希望さえも見える。
この時期に、彼らがここにたどり着いた。
この、声高に調和神の名が呼ばれ、空気はわずかにそこへの道程を示してくれる。
(運命だと?)
ユセは考え込むランの姿を視界の端に納めながら、騒ぎ出す人々の表情を見ていた。クルクルと踊る少女。それにあわせて、足を踏み鳴らす少年。
(上手く、動いている。流れが)
怖いくらいに順調に。導かれるかの様に。
どこまで意志が働いているのか。そして、これは誰の意志なのか。
太陽の娘、封印の名を冠した血、そして、扉である自分。
そして、あの青年……。
純粋が上に、包み隠さない瞳と空気を持った青年。優しく猛々しい風の中に隠されたあの……塊。
ユセは額を押さえた。
(願わくば、あなたたちが私の求める道を歩いてくれたらいいのだが)
この賑やかで、人の気があふれる世界をこのままにしておいてほしい。愚かで悲しいこともあるけど、それ以上に美しいことも優しいこともある世界を。
重ねられた人々の思いを、壊したくない。 |
|
| |
|