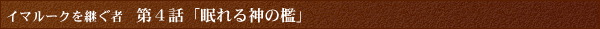 |
| |
|
◇
|
| |
チュノーラと言う国の名前から、人が連想するのは「活気」という言葉である。5つある国のうち、国王に権力のない国はここだけなのだ。王家は残っているが、そこに何の感慨もない。国王はチュノーラと言う名を持っている人物でしかなかった。
ただ、莫大な資金を持ち、絶大な影響力をもっている商人ではあった。そして、この国を運営して行く代表のうちの1人でもあった。ときどきその頂点に座すこともあったが、それは血統ではなく才覚のおかげである。無論、「チュノーラ」という名前を頂く誇りが、いくらかの刺激を与えていることを、本人達は自覚していたが。
シャイマルークと直接結ぶ道は、ノイド山脈を超えるものがあった。だがそこは盗賊と魔物の巣窟となっている。だから、チュノーラには「雇われ兵」という職業もなりたっていた。チュノーラからシャイマルークへ直接物を運ぶこの道は、危険だったが成功すれば財産を築く道でもあった。
チュノーラとナスカータはその大部分が高原、もしくは山や高台で構成されている。肥沃な土地をもったナスカータは、その高原を生かし果実などを特産物とした。また、独特の朝夕の温度差によって育まれたお茶は、最高級品として重宝されてもいた。だが、チュノーラはそれを期待する事ができなかった。その代わり、潮の関係で様々な魚が獲れる漁場を持ち、漁業が盛んであった。それを売り買いするうちに、商業が発達しはじめたのだ。水魔術師《ルシタ》の数が多いのも特徴である。それは、鮮度を保って魚を運ぶには彼らの能力が必要だったからだ。また、魚介類を加工する技術も高い。
だから、大きな町の大部分が海際に存在する。そのためにフュンランからチュノーラへ向かう大きな道は、ゆっくりと海へ向かっていた。
水平線が見えてきたら、チュノーラへ近づいたと言う印。そして、3人となった旅の仲間の目の前にも、その風景は広がっていた。
「海か」
緑色の目を細めて、馬上でランは呟いた。
「ラン、海は初めて?」
エノリアが聞くと、ランは首を振る。
「初めてではないけど、まぁ、初めてみたいなもんか。2回目だ」
「へぇ」
簡単な相槌を打つエノリアの視線の先で、ランは目を細めた。
「カーディスと来たな……」
遠い目をするラン。その目に浮んだ感情をエノリアは計りかねたが、少なくとも『痛み』だけではないようだった。
エノリアは比較的高く明るい声で、ミラールを振りかえる。
「ミラールは?」
「僕? 僕にも珍しいよ」
ミラールはそう言いながら、水平線に目を馳せる。
「フュンランよりこっちに来るのは初めてだから……。でも、フュンランの国の端まで行けば見れるからね。見たことはあるけど、チュノーラの海は……初めてだね」
そう言ってミラールも目の前の景色に食い入る様に見つめている。
エノリアは思いっきり深呼吸をした。
「私は4年ぶりねぇ。シャイマルークに連れて行かれるときの海の色、すごく覚えてる」
曇った瞳を二人は心配そうに振りかえった。だが、彼女は微笑む。そして、気持ちを切り替えるかのように両腕を上げた。
「今日はとっても綺麗だわ!」
空と海の境目がくっきりと現れていた。あの境目の向こうに何があるのか、知ろうとした者はいたが戻ってくる者はいなかったという。
この世の果てだとも言う。
ランは、エノリアの声に反応して、興奮したように鼻をならす愛馬・ラルディの首をさすった。
「ああ」
ようやく気づいたとでも言いたそうに、ランが声を上げた。
「綺麗な、青だな」
「ねぇ、エノリア」
ミラールがいつもと同じような口調で語りかける。
「何?」
「ドゥアーラって町を知ってる?」
「ドゥアーラ……」
エノリアの驚いたような響きに、ミラールが興味を示す。
「エノリア?」
「そうね、知っているわ」
微量の響きの揺れに気づいて、ランが視線を上げた。
「小さな町よ。山の麓の小さな町……」
思い出すような視線は、懐かしさよりも苦しさが混じっている。
「私が育った町よ」
思いを馳せるその視線をミラールは追って、海の青さに辿りついた。
「そう……」
しばらく時間を置いて、ランが足を動かした。
「行くぞ。カイネが待ってるだろ」
チュノーラという国に入り、1番最初に訪れる事の出来る町の名は、ナダム。その町で1番大きな宿を探せというのが、ユセ=ダルト=カイネの最初の指示だった。
町に入る前から、賑々しい雰囲気が微量の風に乗ってきていた。その理由を彼らは徐々に知ることになる。色だ。町はいろんな色で飾られていた。
道路を挟んで向かい合う家同士を、赤、黄、青、緑といった色の旗の垂れ下がった綱がつなげていた。それが幾重にも張り巡らされていた。それをぽかんと口を開けて見上げるランの耳を劈くほどの楽器の音が鳴り響く。ホーンを高々と吹いて、旅芸人が人を呼び込む。それに歓声をあげてついていく子供たち。
大通りを歩く人々は、みなが口々に大きな声で会話を楽しんでいる。
あまりにもにぎやかな音の流出に、ミラールが耐え切れないように眉をしかめた。
これが、チュノーラだろうかと、ランは微量の困惑を混ぜた心境でつぶやく。もしも一年中この騒ぎならば、住人の気力に感心する。
「ああ、そうか。誕生祭ね」
その賑わいを、驚きながらもランとミラールほどは衝撃を受けてないような顔をして通り過ぎていたエノリアが、そう言って二人へ目を向ける。
「祭?」
「そう。チュノーラだけだと思うんだけど、その……分宮《アル》の巫女《アルデ》の誕生日にお祭りをするのよ。いつしか、それは一年に一度だけ行われるってことになったの。昔に飢饉かなんかが起こってからだったじゃないかしら。
だから、誕生祭って言われてるわ。そうかぁ、もうそんな時期なのね」
エノリアが目を細め、色とりどりの旗を見上げた。
「ここまでにぎやかなのは初めて見た」
「こんなのなの?」
ミラールが右手で右耳を覆った。ちょうどそちらに居た旅芸人が彼に向けてホーンを吹き鳴らしたからだ。
「シャイマルークで言うと、王や娘たちの誕生日みたいなもんか?」
ランがそう聞いた。王と王妃、また、宮の娘たちの合わせて5人の誕生日には、こうやって祭りが行われた。今は4人である。現在の王に王妃がいないからだ。
「でも、音楽会が開かれたりぐらいだったろ? 宮に行ったりとはしたけど……。王と宮の最長老の大地の娘《アラル》の誕生日には、窓に花を飾ったりするぐらいで」
年に二度だ。ランも門に赤い花を飾ったことを思い出す。ダライアの誕生日に飾るのは、新緑の葉だったが……。ここまで町中がにぎわうということはなかった。
異常なほどの熱気だ。大体、本当に巫女《アルデ》の誕生日をまとめてお祝いするという主旨を、踏まえてなされている祭りなのかと、ランは思わず首を傾げてしまった。
「兄さん! 笛を吹いてくれよっ!」
ミラールの腰にさされた笛を指して、路上の人が声を上げた。ミラールはその人にあいまいに微笑んで、広場を指す。
「宿が決まったら」
彼が声を張り上げたが、それがその人物に届いたかどうかは謎だ。その人はにっこりと笑って、逆のほうへ走って言ってしまった。その先に別の音楽隊がいることを確認して、ミラールは苦笑する。
「僕、こんなにぎやかなところに合うような曲ができるかな」
「大丈夫よ、ミラール」
妙に確信を持ってエノリアがうなずいた。
「こんなにぎやかな音ばっかりじゃ、人は壊れちゃうわよ。だから、他の曲もすっごく聞きたくなると思うわ」
「主旨がわかってやってるのか? これ」
ランが不機嫌な響きでもって怒ったように言った。町の人は歓迎の印なのか、楽しそうに彼らに向けて声をかける。楽しんでいってくれよ若い人。ここの祭りは最高だ。いいときにきたな旅の人。ドゥエルーラ・トゥ・トエスタ!
ふとランが眉をひそめた。
「なんだ?」
違和感を感じて振り返る。何に引っかかったのか、自分でもわからない。だが、心の中に確かにざわめきが走った。
「ラン?」
「あー……。いや、なんでもない」
エノリアに手を振った。多分普通の声なら届かないだろうと、手振りを加えて見せた。
「ねぇ、とにかく宿を探さない? 大通り沿いにはなさそうだけど」
ミラールの言ももっともで、この先を見通しても、あまり宿らしき建物はない。無論、探せばあったかもしれないが、とにかくひとまずでいいからこの賑やかな大通りから離れたいという気に、3人ともがなった。
3人は大通りを外れる小道を選んで曲がった。その脇をしっかりと握りこぶしを握り締めた子供たちが歓声を上げて駆け抜けていく。ぶつかりそうになって、ランが無茶な体勢で体をよじった。子供たちは彼に笑い声と簡単な謝罪を軽やかに投げてそのまま大通りに消えていく。
「元気だねぇ」
ミラールがそうつぶやいて、笑った。思わず笑みが零れ落ちる。
「早く宿をさがそうぜ」
ランが前を向いてうんざりしたようにこぼした。
「ここまで賑やかだなぁ」
「まぁまぁ、すぐに慣れるわよ。これがチュノーラなんだから」
エノリアがあまりにも楽しそうに笑う。
「そうか、お前の生まれた国だったな」
「そうよ」
「道理で」
「あ」
エノリアが聞きとがめるように声をあげた。ランを覗き込む。
「今の、なんか悪意を感じた」
「気のせいだろ」
ランはふと笑って、そのまま視線を前に向けたままだ。納得いかない顔をするエノリアにミラールは微笑む。
「褒めたんだよ」
「え?」
「『君みたいな太陽のように明るく、私の心を照らし出す存在が生まれ育った国だから、こんなに賑やかで楽しい場所なのだろう』ってこと」
歌うように言葉をつむぐミラールに、エノリアがどう反応していいのか迷っている表情を向ける。笑いとばすべきか、それとも困るべきか、それとも照れるところなのか……無視をするか。
聞いていたランが、ぴしゃりとミラールに言葉をぶつけた。
「勝手に訳すな」
「そうでしょ」
「違う!」
「またまた……僕はランが言いにくいことをいってあげたんじゃないか」
「お前なぁ」
振り返ってランが右手の人差し指をミラールに突きつけた。その指先を見つめてから、ミラールはランへ顔を上げる。
「どうしたの?」
「……やめた。……お前さぁ、そういうところ、セアラに似てきた」
「そう? 需要があるから供給してるんだよ。ランも、セアラにからかわれないで寂しいんじゃないのかなぁって」
二人の間で立ち尽くしていたエノリアが、自分の態度を「無視をする」という方向に決めて、一軒の宿らしき建物を見つけて指差した。
「ほら、あの大きい建物、宿じゃない? あそこのことじゃない?」
3人はひとまず周りをぐるりとめぐり、その宿以上に大きい宿がないことを確かめた。ついで、エノリアが気のよさそうな人に声をかけて確認し、門の前で控えている宿で働いていると思われる少年に近づいた。宿の主人の身内か、それとも雇われている子供なのかわからなかったが、愛想の良い笑顔で3人を迎えた。
「いらっしゃいませ。3名様ですか?」
「ああ、カイネという人物が泊まっていると思うんだが」
ランの言葉に、少年はしばらく反芻するように目を泳がし、ああ、とつぶやいた。そして、にっこりと笑って3人の後ろを示す。
「思ったよりも早かったですね。大き目の部屋を取っておいてよかった」
3人は振り返る。ゆったりとした白い服に身を包み、穏やかに微笑んで長身の人物が立っていた。腕にたくさんの果物が入った包みを持って、笑みをそのまま門番をしていた少年へ向ける。
「お疲れ様」
そう言って色とりどりの果物から赤い実を取り出し少年に渡す。少年は素の笑顔を見せて喜んだ。そして、再び3人へ向き直る。
穏やかな笑みをエノリアは安心したように、そしてランは抜けきれぬ警戒心を持って迎えた。ミラールは目の前の人物に既知感を覚えていた。あったことのない人物のはずだったが……。
「中へ入りましょう。私のとっておいた部屋は寝室が3つついていますからね。問題ないでしょう?」
「ちょっとまった」
さっさと3人を促すユセの肩を掴んで、ランがとめる。ユセはまるで幼子に対する父親のような目でランに問いかけた。
「部屋は別にとる」
「大丈夫です、宿代はちゃんと割っていただきますよ」
にっこりと微笑むユセ。暖かい笑みではあるのだが、どこか有無を言わせぬ笑顔でもあった。
「それに、この時期に部屋を一つでも余分に取れるとは思いませんね。ねぇ、そうでしょう?」
ユセは門番をしていた少年に瞳を向けた。少年は赤い実を大切そうに懐に収めて、こくこくと頷く。
「うちもそうだけど、もう多分部屋はどっこにもないと思います」
「あなたたちが来ると思って、大きな部屋を取っておいたのです。遠慮なさらずに」
意外に強引だと感じながらも、ランはそれ以上強く言い返せなかった。また、自分たちのために部屋を取っていたという言葉も、彼を押しとどめた。これで断ればこの目の前の青年は困るのかもしれない。
ユセはにこにこと微笑んだまま、ランを見る。
「つもる話もあるでしょう?」
釈然としなかったが、ユセは何も構わず建物へ入っていった。少年が追い討ちをかけるように「さぁさぁ」と3人を促す。従業員が3人出てきて3人から馬の手綱を受け取った。
「誰? あの人は」
ミラールは初対面である。ランはその質問にも正確に答える自身がなかった。よく知らないというのが本音であった。その上、そのよく知らない人をエノリアはなぜか信用しており、疑いなく後へついていく。むしろ、楽しそうにも見えた。
そう思うとなぜか胸がむかむかとしてくる。ランは唇をへの字に曲げながら、ミラールへできるだけ今の心情を表さないような声色で答える努力をした。
「ユセ=ダルト=カイネ」
「ああ、歴史家の人だね? ところで、何を怒ってるの? ラン」
その一言がランの我慢していた何かを解き放った。
「知るか」
そう一言吐き捨てて、ランはエノリアの後へ続いていく。ミラールはその後姿を見ながら、少しだけ肩をすくめた。やれやれとつぶやきそうな顔をしながらついていった。
ユセの言ったとおり、通された部屋は広かった。入って真向かいの壁は大きな窓が嵌められていて、凝った模様が薄く刺繍されたカーテンがかかっている。それだけでも、この部屋の質がわかるというものだ。
右手の壁に扉が2つ、左手の壁に扉が一つあった。これが3つある寝室へ続く部屋なのだろう。そして、中心となる部屋が今4人が立っている部屋だ。4人でくつろぐには十分すぎるほどの広さで、備え付けられた長いすは寝台代わりになるほど大きい。これは、おそらくこの宿で高いほうの部屋となるはず。
ユセは3人をちらりと見ると、テーブルを挟んで向かい合わせにおかれた長椅子を示した。
「まぁ、座ってください」
そうして、ユセはそのまま奥へ進む。その先にお茶を入れる道具があるのを目にして、ミラールは手伝おうとした。だが、ユセはやんわりと笑って断る。
「ついたばかりなのですから、お疲れでしょう。座っていてください」
エノリアは言われたままに椅子に座り、またミラールもユセを気にしながらもエノリアの向かい側に座る。ランはユセを見つめていたが、ここまで自分がユセについてきているということを改めて思い直して、首を振りながら座った。
エノリアがいぶかしげにランをみる。その視線で言いたいことはよくわかったが、ランは少し視線に力を込めてエノリアを見た。
エノリアはますます困惑する。ランがどうしてそんな目をしているのか思い当たる節が無い。節が無いとすると、困惑は苛立ちに変わってきた。エノリアの視線に微量の怒気が加わりかけたそのときを狙ったように、彼らの視線をユセが運んできたお茶がさえぎる。
「ここの宿はいい葉を用意してくれてますよ。ナスカータの一品のようです」
二人の間にお茶の香りが割って入り、ゆっくりと落ちていく。その香りとユセの優しい声に苛立ちは癒された。ランは前傾していた体をそらして、背もたれへ力を抜いてもたれかかった。ユセも自分の分のお茶をおくとエノリアの隣で、ミラールと向かい合わせの場所へ座った。
エノリアとミラールがお茶を手に取るのを見て、にっこりと微笑む。
「道中、魔物には会いませんでしたか?」
ユセがそう聴くと、エノリアが答えた。
「ええ。一度だけ」
「問題はありませんでした?」
「ランとミラールが居ますから」
エノリアはそう答えて微笑む。ミラールが意味ありげにランに視線を向けると、本当に少しだけ表情が緩んだランと目があった。
「ミラール、さんですか」
ユセがふとミラールのほうへ顔を向けた。ミラールは、さきほどから自己紹介の機会をうかがっていたので、居住まいを正してユセへ向き直る。
「ミラール=ユウ=シスランです。ユセ=ダルト=カイネさんのことはエノリアから聞いてました。本も、知ってます」
「ありがとう。私もあなたを知っていますよ」
ミラールの人好きする笑顔に、ユセも負けずと微笑み返す。エノリアは二人を交互に見ながら、ほんわかした気分になっていた。
「シスランというお名前は、何度かお聞きしたことがありますよ。まぁ、私は音楽が好きなものですから……」
「そうなんですか?」
「ええ。この時期のこの町には多くの演奏家や旅芸人が訪れます。フュンランから来ている人も少なくないので、あなたが知っている人もいるのではないでしょうか?」
そういいながら、ユセは肘掛に肘を乗せて少し体を傾けて、顎を支える。
「もう遅いので人もまばらかもしれませんが、演奏は夜中まで続いてると思いますよ。広場のほうへ行けば、幾人かいるでしょうし」
ユセは促すようにミラールを見た。
「行ってみられますか?」
「あ、いえ、今日は別に……」
と言ってミラールはランを見た。物見遊山でここまできたわけではない。ランは構えるような緑の瞳でユセを見ていた。
「ユセ……さん」
「さん」の部分はどう読んでよいのか散々悩んだ末にかすれてしまったようだ。ユセはにこりと笑う。
「ユセ、もしくはカイネで構わないですよ」
「俺らはあんたが言ってた『忘れられた神殿』に行ってみようと思ってます。その前に、あんたの知ってること、教えてくれないか? いや、教えてくれませんか?」
「本当にまっすぐに聞きますね」
「それに調和神の名前さえ口にした。その名前は、誰にも忘れられているはずなのに」
「その名が本当だと信じるのですか? でたらめかもしれませんよ?」
ランはユセを見つめている。その一部分を疑うとか疑わないとかの問題ではない。ユセは目を細めた。
「貴方の目は……怖いですね」
ランが少しだけ問うように眉を上げた。その瞬間、張り詰めたような空気がほんのすこしだけ和らいで、ユセはほっと息をつく。
「……調和神の名は、本当の名ではありませんよ。エルドラは本当の名前ではないのです。だから、口にしても、なんの影響も無いですから」
ユセはそう言って、カップに口をつけた。一口飲んで、再びカップをテーブルへ戻す。
「この時期に、チュノーラへついたのは何かの導きでしょうね。この祭りのことを何かご存知ですか?」
「いや。巫女の誕生祭だとか」
ランがエノリアの方を向く。確認するような視線に、エノリアはこくりとうなずいた。少し自信を失った表情でユセの静かな表情を覗き込んだ。
「と、言いながら伝えられてきたものですよ。この祭りはチュノーラ独特のものです。チュノーラは、シャイマルークから一番遠い国です。ああ、いえ。地理的な話ではありません。道程がね。
それに、一番シャイマルーク王家から遠い者達が収めてきました。これは血筋的にです。だからこそ、残ったのでしょう。「忘れられた神」の名残が」
「忘れられた神の名残」
エノリアの呟きに、ユセはこくりと頷いた。
「この祭りは、忘れられた神を慰めるものです。それさえも忘れられてしまえば、意味のないものですけどね」
「何故、そんなことを知っているんですか?」
「ドゥエルーラ・トゥ・トエスタ」
ユセが呟き、少しだけ微笑んだ。
「言葉だけは、残るものです」
ランが眉を寄せる。その響きを聞くたびに、何かが心の中にひっかかっていた。その響きを聞いたことがある。
ずっと、ずっと昔。そして、最近も。
優しさと懐かしさ。そして、微量の悲しみ。
「この世界には、忘れられているものがたくさんあります。精霊語も徐々に失われ、調和神の存在も忘れられ、そして、闇魔術師《ゼクタ》の意味もね」
ランが口を開こうとしたのをさえぎるように、ユセは言葉を続けた。
「国の名の、本当の意味も。チュノーラの意味をご存知ですか?」
3人が3人とも顔を見合わせただけで、その問いには答えられなかった。ユセはその反応に対して落胆もせず、ただ淡々と先を続ける。
「ルスカも、ナスカータも、意味があるのです。国に名をつけるのを許したその人物のささやかな遊び心だったのかもしれません。
響きというのはね、最大の魔術なんですよ。その響きをたくさんの人の声で紡がせることで、いつまでも影響を残していくのです。
人の名も、物の名も、すべてに影響力があるのですよ」
ユセはそう言うと、片目に嵌めていた硝子に手をやる。
「時に、その響きは、全てをある人に知らせてしまう。だから、不用意に真実は語れないのです。あなたたちが、知りたいのなら、ゆっくりと探さねば。
最適な場所と、時間と、状況が重ならねば、響きにしてはいけない事実があるのですよ」
「ユセさんは……知っているんですか?」
両手を強く組み合わせていたエノリアが顔を上げてそう聞いた。さきほどまで、ユセを見ていた柔らかな瞳の光が、強くなっていた。
「その、今、起こっていることの……全ての原因を」
沈黙は重かった。ユセはエノリアの視線をまっすぐにうけ、そして、そらそうとしない。エノリアは喉を上下させる。彼女が組み合わせた掌はじっとりと汗ばんできていた。
「知っています。けれど、それはきっと貴女には意味のないことです」
「……教えてはいただけないのですね?」
ユセはかすれるような彼女の声に、微笑を返した。
そうして、それ以上彼は何も言わなかった。
「部屋は好きに使ってください。私は、少し外へ出てきます。話は、また後で」
お茶を片付けながら、ユセはそういうと部屋を出て行く。ランは長いすに無言で座っていたが、すっと立ち上がった。
「ラン?」
エノリアがそう声をかけると、ランは少しだけ二人を振り替える。
「ちょっと、出てくる。ミラール、エノリアを頼むな」
「わかったよ」
ランはユセの足取りを追おうと宿を出る。門番をしていた少年は交代したのか、もう少し年長の子供が居た。宿の外の暗さを見て納得する。太陽は既に沈んでいた。あの部屋で、どれくらい沈黙が続いたのか、ランはうんざりとしたため息をついた。
門を出てユセの後姿を捜そうとする。だが、その必要はなかった。門から出てすぐのところに、ユセが立ってこちらを見ていた。
「私に用があるのでしょう?」
笑っているのに、目だけが真剣な光を浮かべている。ランは自分の上着に手をかけて、襟を整えた。息を吸い込む。喉を冷たい空気が冷やした。
「話が、したい」
「わかってますよ。私こそ、あなたとだけ話がしたかったのです。伝わったのですね?」
「……?」
ユセは、口元に笑みを浮かべると、手で道の先を示した。
「少し、お酒でも飲みませんか?」
眉を寄せるランに、ユセはおかしそうに笑った。
「警戒しなくてもいいんですよ。私は、言葉以外に貴方を傷付けるすべを持っていないのですから」
そうして、ユセは声にせずに何かを呟いた。と、ランが気色ばむ。
「何故その名前を」
「……貴方が、言わなかったら、意味のない言葉ですよ。そう、貴方さえその言葉を言わねばね」
ユセは改めてランを促した。ランは大きく息をついて、そして、歩き出した。ユセとの間に十分な距離を置いて。そうでもしなければ、飲み込まれそうな気がしていた、その空気に。 |
|
| |
|