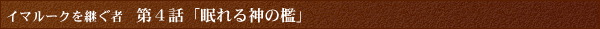 |
| |
| I 忘れられた神へ |
| |
濃い影が落ちていた。日差しの強さに比例して、大樹の影は一層強く。また、目を馳せれば影を境界にし、周りの風景が……花が芝が噴水が、痛いほどまぶしかった。
だが、目を細めた理由はそれ以外にあった。
何と問われたのか。それを理解しようとして眉間に皺を寄せたからだ。おそらく、不快感を顕にした表情となっていたのだろう。目の前の二人の女性の目がたじろいだ。
金色と銀色の目。光を宿した2対の目が、微笑み以外の理由で細められたのをはじめてみたような気がした。いつも穏やかに微笑むようにと、教えたのは私と……この宮という地にある空気であったろう。
影の下に置かれた円卓に、上品で繊細な植物の模様が刻まれたカップが3対。もう、立ち上る湯気は消えてしまっていた。
彼女達は不安そうに、私の名を呼んだ。私は首を振る。少しでも彼女達を安心させようと微笑んだ。
(多分それは失敗だったのだ)
彼女達もぎこちなく微笑んだ。
(何も伝わらなかったのだろう)
彼女達は同時に自分のカップに手を伸ばし、そして、冷え切った茶を口に運んだ。
それから、ちょうど5日後だった。
私は、自分よりも年若い娘達を止めることは出来なかった。
彼女達は私よりもずっと純粋だった。純粋に生きるからこそ、長く生きることは出来なかった。
二人、繋いだ手はとても冷たかった。私はそれに触れて、涙流すことさえ出来なかった。ただその手に手を重ねて、そして、その冷たさを心に深く刻むことが、私に出来る事だった。
光《リア》が死の選択をさせるなど、愚かなことなのです。
私はそう刻み込んだ。
泣いてはいけない。悲しんではいけない。その代わりに誓う。
愚かなことなのです。生きねばならぬのです。
違う、生きねばならぬのではない。
(生きていてほしかった)
現実にしてほしかった。万人のために生きるということが可能だということを、信じさせてほしかった。
私は信じている。
それが可能だということ。
信じていると何度も頭の中で繰り返した。
私は大地の娘《アラル》。この世界に生きる人々全ての幸福を願って生きていくために、生まれた娘。
濃厚な花の香りがその部屋を満たそうとしていた。その前に、窓をそっと開く。入り込む風はカーテンを力なく揺らす程度、心地よいやわらかさで、彼女の体を蝕むことはないであろう。
それでもセアラは開けた窓の隙間を神経質に調整した。香りがほどよく残る換気。それを確かめていると、背後から掠れた声がした。
「……夢を、見た」
セアラは声のするほうを振りかえり、足音を極力忍ばせて寝台の近くにある椅子に腰掛けた。厚く温かな毛布をかけられ仰向けに寝ている人物を覗き込む。彼女こそ、この部屋の主人であるダライア=ファン=ディラアラル。大地の娘《アラル》と呼ばれる存在であった。
金と銀の瞳をうっすらとあけて、天井を見つめていた。
「どんな、夢を?」
セアラは優しく聞き返す。そのような柔かな言い方をしたのは、久しぶりだと彼自身が感じていた。
「……ああ……、ラスカフューネの香りがする……」
うっすらと目を閉じながら、ダライアはそう呟いた。セアラの問いに答えたものではなかったが、セアラはもう1度聞きなおさなかった。
ダライアはもう1度目を開く。今度は、さきほどよりもはっきりとした意識をもった瞳でセアラを見た。
「セアラ?」
「そうだよ」
今気づいたというようなダライアに、セアラは口元に笑みを刻んでみせた。ダライアはその笑みで少し安堵したようだった。大きく息をついて、自分の置かれた状況をようやく把握する。
「……どうしたのだろう?」
「倒れたと聞いたよ」
「そうか……」
「気分は?」
「特には」
そう答えて、ダライアは自分の体の感触を探った。ふといつもよりも胸の辺りが苦しいことに気づく。だが、改めて意識すればという程度であって、騒ぐほどのことでもなかった。声に張りが無いことさえ、彼女にとっては些細なことだった。
だが、第3者のセアラの目に映るのは、あまりにもはっきりした前触れであった。セアラはダライアを見つめ、その体からいつもの力が感じられないことをはっきりと認識していた。だが、本人にはいえない。
酷だからではなく、彼女の瞳はそれをすでに受け止めていたから。
ダライアは薄い唇に笑みを刻んだ。
「そうか、だからあんな夢を。しばらく、そう、もう、10年近くみていなかったな……」
独白のような言葉の綴りを、セアラは黙って聞いている。足を組みなおし、視線は窓際でゆれるカーテンの動きを追う。
ゆらゆらと風に任せて揺れる布の軽やかな動きを追いながら、頭に浮かんだのは、うっすらとした少女の輪郭。金色の瞳と髪。銀色の瞳と髪。報告を受け、この王宮に参上したときは既に遅く、ただ何かに耐えるように顔をまっすぐに上げていたダライアの強い瞳の色だけが強く印象に残っている。
「エルラ、アーシア……。良い娘達だったのに」
「辛い、出来事だった」
セアラは目を細めた。
「止める事が出来なかった。助けを求めていたのに……。私だけのうのうと生きて、生き続けてしまった……。セアラ……」
名を呼ばれて、セアラは再び視線をダライアに向けた。完全に閉じられたダライアの瞳の端から、一筋の涙が落ちた。
「私は死ぬのが怖かったのだ……。だから、できなかった……」
セアラはそっと彼女の頭に手をやる。黒い髪に少しだけ混じった白い筋。だがとても74歳になる女性の髪だとは思えぬほど艶やかだった。子供をあやすように、髪を撫で、白い指を優雅な動きで移動させ、彼女の涙をぬぐった。
「それは当たり前だよ、ダライア。誰もが怖い……。それに、あれは誰も悪くないんだよ。君はよく耐えた」
ダライアは目をさらに開く。赤い瞳はここ数年見ていないほどの優しさに溢れていた。
「おかしいな、セアラ。とても優しい」
「変だねぇ。私はいつもとっても優しいじゃないか」
片目をつぶってみせるセアラに、ダライアは小さく微笑んだ。セアラは眉をしかめる。
「どうして笑うんだい」
「いや……」
ダライアはごまかすように、視線をそらした。その視線の先には花瓶から今にもあふれてしまいそうな花の色。
「ああそうか、もって来てくれたんだな。だから、香りが」
セアラがダライアの視線の先を確かめるように一瞬振り返り、そしてまたダライアに向き直った。
「ようやくゼアルークが名前を覚えた花だよ」
「最近、よく持って来てくれるな。昔は……」
金と銀に昔を懐かしむ色を浮かべて、ダライアは少しだけ目を細めた。
「あの花は嫌いなのかと思っていたのだが」
「私がかい?」
「そう」
ダライアはそう言って、くすりと笑った。
「城へ来て、私に会いに来てくれるときはいつも、花を持ってきてくれた。だが、いくらラスカフューネが大輪の花を咲かせる時期でも、もってこなかったよ。
そう、あの花を持ってきてくれるようになったのは、また城へ帰ってきてからだ」
「そうかなぁ」
形のよい鼻の頭を掻くしぐさをした。
「花の束を抱えて、来てくれるのをいつも楽しみにしていたよ。どんな花も、あなたにはよく似合った」
かすれるような声でつぶやくダライア。セアラが視線を向けると、彼女は目をつぶっていた。
「だけどいつもラスカフューネを持ってきてくれたら、と思ってもいた。あなたにはとてもよく似合うだろうと」
「そんなことを考えていたのかい」
「ここは美しい花が咲くから。その花で時間が経つのを感じるんだ。退屈になったら花を見つめて、誰に何がよく似合うのか考えるのが楽しかった」
ダライアはくすりと笑った。
「ノーラジルには白いシュースネス。……彼女の結婚式には、たくさんの白い花を贈った。あなたは青い花ばかり集めて贈っただろう? 白と青の花に囲まれて、とても綺麗だったな」
「ノーラジル=ロード=キャニルスか」
セアラもまた懐かしさに目を細めた。脳裏に浮かぶ黒い髪、青紫の瞳。とても美しい女性だったが、めったに笑顔を見せなかったことからから、「冷たい花」とも呼ばれていた。キャニルス家の先々代、もう今は先々々代当主となる女性だ。
「怒っている顔しか覚えてないよ」
「あなたとはいつも口喧嘩ばかりしてたからな。ああ、でもノーラジルが一方的にあなたに噛み付いてただけか。あなたがからかったりするから」
「かわいかったもんでね」
一瞬だけ、セアラの瞳も懐かしさで細められる。唇にふと浮かんだ笑みがあたりの空気を和らげた。
「とても羨ましかった。ノーラジルが結婚するといった時は、とても心配だったけれど。彼女は幸せになれたな」
「ユラが幸せにしたんだろう」
ささやくような声で言うセアラを、ダライアは探るように見つめた。
ノーラジルの結婚相手をほぼ無理矢理決めて実行させたのが目の前の人物であることをダライアは知っている。だから「心配した」とあてこすりのつもりで言ったのだ。それに答えたセアラの声は心底安堵しているような響きだった。
少しは気にしていたのかと思うと、少しおかしくなりダライアはくすっと笑った。
「何」
「いや、別に」
セアラに結婚相手を決められ憤慨していたノーラジルを思い出す。地宮《ディラノアル》に、怒りの感情をあらわにした赤い顔で、乗り込んできた。あれだけはっきりとした表情を見たのは後にも先にもそれ一度きり。
ユラは……才能と力はあったが、女性関係に関してはあまり評判のいい魔術師ではなかった。でも、彼女と結婚してからは、本当に彼女だけを見て生きていたと思える。
ノーラジルとユラ。一緒にいた姿をダライアは目に浮かべた。
いつごろからか、ノーラジルの顔に穏やかな笑みが浮かぶようになった。結婚してからもときどき私の元を訪れてくれたノーラジルは、ゆっくりと変わって行った。
ユラのことを言葉少なに、そして、幸せそうに語る彼女を羨ましいとも思ったことがある。たった一人授かった子供を私に抱かせてくれたときも。とても羨ましかった。
「もう一度会いたい。ノーラジルに」
かすかなつぶやきは、その音の大きさ以上に部屋に響いた。セアラは椅子に浅く座りなおし、ダライアを覗き込んだ。
「……ダライア」
「充分生きた」
目をつぶったダライアの顔の輪郭を、セアラはたどるように見つめる。皺が深く刻まれた顔。だが、そこに気品は顕在し、衰えない。いや、この女性は年を重ねるごとにその気品を深くしていった。
「あの事件から18年になる……。私はそのときも老人で、あなたはそのときもその姿だった」
ダライアの言葉に、セアラの笑みがゆっくりと引いていった。瞳に浮かんでいた笑みは、ダライアの言葉を咎めるような光に変わり、でも、少しだけ含まれた静けさが視線を柔らかなものにしている。その深い瞳が語る言葉を、ダライアは首を振って受け止めた。
「いや、74年も生きていて、私はまだ若いなどと言う方がおかしなことだよ。この皺皺の手……」
毛布の上に重ねていた手を少しだけ上げ、また力尽きるように落とす。セアラはその手をとり、自分のほうへ引き寄せた。
「外見の老いや美醜が私に何の意味を与えると?」
セアラはダライアが皺皺だと評した手の甲をそっと撫でた。
「貴女は、いつまでたっても美しいよ。年を重ねても、その内面の強さと賢さと美しさは変わらない。美しい……」
「セアラ」
「死ぬなど、言葉にせず。まだ、生きていてくれないか」
「新しい大地の娘が産まれる」
そう言葉にしながら、彼女の目はセアラに同意を求めた。だがセアラは静かに首を振る。
「ダライアまでそんなことを言っては駄目だ」
「そうじゃない。私は『娘』という存在であったことを誇りに思っている。その力は脆弱でも、笑えば多くの人が喜んでくれた。そんな存在には、なりたいと願うだけでは、なれないものだ……。
そう気づけば、この生活も悪くない。疑問に思わなかったわけではない、あなたに問おうとしたこともある。
だけど、私がここにいるだけで、一人でも幸せを感じてくれるなら、それで構わないと思った」
セアラはダライアの手を握り締めた。そして、その甲に口付ける。
「セアラ? どうした」
だが、セアラは黙っていた。ダライアの甲に唇を押し当てたまま、身動きしない。
「セアラ」
「……生きていてよ、ダライア……」
幼子のような懇願の響きに、ダライアは驚いた。だが、その瞳に含まれた驚きは慈愛に変わる。セアラの乳白色の髪を空いた手ですいた。何度も何度もそうやって彼の髪をすいてやる。
慈愛に満ちた瞳は、彼を見つめていたけれど、彼の懇願に答えることはなかった。
「人は」
しばらくして、顔を上げた彼に、彼女はぽつりとつぶやいた。
「死ぬ。いつか、必ず」
そのときのセアラの表情を、ダライアは死ぬそのときまで忘れることはなかった。 |
|
| |
|