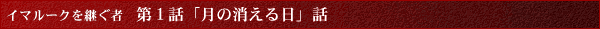 |
| |
|
◇
|
| |
「エノリア。私と飲む最後のお茶は、最初に一緒に飲んだものと一緒よ。何を入れようかしら。花のジャム?ラミュの?」
月の娘《イアル》シャイナ=フィン=シャイアルは、朧月のような印象を与える女性だ。はかなく、淡く、優しく。娘とし て宮に引き取られる者は、両親の名と顔を知らない。だが、シャイナは知っている。彼女はアライアルにある国の一つ、フュ
ンランの王女として生を受けたからだ。王族の血をひく証である気品も彼女のもつ魅力の一つである。
「じゃあ、ラミュのジャムを」
エノリアはそういうと、感慨深い顔をして親友の顔をみた。シャイナはその視線に気づいてか、ピンク色の唇を開いた。
「本当に、行くのね」
「……うん」
くるくると指でスプーンを回しながら、シャイナはつぶやいた。
「止めたりはしないわ。協力したのは私ですもの。心配はするけれど」
「ありがとう」
言葉と渡されたお茶と両方に述べて、エノリアは温かいお茶を一口のんだ。シャイナはカップを手のひらでつつんだ格好で、
しばらくエノリアの動作を見ていた。
「……幸せ、なのかしら」
唐突にシャイナはつぶやいた。エノリアはその言葉が誰のことをさすのか一瞬分からなかった。自分か、それとも、月の娘 《イアル》として生まれたことを誇りにしている彼女か。
「壁の外は幸せかしら」
「少なくとも、私にはね」
エノリアはそれ以上の答えを見つけることが出来なかった。
「私は、ここしか知らないから」
シャイナは一つも口をつけていないカップを卓上に戻す。揺れる茶色の水面に、卓上に飾られた薔薇の花びらを落 とす。
「あなたをうらやましいと思うのは、月の娘《イアル》としては失格かしら」
側に控えていたシャイナの侍従・ローザが少し目を見開いた。何か言いたげに開いた唇は、一言も発せずに閉じられたが。
「失格かどうかは分からないけど。シャイナはここに居場所があるわ。でも私は……。光宮《ヴィリスタル》に居ながら太陽の娘
《リスタル》であることさえ、認められなかったから、シャイナのようにここに居場所がないのよ」
エノリアにはそう言うことしかできない。シャイナはその言葉に少し微笑んだ。エノリアのこの四年間を見てきたから、シャ
イナは自分の呟きを、贅沢な考えだととったのだろう。
「私には、ここが幸せなのね」
「……たぶん……」
自分には理解できないだろうけど、と思いつつエノリアはシャイナにそう答えた。月の娘《イアル》であることを幸せだと思えと教育されて
きたシャイナにとって、エノリアは異質だっただろう。
太陽の娘《リスタル》の姿を継いだことに反抗し、壁の向こうに自由を求め続けた。それはエノリアには当然のことだが、シ ャイナには真に理解は出来なかっただろう。多分、これからも。
エノリアは沈黙を紛らわすために、カップを口に近づける。中身はほとんど残っていなかったが、少しだけ口に含んだ。
幼少期の教育とは恐ろしいものだと、エノリアは思った。シャイナとエノリアの違い。ひいては、同じ姿を継いだナキシスと
エノリアの違い。考え方も何もかも反対へ向かってしまった。壁の向こうに出られないことを、疑問にさえ思わない。ただ、髪
の色と目の色だけで、聖女として祭り上げられることを、疑問に思わない。エノリアはシャイナを見つめた。
それでも、シャイナはエノリアのことを理解しようとした。エノリアの自由を求める心に協力してくれた。
「ありがとう…」
「え」
エノリアの小さな声を聞き取れなくて、シャイナが少し体を前に傾けた。
「ありがとうって、言ったのよ。シャイナがいろいろしてくれなかったら、こんなこと出来なかったもの」
「いいの。エノリアがそれで笑ってくれるなら」
シャイナの答えはエノリアにとっては心外だった。
「私、笑ってなかったかな」
笑わなかったことなんてなかったと思うけど…。シャイナはかすかに頷くと、エノリアの後方に控えているリーシャに目を向
けた。
「本当には、笑ってなかったわ。そう、言っていたのよね、リーシャ」
リーシャは頷き、シャイナの後方に控えていた侍従のローザもそれに習うように頷いた。
「今日は、本当に笑ってる。嬉しいのよ」
エノリアは恥ずかしくなって思わずうつむいた。心の中を見透かされているような感じは、あまり居心地のよいものではない
らしい。それに、自分の演技の未熟さを指摘されたようでもあった。しかし、見てくれる人は見てくれているのだというのは、
嬉しい気もする。この宮で、自分はたった一人ぼっちでいたわけじゃないのだと、今更ながらに実感した。この人たちがいたか
らこそ、まだ堪えることが出来たんだ。
「そろそろ、いくわ」
たいした会話も出来ずに、エノリアは立ち上がった。最後だと思う。でも、最後だからと言って何を話せばいいのか、そんな
こと分からない。特に何もないし、何もないことに居心地の悪さは不思議と感じなかった。
「荷物には、路銀が。あと、これを」
シャイナは、部屋の片隅に用意していた一振の剣をローザから受け取った。
「軽いから、邪魔にはならないわ」
すっと鞘から剣を抜いた。美しく光る刀身にシャイナは唇を軽く押し当ててキスをする。
「月の娘《イアル》の祝福を。この剣が多くの災いを振り払い、持ち主を守護するように」
誰もが望む娘の祝福のキスを受けた剣を、エノリアは受け取った。剣の腕前は悪くないと思っている。剣の扱いも心得なくて
はいけない侍従のリーシャが、エノリアの先生だった。リーシャも侍従の中では、剣の扱いは優秀なほうだが、エノリアはその
先生を半年で超えてしまった。
「ありがとう」
「抜け出したことがばれたら、ゼアルーク王はきっとあなたを殺そうとするわ。人々にばれる前に、消そうと……」
シャイナはそう言いながら、心の中で首を振った。こんなことを言いたいのではないのに……。
「ここにいても同じことをいつかはしたでしょうね。だから、逃げてみせる。大丈夫。わたし、したたかなのよ」
エノリアもシャイナと同じことを感じていた。こんなことを言いたいのではない……。
シャイナは次の言葉を捜した。あたりを見回しても、言葉は出てこなかった。エノリアも同様だった。つまらない毎日の中で
も、宮に好きなものは出来た。リーシャとシャイナ。大切な友人達。だけど、いま、何かを言わねばならないのに、言葉など出
てこない。
「もう、いくね」
荷物を持ち、フードをかぶって、エノリアは道案内するローザのあとに続こうとした。そのとき、シャイナの両腕がエノリア
を後ろから包み込んだ。
「元気で。必ず、幸せになって……!」
そっと手のひらに渡されたのは、シャイナの耳飾の片方だった。エノリアはそれを見るとすぐに自分の耳飾をはずしてそ こにつける。はずした耳飾はシャイナに渡された。
「必ず」
エノリアの金色の目は強い意志の色が見えた。リーシャが隣でしゃくりをあげる。エノリアは喉と目頭が熱くなるのを感じた
が、首を振ってそれをごまかそうとした。二人に無理をして微笑むと、その部屋を勢いのままに飛び出す。その後ろ姿を送り、
シャイナはエノリアの耳飾を耳につけた。片方は青で片方は白。その組み合わせはどんな一対の耳飾よりも美しく見えた。
行ってしまった……。
シャイナは扉がゆっくりと閉るのを、ぼうっと見つめていた。
離れていく。この手から。自由を求めて、光が……。
自由ってどんなものなのだろう……。
壁の外に何があるのだろう。それを、私は知ることができずに一生を潰えるのだろうか。月の娘《イアル》として自分のこと
は何一つ望まずに。あの人ともう一度逢うことも出来ずに。あの、音楽祭の夜に見かけた人…。
エノリアが来るまでは、それに疑問を抱いたりしなかった。だけど、彼女の光は自由奔放で力強く、意志の強さが光となっ
てあふれていた。どこに、あんな強さがあるのだろう…。
外には、それがあるのだろうか。
私も、得ることが…。
「シャ、シャイナ様!」
シャイナの思いは、リーシャの声によって中断された。気がつけば、目の前に黒いフードをかぶった人間が立っていた。
(人間?)
否、そこから漂うのは闇《ゼク》。フードの合間から見える瞳からは、闇《ゼク》以外のなにものも感じられない。体格から
いって男性だろう。だけど、人間であるとは思い難かった。
「何者」
闇《ゼク》の要素のみ持つ人間。創造神《イマルーク》も闇《ゼク》の要素からは生き物を作ることが出来なかったという。
ごくまれに、闇《ゼク》の要素を持つ者が生まれるが、そんなにそれは強くないし、属性は別にある。闇《ゼク》は人のなかに
とどめるには濃く、人の心を侵食する。だから、闇魔術師《ゼクタ》はめったに現れず、しかも、それは禁忌とされているのだ。
その闇《ゼク》で出来たような人だ。絶望や失望を闇《ゼク》にかえ、体にため込んでしまう人がいるのは事実だが、それを
物質化して魔物にしてしまうというのは、明らかに『悪いこと考えたりしてたら、ろくなことはないよ。魔物がうまれるよ』と
いう教訓じみたものでしかない。それが十七年前に魔物が発見されてからは、本当の話になっていた。どこからともなく、闇《ゼク》
のみを要素とした生き物が突然現れる。だが、すべて獣の形をしていた。このように人間の形をしているというのは聞いたことがない。
闇《ゼク》を属性に持つもの、それは明らかに創造神《イマルーク》の創造物ではないといわれている。シャイナ自身、話に
聞いてはいたが、実際に見たこともなかった。今までは。
「月の娘《イアル》よ。迎えにきた」
それは話した。その声は低くもあり、美しくもあった。人の心を魅了する魔性の響き。
「二つ目の太陽は解き放たれた。我が君はもうすぐ目覚める」
「我が君?」
恐ろしさも忘れてシャイナは問い掛ける。リーシャはそれに惑わされなかった。自分だけで立ち向かうのは無理だととっさに
判断し、助けを呼ぼうと扉に駆け寄る。だが、その男はそれを許さなかった。すっと動いた腕が、リーシャの前に出されると、
リーシャの動きが止まった。そして、その場に崩れる。
「リーシャ!」
「死んだ。もう」
男はその手を、シャイナの顎にかけた。呆然とリーシャを見つめているシャイナを自分のほうを向かせる。瞳は闇の色。だけ
ど、シャイナは見つめてしまう。たった今、リーシャを殺した男なのに……目が離せない。
「我が君は光《リア》を所望する」
「我が君って一体何」
シャイナは男を睨み付けた。宮で、蝶よ、花よと育てられ、人々から愛されることだけを知り、また人々を愛するだけだった彼女の瞳に、そんな光が浮かぶのは初めてだった。
「我が君は、この世界を破壊するために目覚める。放たれた光《リア》は闇《ゼク》を濃くし、人々の心の影を濃くする。われ
われは、人の闇《ゼク》が源。そして、我が君も」
「エノリアが、その放たれた光だと?」
「二つも太陽が現れたときから、それは始まっていた。そして今、一つが再び宮から解き放たれた」
シャイナは眉間に皺をよせる。光が闇を強める? そんなこと、聞いたことがない…。
「そして、お前は私と共に世界の滅びをみる。それが、イマルークへの報復だ」
「何を言っているの。創造神《イマルーク》に報復?世界の滅び?そんなことありえないわ」
シャイナは首を振った。男は手を放さない。
「イマルークなど、苦しめばよいのだ。それが、我が君の望みなのだから」
「創造神《イマルーク》はすべての源。あなた達の存在を許しはしないわ」
毅然としたシャイナの瞳を男は見返した。誰もがひるむだろうその目の光に、少しもおじけずに男は見つめ返していた。
「イマルークは我らの存在に関係ない。我らが何から生まれるか、分かるか。闇だ。人の闇だ。欲望・絶望・憎悪すべて。その
者の望みの姿で、その者の望むことをするために生まれるのだ。そして、なぜ私がここにいるか、分かるな」
男はフードに手をかけた。そして、その下に隠された顔をさらす。漆黒の髪・闇色の瞳。
シャイナは息を呑んだ。そんなこと、ありえない。この顔は…!
それなら。
シャイナは心の中で否定したかった。だけど、
「私が……呼んだと……」
「私の手をとれ。月の娘《イアル》よ。月宮《シャイアル》を我が手に」
「私が……」
「シャイナ」
名前を呼ばれて、シャイナは操られるように、白い手をゆっくりと差し出した。男の手がその手のほうへ差し出されたが、男
は自分からその手を握ろうとはしなかった。シャイナの心を試すように。
「貴方、名前は」
ふと、シャイナがたずねた。男は無表情だったその顔に、かすかに笑みを浮かべた。
「ザクーと呼んでいたではないか」
それを聞いて、ああ……と思った。シャイナは操られるようにその手をとる。それが、どんなことを現すのか、そんなこと十分
に承知していた。しかし。
シャイナの存在はその瞬間、月宮《シャイアル》から消え去った。どこに行ったのか、分かる者はいない。
去年、だっただろうか。そう、あれは音楽祭だった。いろんな人々が楽しめる大きな音楽会。一般にも公開されて、いろん
な音楽家達が美しい音楽を奏でてた。
その中でも、一際美しい音楽を奏でる青年がいた…。まだ、音楽家になる勉強をしている途中らしいと噂で聞いた。でもそ
の音楽は見事で、もう、どんな音楽家達にもひけはとらなかった。
なぜか、私は興味を持って彼を観察していた。そうすると、早早に退散するみたいだった。一言声をかけたいと思って、外に
出た彼を追いかけて露台に出た。彼の傍らには腰に剣を下げた青年が側にいたけど、構わず声をかけると、音楽家の彼とそ ばにいた彼が振り仰いだ。
その時、剣士の青年と目が合った。
分からない。分からないけど……。忘れられない、ただそれだけ。
ふとした瞬間に思い出す……それだけ……。
その青年に、この闇の者はそっくり……。
私が考えていることが、そうだとは言えない。
でもこの闇の者が、結界をものともせず急に現れたということは。彼の姿にそっくりだということは。
それに私は彼をこう呼んでいた。《ザクー》【彼の人】と。
私が、私が…!
創造神《イマルーク》!私は…!
そう、誰にも負けない思いを抱いていたのかもしれない。
闇を呼ぶほど。
エノリアが、去ってしまった。
エノリアは、自由になった。
でも、私は…。
わたしは……?
ローザが部屋に帰ってきたとき、まずシャイナが居ない事が気になった。予定よりも早くに、リーシャが倒れているのも気
になった。
「シャイナ様?」
ローザはふと、机にあるものに目をやる。睡眠薬の入った紙包みは三つ……。手に取り全てにまだ、中身があるのを確認して、
そこで事の重大さに気がついた。
倒れたリーシャに駆け寄り、その手を取る……。
ローザはしばらく、声にならない声を出し、目をこれ以上は開けられないと言うほど見開いて、リーシャを見つめていた。 そして、やっと声が絶叫になったとき、全ての意識を放棄したのだった……。
|
|
| |
|